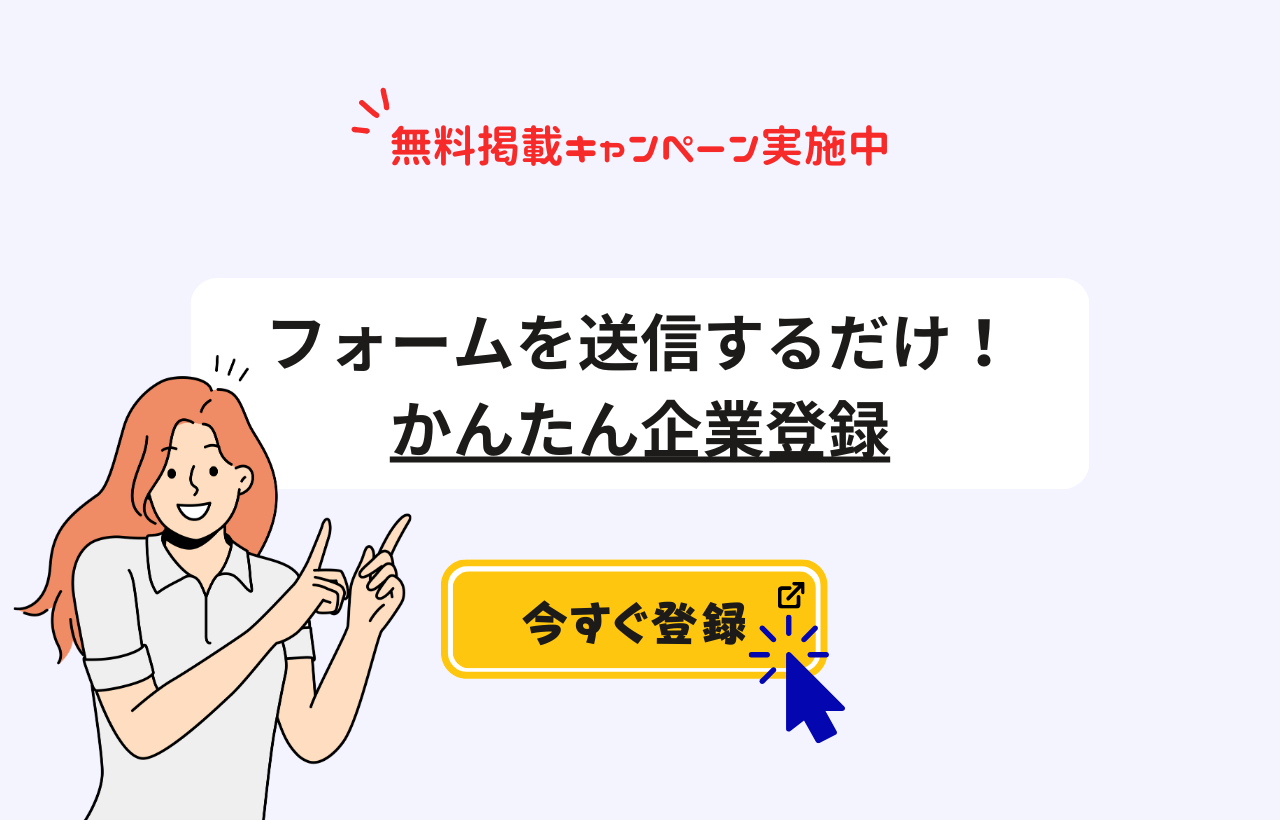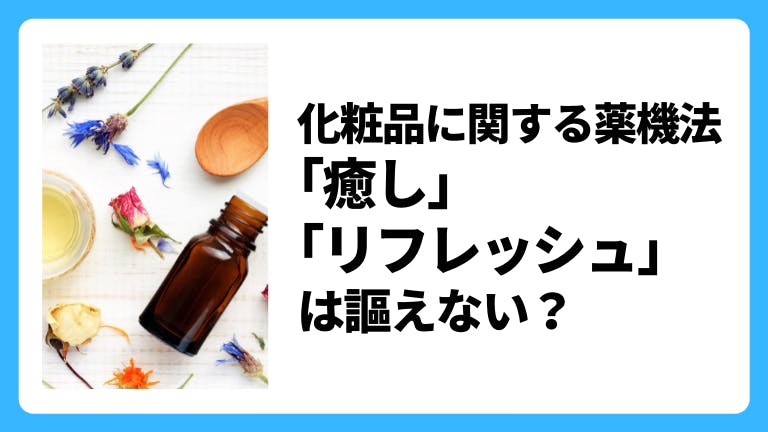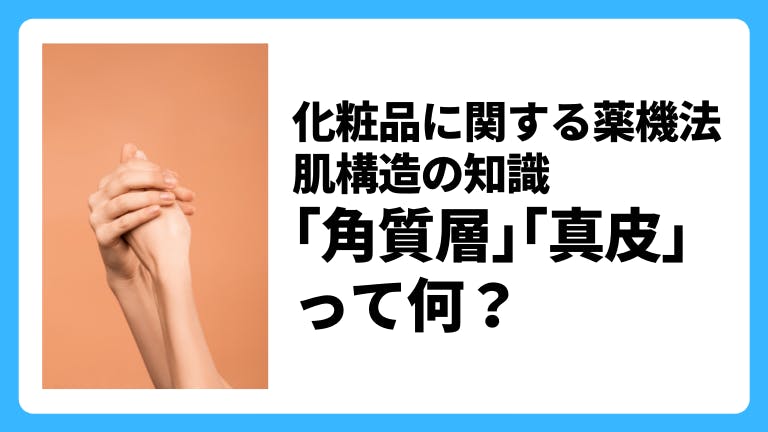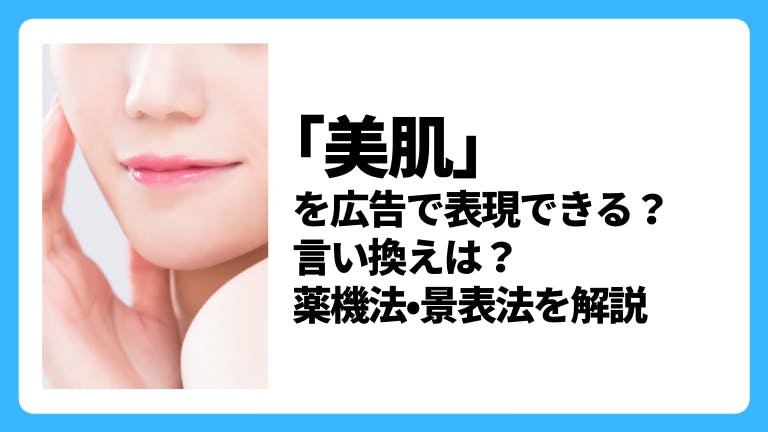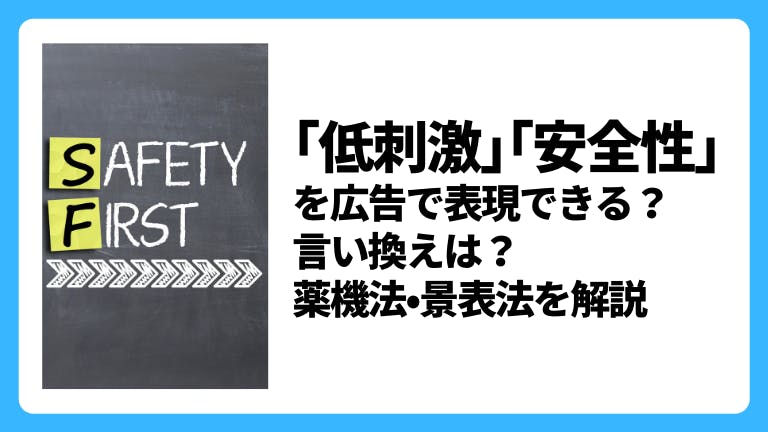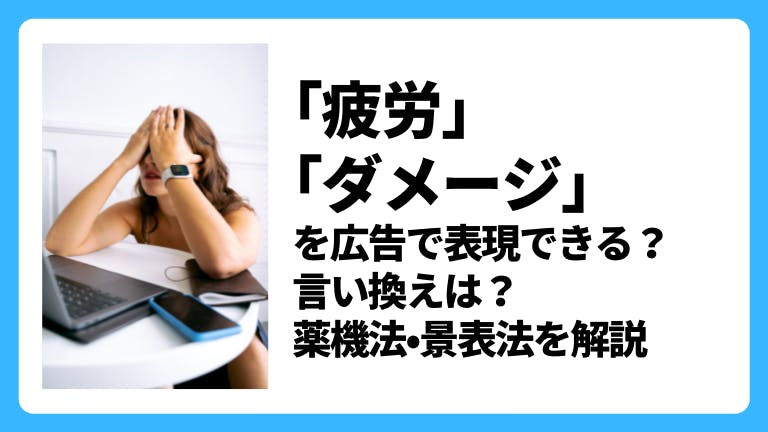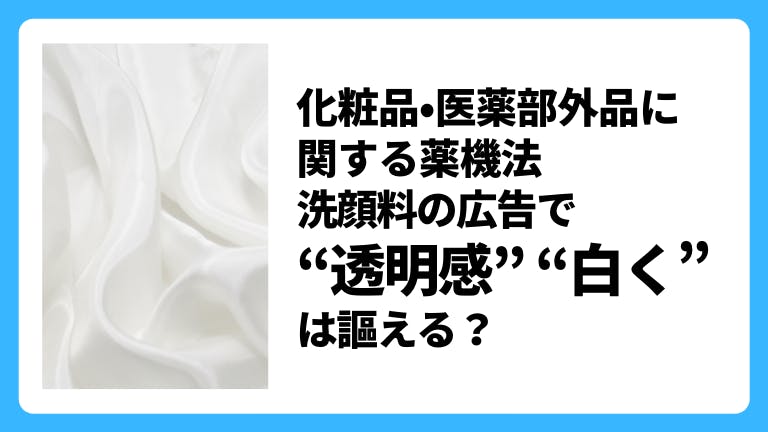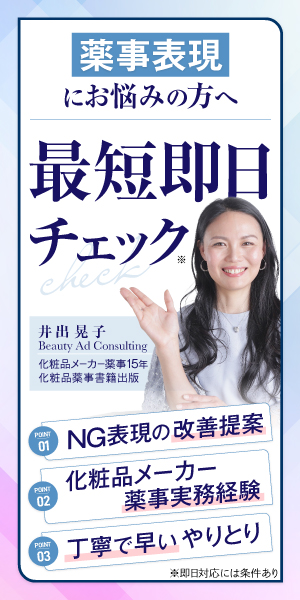最終更新:2024/07/04
化粧品や健康食品で用法、用量は記載できる?薬機法との関連性
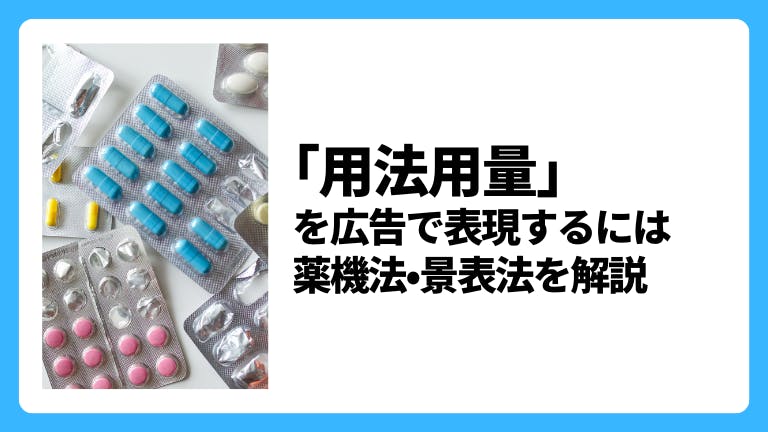
「用法、用量」という言葉から、薬の飲む量やタイミングなどが思い浮かぶと思います。 医薬品の言葉であるという印象を持たれる方もいるのではないでしょうか。 実際には、化粧品や食品でも用法、用量の概念があります。 今回は、化粧品や健康食品で用法、用量の記載は可能か、薬機法とはどのような関連があるのかを解説します。
薬機法・景表法とは
はじめに薬機法と景表法に関して簡単にまとめてみました。 どちらも広告表現をする上で非常に重要な法律です。 一つずつ解説します。
H3薬機法
薬機法とは、医薬品医薬部外品化粧品などについて製造・販売・安全対策まで規制し、その適正化をはかることを目的としたもの。
薬機法では広告規制があります。
「虚偽・誇大広告の禁止」「未承認の医薬品等の広告の禁止」という規制です。ウソやオーバーな表現、医師が保証したと誤解を与える恐れのある広告が禁止されています。
規制の対象は「何人も」となっており、広告主以外にも、広告代理店やアフェイエイター、インフルエンサー、ライターなどの個人も対象となるのです。
薬機法には罰金や懲役という罰則があります。
また、許可の取り消しや業務停止命令が出ることもあるのです。
H3景表法
景表法(景品表示法)とは
- 消費者向けの不当な広告を規制するもの
- 消費者向けの販売における過大な景品提供についての規制
の2つからなるものです。 例として、実際よりも優良であるかのような広告表現をするのはNG。 また、商品に付ける景品が決まっている限度額を超えた場合もNGです。 景表法の対象は、現在行われている表示・広告はほとんど網羅されています。 もし、景表法を違反してしまうと行政から措置命令がきます。 従わずに、違法名広告表示を継続した場合に、懲役や罰金が科されるのです。
用法、用量とは
服用時期、服用量、服用回数などの、使用方法や使用量を「用法、用量」と言います。 薬の場合は薬袋に、一般用医薬品(処方箋が無くても購入できるくすり)の場合はパケージに記載されています。 用法、用量が決められている理由は、薬の有用性を最大限に発揮させるためです。 用法、用量を以外にも使用上の注意して、副作用、高齢者や妊娠中の方が服用する際の注意点などの表記されています。
用法、用量と薬機法との関係性
薬機法68条の2第1項では、医薬品製造・販売業者等は医薬品を製造販売した後も医薬品の有効性及び安全性に関する事項その他医薬品の適正な使用のために必要な情報を収集・検討するともに、医師・薬剤師等の関係者に対しこれを提供するよう努めなければならないとされています。 薬機法では、もし記載していなくても、「努める義務」であるので、このことを理由に罰則を受けることはありません。
H3 用法、用量が広告表現に使用できるもの、できないもの
医薬品では問題なく使用でき、化粧品でもよく表記されています。 健康食は薬機法上では、一般食品の扱いです。 そのため、用法、用量を記載してしまうと、医薬品と同じ扱いになってしまうため、薬機法に抵触する恐れがあるでしょう。 健康食品と似ている分野で栄養機能食品があり、薬機法上では保健機能食品に該当するものがあります。 この栄養機能食品では、摂取の時期、間隔、量などの方法を示すことについて「食前」、「食後」など特に医薬品的な誤認を与える表現でない限り、医薬品的用法用量には当たらないと考えられています。 同じ食品でも、薬機法上の扱いが変わりますので、常にチェックは必要です。
H2 化粧品の用法、用量の規制とは
医薬部外品、化粧品に添付する文書又はその容器若しくは被包には、用法・用量その他使用及び取扱い上の必要な注意等が記載されていなければならない。 (法第60条、第62条準用同法第52条) このことから、化粧品を入れている容器や、被包に記載することが必要です。 もし、化粧品が入っているボトルや箱が小さく、記載事項を表記できないときは、外箱やタグ、ディスプレイカードを使って表示することが例外的として可能です。(薬機法施行規則225条参照)
化粧品での違反例
化粧品の用法、用量についての基準は下記です。
❝用法用量についての表現の範囲の原則 化粧品等の用法用量について、承認を要する医薬部外品にあっては承認を受けた範囲を、 承認を要しない化粧品にあっては医学、薬学上認められている範囲をこえた表現、不正確 な表現等を用いて効能効果又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある 広告をしてはならない。❞(医薬品等適正広告基準第4の3(4))
広告表現に用法、用量を使用するときは、嘘の表記や誇張したような広告にならないように、認められている範囲で伝えることが必要です。
以下が認められない表現になります。
- 天然成分を使っているのでいくら使っても安全ですという表現
- どんな使い方でも大丈夫と誤解するような表現
- 複数の用法用量がある場合で、一つだけ、特定の用法用量を協調するような表現
- 〇〇専用という表現
- 薬用という表現
適正な使用を促すため、化粧品の用法、用量は正確に示しましょう。
回避方法(参考)
化粧品で用法用量を表記する際の例です。
- 清潔なお肌に適量なじませてご利用ください
- 洗顔後に化粧水でお肌を整えたら、パール1~2粒を目安にお肌になじませてください。
などの表現はOKです。
パールの他にも硬貨やさくらんぼで表現されることもよくあります。
化粧品での用法、用量の表記は使用できるというだけで、必須ではありません。
ただ、用法用量が分かりづらい商品に関しては記載する必要があります。
基本的には記載されている方が望ましいです。
一般的な量や使い方と異なる場合、放置時間があるものなどは、記載義務があるので気をつけましょう。
H2健康食品での用法用量が使用はできないが、目安はあった方が良い
前述のとおり、健康食品では用法用量は使用不可です。 医薬品と誤認を与える表現となってしまうからですね。 ただ、過剰摂取などによる健康被害が起こる可能性があるので、目安として摂取量が必要とされることもあります。 用法、用量を明確に示すことはできませんが、消費者の安全のために、摂取量の目安を表示しておくと安心です。
健康食品での違反例
健康食品では、使用量、摂取時期、使用回数などを「明確」に記載することができません。 例えば
- 1日1~2回→1日の量、回数が明確な表現
- 1回2錠→1回の量が明確な表現
- 毎食後→服用時期が明確な表現
- オブラートに包んで→服用方法が明確な表現
これらの表現は全て医薬品と判断される恐れがあるため、避けた方が良い表現です。
回避方法(参考)
使用量や服用時期を明確に表現しないようにしましょう。
回避方法の例として
- 1日2~3個を目安に
- 栄養補給のためには、添付のサジで1日2杯程度を目安として
- 栄養補給の目安として、1日3個から6個ずつ
- 1日10粒を上限にお飲みください
- 牛乳などに溶かして
というような表現であればOKです。
まとめ
「用法、用量」を広告表現で使用するときは、薬機法と景表法をどちらの観点からも適切な表現であるか、確認することが必要です。 化粧品の場合は、用量、用法を明示する必要があるので、広告表現として使用ができます。 ただ、禁止されている表現もあるので、注意は必要です。 健康食品に関しては、薬機法の違反となってしまうため、広告表現としての用量、用法は使用ができません。 ですが、過剰に摂取してしまうことの健康被害が起きてしまう場合もあるので、表現を工夫して、目安を載せるようにしていきましょう。 言い換え表現の例を参考に、用法用量の表記をしてみてくださいね。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能