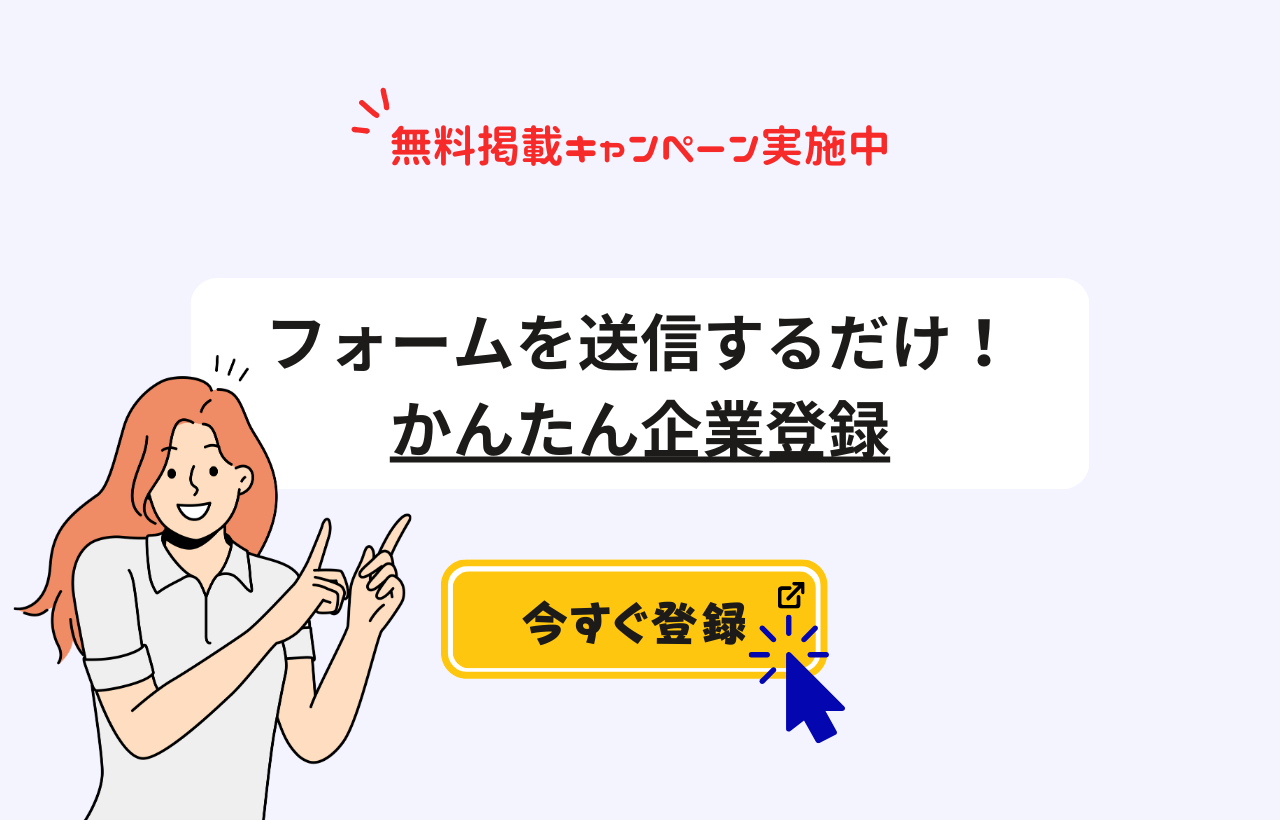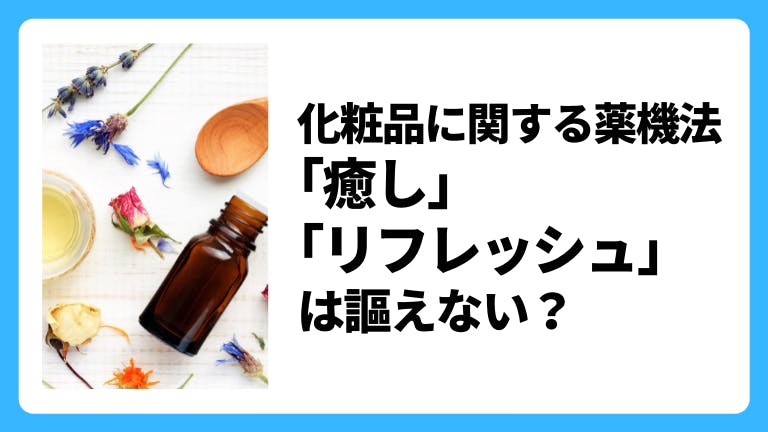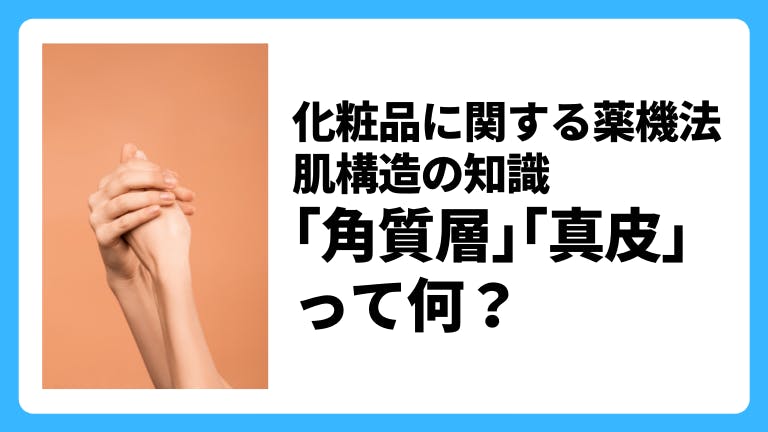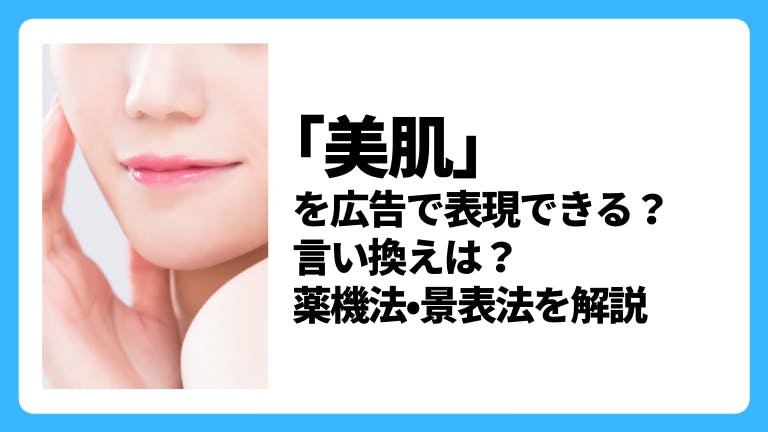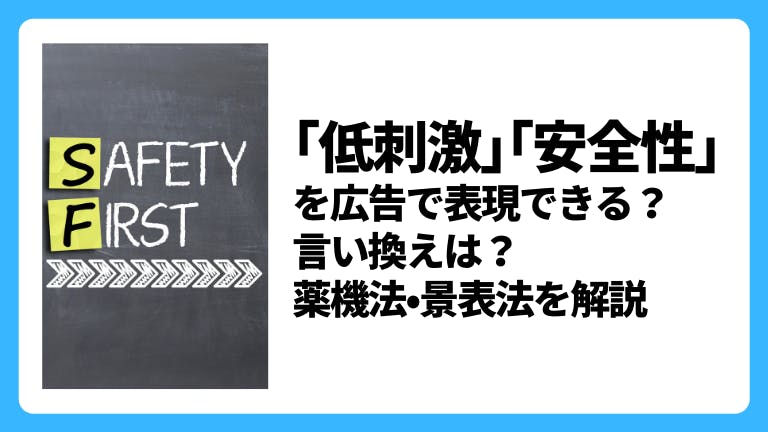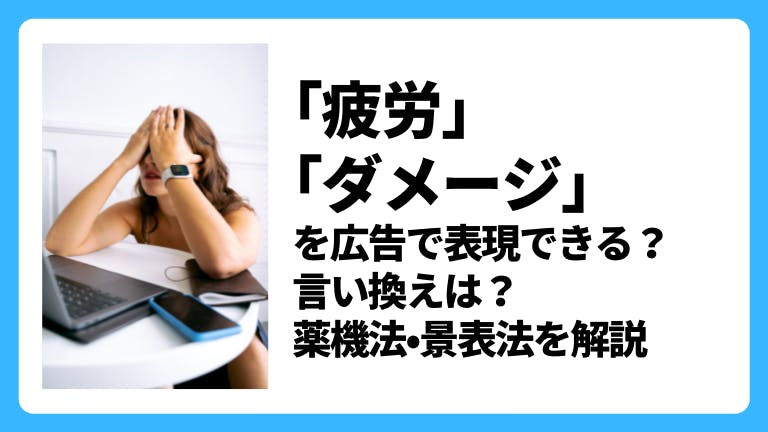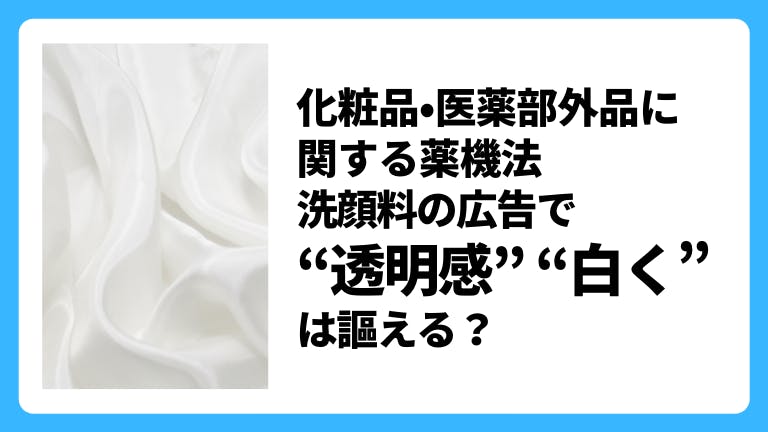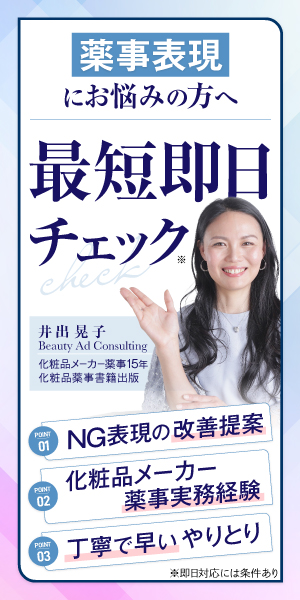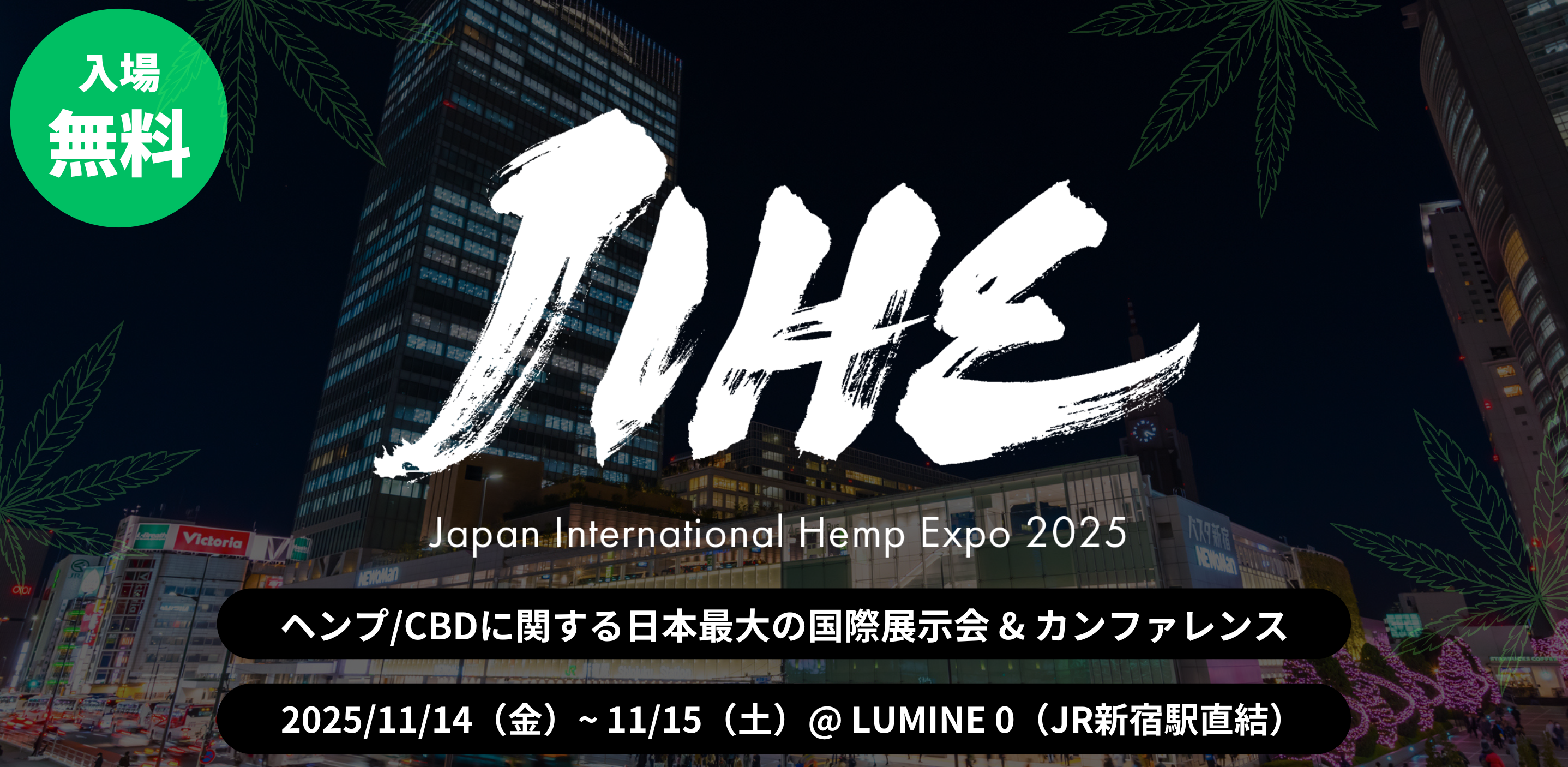
最終更新:2024/07/16
医療広告における薬機法 遠隔診療・オンライン診療とは?
コロナ禍に入り多くの企業がリモートワークを行なっています。
医療業界も例に漏れず、遠方で直接診療出来ない場合や緊急性の高い場合などにオンライン診療が活発的に行われるようになってきているのではないでしょうか。 今後コロナが落ち着いたとしても医療過疎地域に対してオンライン診療が必要になってくるなど、遠隔診療・オンライン診療の需要はより高まってくるかもしれません。
オンライン医療関係の事業を実施する際には医療法や薬機法による規制などが考えられます。 今回は今後より注目を集めるであろう、遠隔診療・オンライン診療について関係のある法律を交えながら説明していきます。
遠隔診療・オンライン診療とは
そもそも遠隔診療・オンライン診療とはどういった診療方法を指すのでしょうか。 遠隔診療もオンライン診療もどちらとも同じ意味として扱われますが、似たような単語に遠隔医療という単語があります。
遠隔診療・オンライン診療の定義
厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」にそれぞれの定義が記載されていたので紹介します。
・遠隔医療 情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為 ・オンライン診療 遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。
「遠隔医療」は情報通信機器を用いた医療行為全般の事で、「オンライン診療(遠隔診療)」は遠隔医療のうち診察・診断・処方などを行うことを言います。
遠隔診療・オンライン診療を行う手順
通常、オンライン診療を始めるには様々な作業を事前に行う必要があります。 厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」や「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」に記載されていたオンライン診療を始めるのに必要な事項についてまとめてみます。
- オンライン診療研修(e-ラーニング)
- 地方厚生局へオンライン診療の届け出
- オンライン診療の実施にかかる診療計画書の作成と患者の合意
2021年12月現在は「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて」により診療計画書の作成と患者の同意は不要になっています。
通常、オンライン診療を行うにあたり医師はオンライン診療研修(e-ラーニング)を受ける必要があります。
(1) 医師教育/患者教育 オンライン診療の実施に当たっては、医学的知識のみならず、情報通信機器の使用や情報セキュリティ等に関する知識が必要となる。このため、医師は、オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省が定める研修を受講することにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得しなければならない。
また、オンライン診療を行うにあたってオンライン診療料を算定することができ、施設基準も定められています。
オンライン診療料 1 オンライン診療料に関する施設基準 (1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有す る保険医療機関であること。 (2) オンライン診療料の算定を行う患者について、緊急時に概ね 30 分以内に当該保険医療機 関が対面による診察が可能な体制を有していること。(ただし、区分番号「B001」の 「5」小児科療養指導料、区分番号「B001」の「6」てんかん指導料又は区分番号「B 001」の「7」難病外来指導管理料の対象となる患者は除く。) (3) 当該保険医療機関において、1月当たりの区分番号「A001」再診料(注9による場合 は除く。)、区分番号「A002」外来診療料、区分番号「A003」オンライン診療料、 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び区分番号「C001-2」在宅患者訪 問診療料(Ⅱ)の算定回数に占める区分番号「A003」オンライン診療料の算定回数の割 合が1割以下であること。 2 届出に関する事項 オンライン診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式2の5を用いること。
出典:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
さらに、オンライン診療を行う際には診療計画書と患者の合意が必要です。
診療計画 ①考え方 医師は、患者の心身の状態について十分な医学的評価を行った上で、医療の安全性の担保及び質の確保・向上や、利便性の向上を図る観点から、オンライン診療を行うに当たって必要となる医師-患者間のルールについて、②ⅰに掲げられるような事項を含め、「診療計画」として、患者の合意を得ておくべきで ある。
本来であればオンライン診療は一度対面で診療を行った後にオンライン診療に切り替えることが可能となるのですが、2021年12月現在はコロナ禍により初診の段階からオンライン診療を行えるようになっています。
医療広告と医療法
医療情報ネットには医療機関の住所・アクセス方法・電話番号・診療科目・施設情報・ホームページなどが記載されています。 オンライン診療をする際は、患者自身が該当医療機関のホームページで実際にオンライン診療を行っているか確認しそれぞれの医療機関で決められている予約方法に従って予約を行います。
ここで問題になってくるのが医療機関のホームページの記載事項の規制です。 医療法を根拠として「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」で下記のような広告が禁止されています。
・内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告) ・他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告) ・誇大な広告(誇大広告) ・公序良俗に反する内容の広告 ・広告可能事項以外の広告(国が定める特定の文言 例:専門外来は禁止など) ・患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談 ・治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等 ・その他(品位を損ねる内容の広告・他法令又は他法令に関連する広告ガイドラインで禁止される内容の広告)
出典:医療広告ガイドライン
上記の内容に注意して医療機関のホームページの作成や医療機関に関する広告を行う必要があります。
オンライン診療アプリと薬機法
せっかくオンライン診療を行うのであればスマートウォッチやスマートフォンを利用して疾病の診断・治療・予防に役立てたいと多くの医療機関が思っているのではないでしょうか。 ですが、各医療機関によって患者自身が利用できるアプリや患者の情報を収集・処理するアプリなどを作成する場合は薬機法によって医療機器に該当する可能性があります。
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
となっており、病院などで使用されているCTやMRIからの情報を三次元画像表示するプログなども医療機器に該当します。
そのため、スマートウォッチやスマートフォンなどからの情報を収集し処理するシステムをアプリに組み込んだ場合も医療機器に該当しこれらのアプリを製造販売する場合には製造販売業の許可などを得る必要があります。また、医療機器も下記のように分類分けされています。
・この法律で「高度管理医療機器」とは、医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第七項において同じ。)において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 ・この法律で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 ・この法律で「一般医療機器」とは、高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 ・この法律で「特定保守管理医療機器」とは、医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
となっており、CTやMRIの三次元画像表示ソフトは管理医療機器に該当するため情報の収集と処理を行うオンライン診療アプリも管理医療機器に該当する可能性が高いです。
まとめ
本記事では遠隔診療・オンライン診療について関係のある法律を交えながら説明していきました。今後より医療のオンライン化が進みより便利なアプリやシステムが開発され、オンライン診療の規制緩和のように法律も日々変化していくと思います。 ですので、その変化に対応できるよう知識のアップデートが大切ではないでしょうか。そのような時に本記事が少しでも皆様のお役に立てれば、非常に嬉しいです。
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能