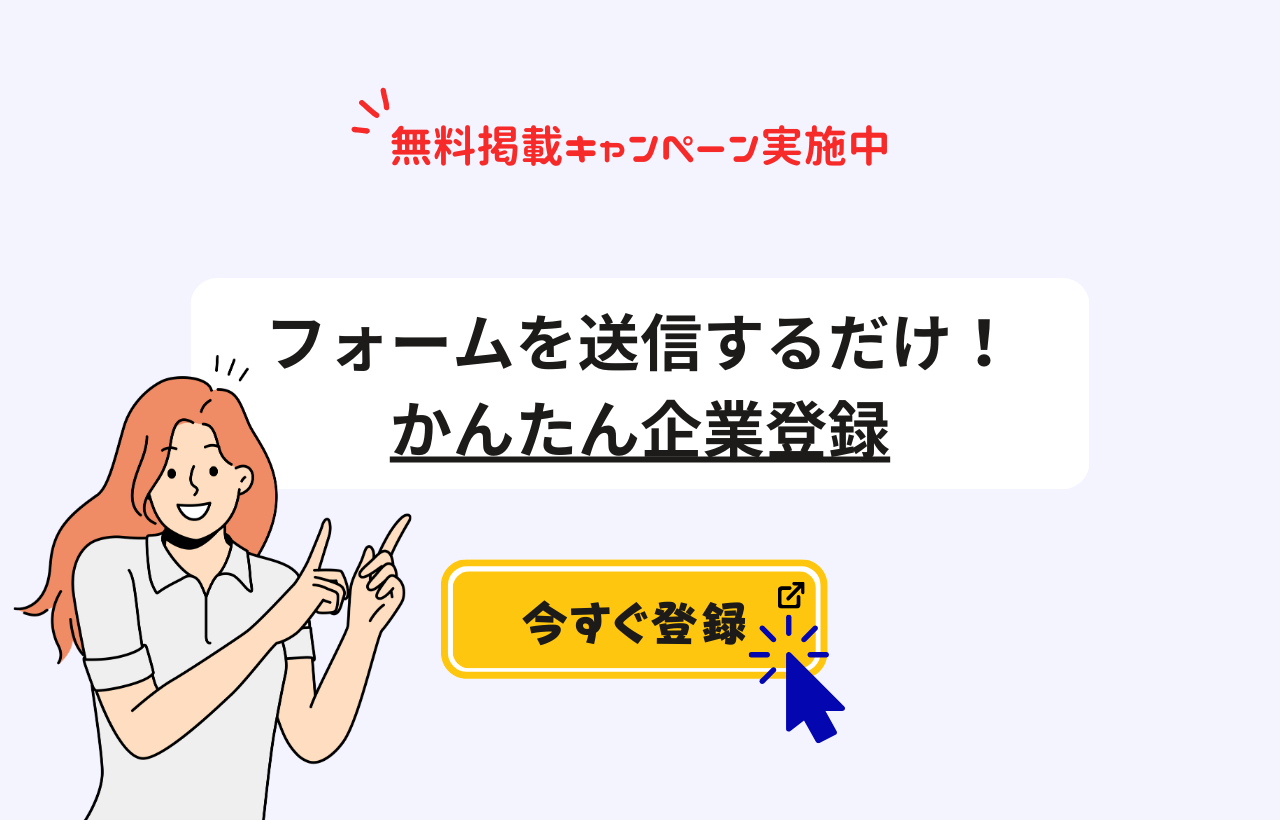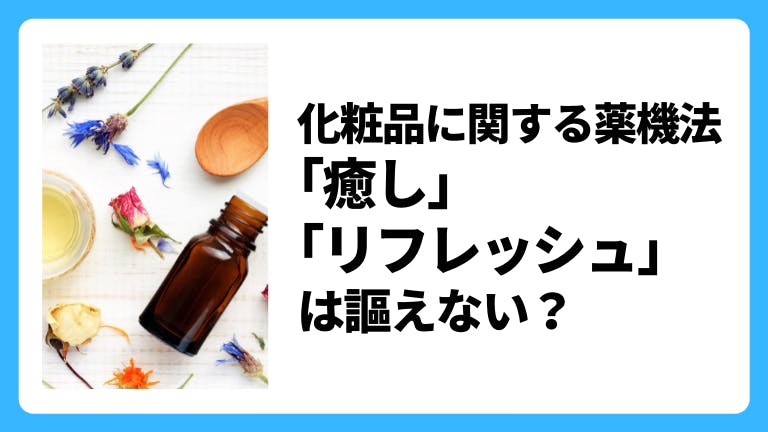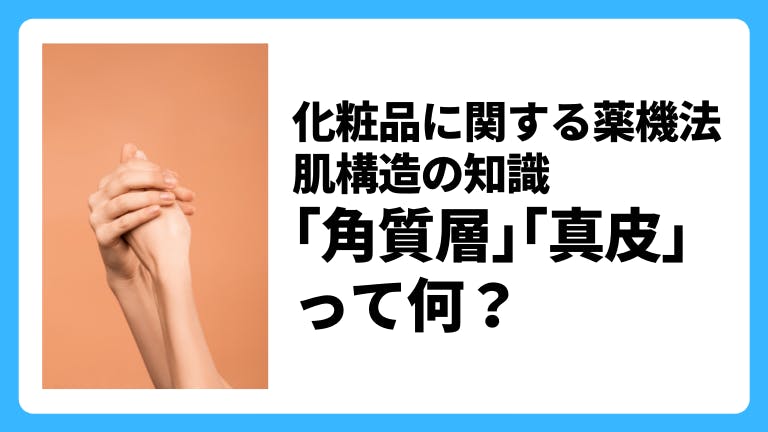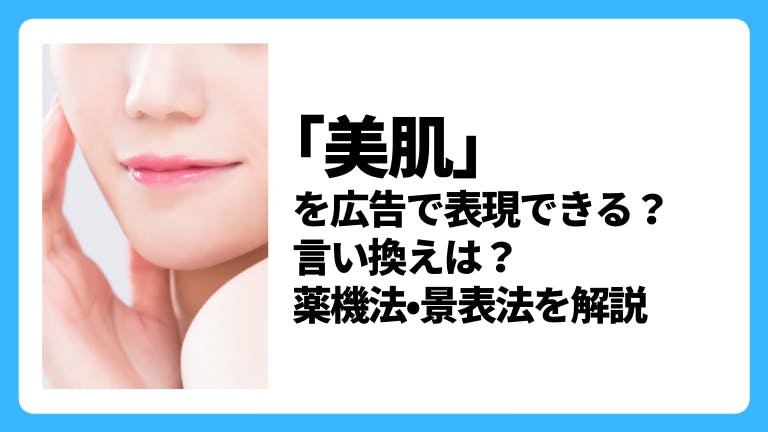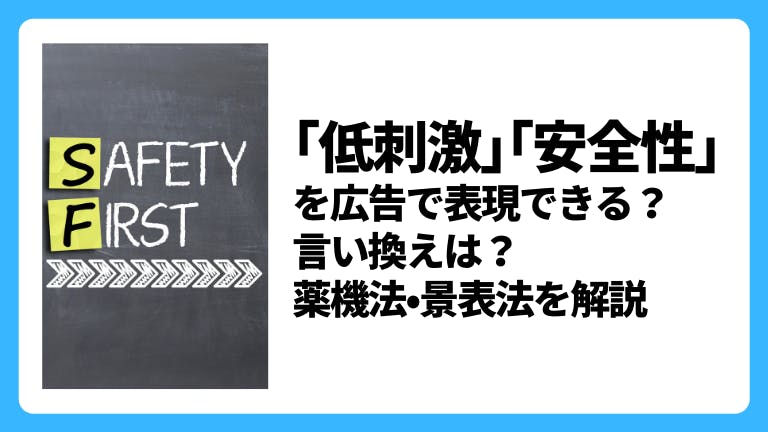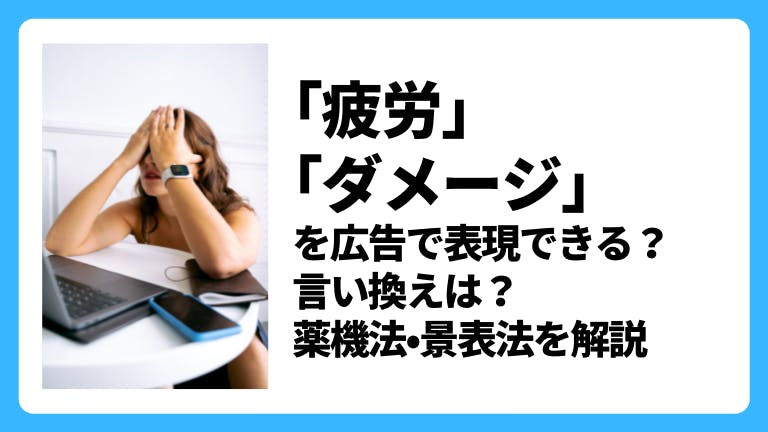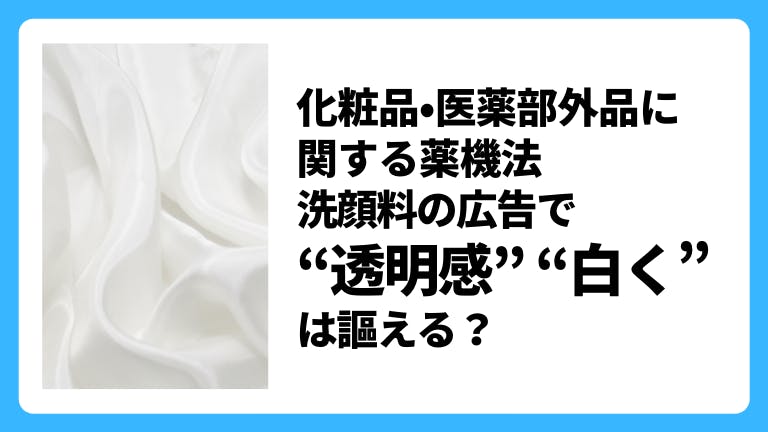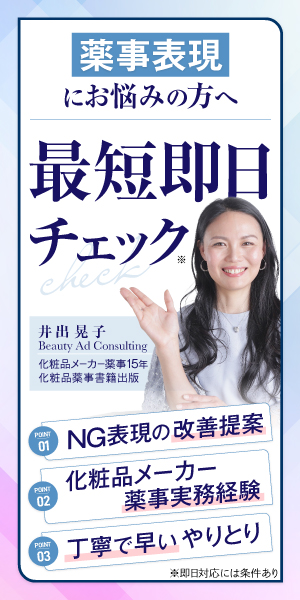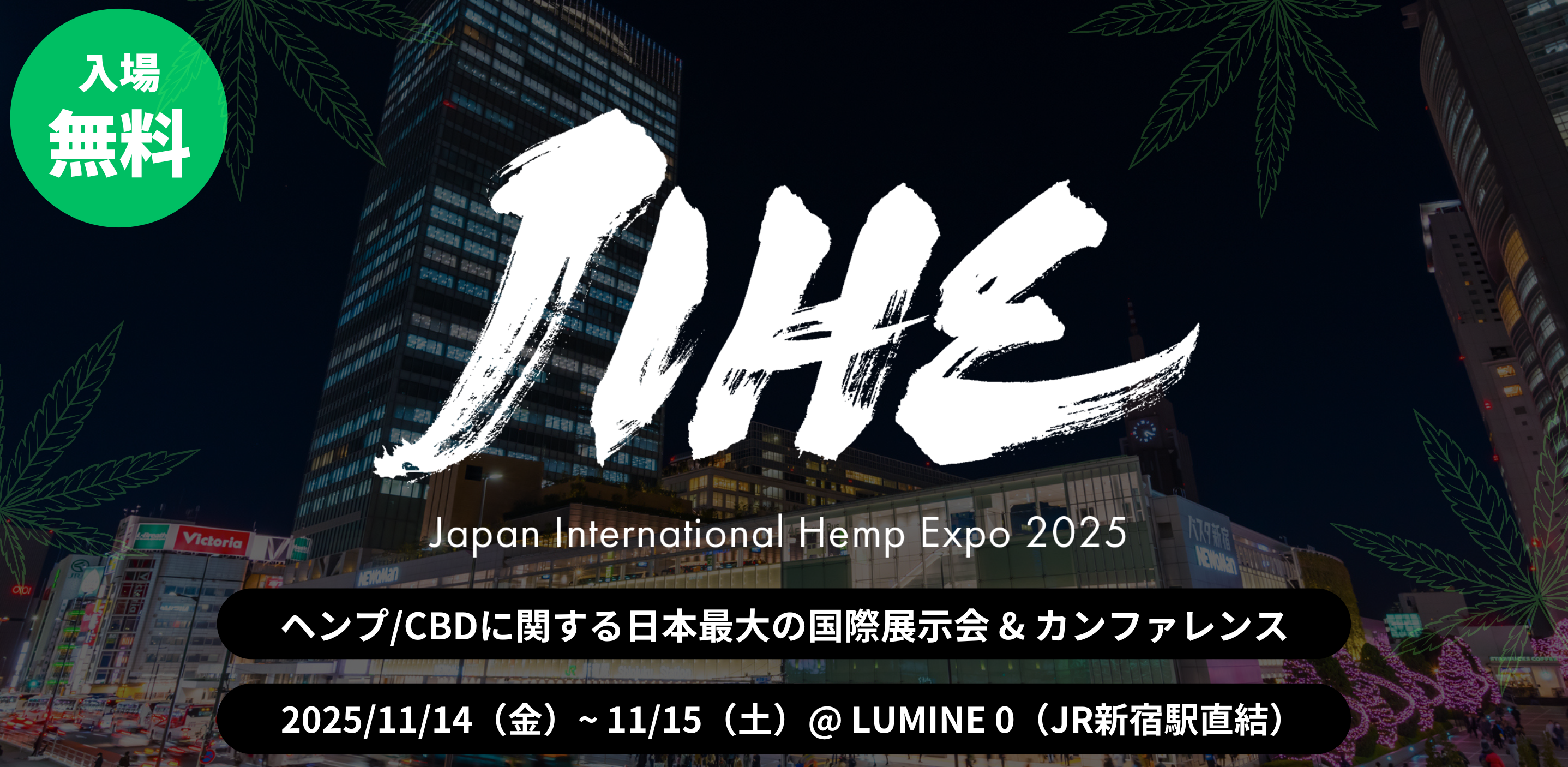
最終更新:2024/08/09
容器包装と色の関係性
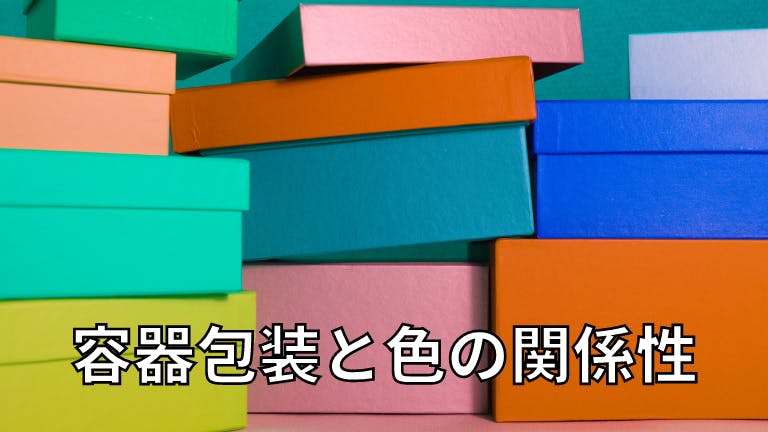
当記事では容器包装と色の関係性についてご説明します。 容器包装の色は消費者の感情や製品の実用性に影響を与えます。ぜひ当記事を通して色に対する理解を深めていただけたら嬉しいです。
容器包装と色の関係性
容器包装と色の間には、心理面でも実用面でも関係性があります。
心理的効果
容器包装の色は消費者の心理面に影響を与えます。 消費者は製品購買時にも使用時にも容器のデザインを見ることとなるため、容器のデザインが消費者の心理面に与える影響は多いです。特に容器の色はデザインの中でも大きな部分を占め、色によって商品やブランドのイメージが大きく変わります。
実用的効果
容器包装の色は容器の実用面にも影響を与えます。 化粧品や食品の中には、光に当たると中身が劣化してしまうものがあります。そのため、プラスチックやガラスの容器に着色をすることで、遮光性を持たせ、光から中身を守ることができます。
色が容器に与える心理的効果
色が容器に与える心理的効果は大きいです。 色による効果の違いと化粧品容器・食品容器それぞれでの使われ方をご紹介します。
色による心理面的効果の違い
暖色系
赤色・黄色・橙色・ピンク色などが該当します。 暖かくて元気な雰囲気を持ち、人の感情を高揚させる効果があるとされます。
- 赤色:特に人の感情を前向きにする効果が強いとされ、ビジネスの場では上昇志向や購買意欲を高める色ともされます。
- 黄色:明るく楽しい雰囲気を出す色とされ、自由さや開放的な雰囲気を表現することができます。
- 橙色:賑やかなイメージや家庭的なイメージをもたらす色とされ、容器ではファミリー向け製品などにも向きます。
- ピンク色:思いやりや可愛らしさを表現する色で、メイクアップ用品などでよく使われます。
寒色系
青色・緑色などが該当します。 寒さや冷たさを感じさせる雰囲気を持ち、人を冷静にさせリラックスさせる効果があるとされています。
- 青色:知性を表しストレスを軽減させる効果があるとされ、リラックス用品や入浴剤などでもよく使われます。
- 緑色:植物を連想させ、上品さや健康を感じさせる効果があるとされます。リラックス用品や健康食品などでもよく使われます。
無彩色系
白色や黒色が該当します。 無彩色系は単体で使うと強い印象となりがちですが、アクセントとして使っても全体が引き締まります。
- 白色:神聖さや希望を表します。清潔感も感じさせる色のため、食品や洗剤などで使われることも多いです。
- 黒色:強さを感じさせます。権威性や高級感も出せるため、高級な食品や化粧品で使われることも多いです。
化粧品容器における色の心理的効果
化粧品容器のデザインは、製品の購買の有無や満足度に大きな影響を与えています。 色は下記のような切り口で決められていることがあります。
ブランドイメージ
ブランドイメージに基づいて、容器に使うメインの色が決められているケースが多くあります。 例えば、”知性を感じさせるブランドは青・元気さや活発さを表現しているブランドは黄色・女性らしさや可愛らしさを売りにしているブランドはピンク”といった決められ方がされています。 ブランドのイメージを規定し認知してもらう上で、色を統一することは大きな効果を持ちます。ブランドイメージを決定する際には色も決めておくと良いでしょう。
季節
季節限定で売り出す製品は、季節のイメージに基づいて色が決められていることもあります。 例えば、”春は桜を連想させるピンク・夏は海を連想させる青・秋は紅葉を連想させる黄や茶・冬は雪を連想させる白”といった決め方がされています。 特に日本では四季に沿った製品が数多く発売され人気を集めていますので、他社の商品も見ながら色を決めていくと良いでしょう。
製品の種類
製品の種類によって色が決まっていることもあります。 例えば”清潔感が求められるシャンプーやボディーソープなどの製品には白、可愛らしさが求められるメイクアップ用品にはピンク、リラックス用品には緑”といった決め方がされています。 消費者が保管する場所によっても好まれる色が変わるため、使用場面を想定しながら消費者が喜ぶ色を考えると良いでしょう。
食品容器における色の心理的効果
食品容器も色が消費者の感情に影響を与えます。 例えば下記のような切り口で色が決まっています。
食品の味との相性
食品の味に合わせて容器の色味を決めることもあります。 例えばすっきりとした味の刺身や素麺などの容器には、白色や水色が使われることが多いです。一方で刺激的な味付けが特徴の中華やカレーなどの容器には、赤色やオレンジ色が使われることが多いです。 容器の色から消費者が味をイメージできるかを考えて色を決めると良いでしょう。
食事の場面
食事の場面を想定して色味が決められることもあります。 例えばお祝いの席で食べることの多い大人数向けの寿司の容器には、赤色や黒色が使われることが多いです。また容器のまま食卓に出すことも想定されるケータリング用品には、容器にレタスに似せた緑色の印刷がされていることもあります。 特に容器が食卓上で使われる製品については、食卓への調和も意識して色を決めると良いでしょう。
店頭で目立つか
特に赤い色は店頭で目立ちやすいとされ、よく使用されいます。 数多く商品が並ぶ店頭で目立つために、調味料やレトルト食品などで赤い色が使われるケースがよくあります。 赤色は食欲も掻き立てる色とされていますので、アクセントでも積極的に取り入れていくと良いでしょう。
色が容器に与える遮光性
透明なガラスやプラスチックの容器には、色を着色することで遮光性を持たせることができます。 ただし色をつけても100%完全には遮光できないため、遮光容器を使う際には保管もなるべく光が当たらない場所とするとより安全です。
色による遮光性の違い
遮光容器としては、茶色・緑色・青色が主なものです。 光は290-400nm程度が紫外線、400-800nm程度が可視光線、800nm程度以上が赤外線とされています。
- 茶色 450nm以下のほとんどの光をカットしており、遮光率は極めて高いです。青色や緑色と比べても遮光性が高いため、アロマオイルなどの光に弱い中身には茶色を選ぶと安全です。
- 青色 300nm程度までの光をカットしています。一方で紫外線に対しての遮光性が悪く、ほとんど遮光できていません。
- 緑色 360nm程度までの光をカットしており、紫外線に対しは茶色と同程度の遮光力を持ちます。 一方、可視光線に対する遮光力は弱く、アロマオイルなどでは茶色を使用した方がより安全です。
3色の間で遮光力差があるので、デザインとのバランスで最適な容器を選ぶと良いでしょう。
化粧品容器における遮光性
化粧品は消費者が身につけて使うことになるため、消費者が使う時まで品質が保たれている必要があります。 特にアロマオイルは光によって劣化しやすいため、遮光容器が使われます。また他にも光に対して劣化しやすい成分が配合されている美容液や化粧水などで遮光容器が使われることがあります。
食品容器における遮光性
食品は消費者が口にするものとなるため、品質の管理には特に注意が必要です。 ビタミン剤は光に対して弱く、特にビタミンCが光に対して劣化しやすいとされています。サプリや栄養ドリンクなどでビタミンを含むものについては遮光容器を使うとより安全でしょう。
まとめ
当記事では色と容器包装の関係性についてご説明しました。 色は消費者の感情に訴えるだけでなく、中身を保護する役割もあります。 ぜひ当記事を参考に、製品にぴったりの色を考えていただけたら嬉しいです。
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能