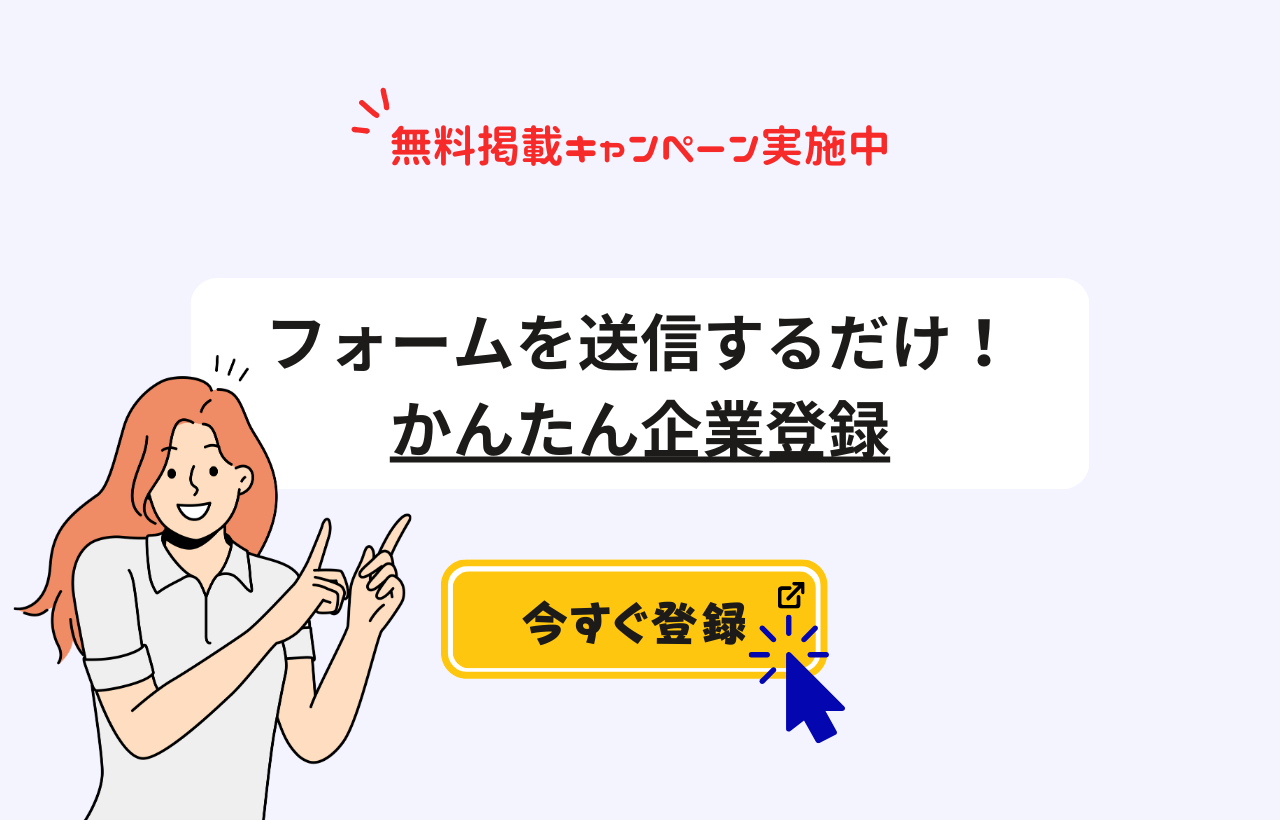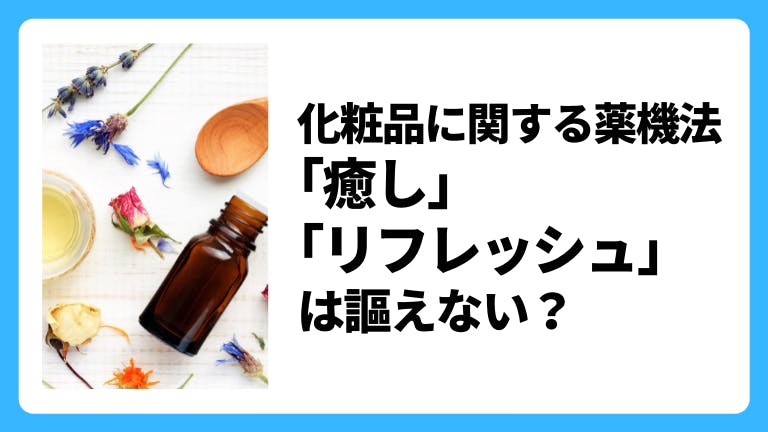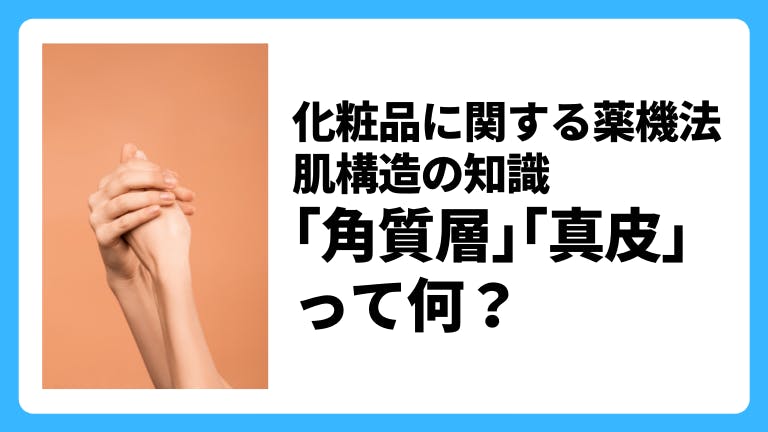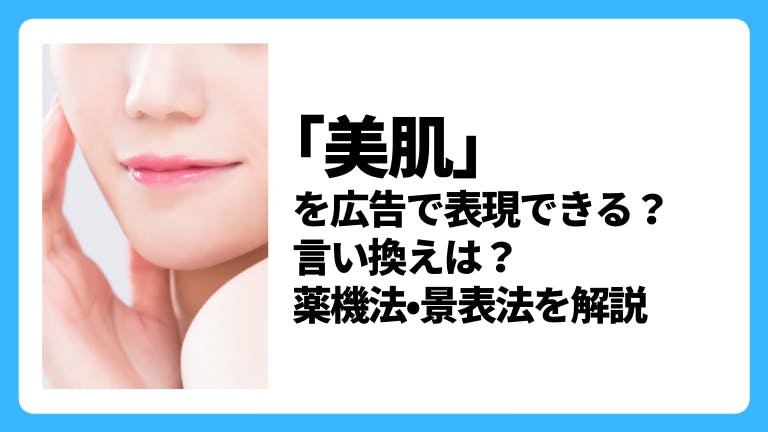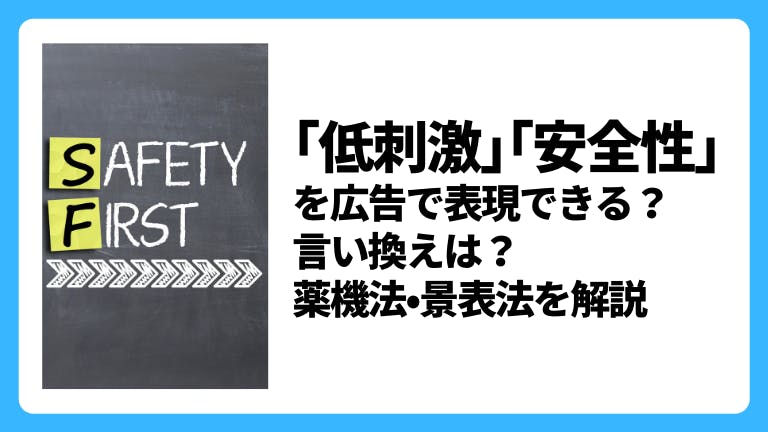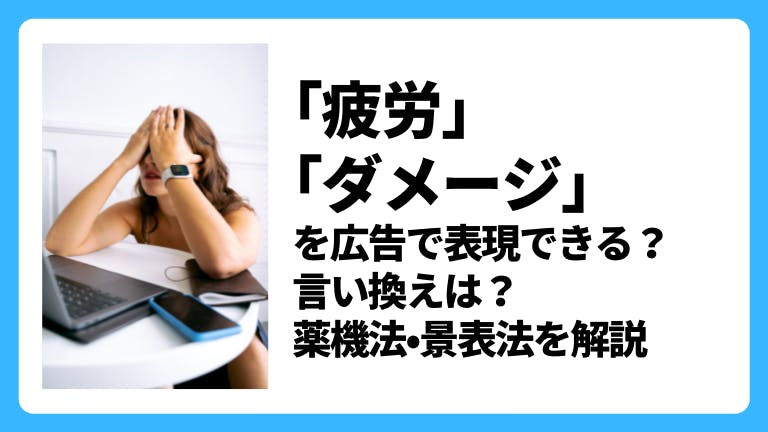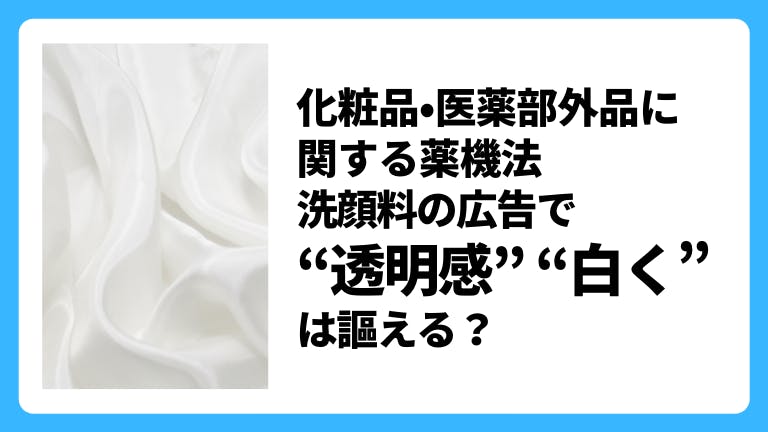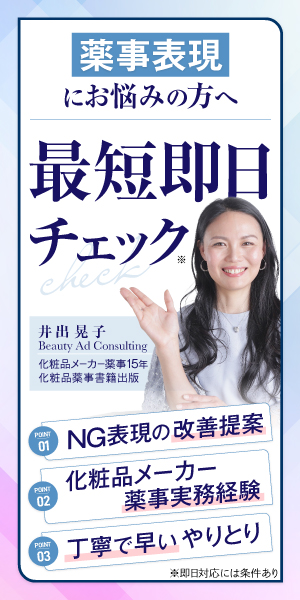最終更新:2024/08/07
ラベルの素材 本物の木・木目調シールについて
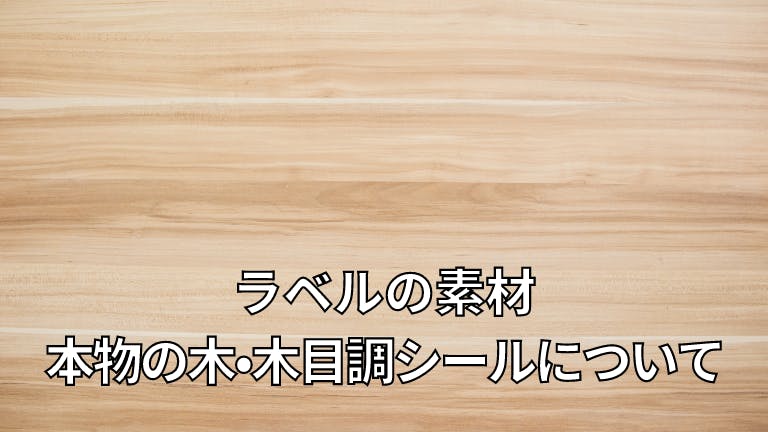
自信のある商品をアピールするとき、一番に考えるのはラベルの差別化ではないでしょうか。他とは違う商品だからこそ、ラベルも他にはない唯一無二のものを使いたいはずです。
自然の助けがなければできない商品なら、ラベルも自然を生かしたものを使いたいでしょう。そんなときに、木のラベルは最適です。現在は本物の木をラベルに加工することができます。今回はラベルの素材としての木について、その特徴やメリット、デメリットについて解説します。
また、本物の木を使うだけでなく、紙に木目を印刷して木のようなラベルを作る方法についても紹介します。木のラベルがグッと身近に感じられるようになると思います。
木製ラベルのメリット・デメリット
自然を生かしたラベルを作りたいとき、木目調のシールではなく本物の木でラベルが作れたら、商品のグレードまで高まるように思われます。木製ラベルならではの手触りと香りが、商品を手に取る人に強く訴えかけてくれるはずです。
木製ラベルの用途
木製ラベルは、自然の助けを借りなければ作れない製品に最適です。具体的には日本酒、焼酎、ワインなどのお酒、醤油や味噌などの調味料です。特に樽醸造、貯蔵をした日本酒なら、木製ラベルでその特徴をアピールすることができるでしょう。また土産物のワンポイントシールなどにもよく似合います。
オンリーワンのラベルが作れる
現在では、実際に桜や樺の木を使ってラベルを作ることができます。本物の木の落ち着いた色合いと模様、そしてまったく同じものは作れないという木の性質のため、ラベルで特別感を出すことができます。 1枚ずつ色と模様が違うことは、デメリットにもつながります。木にはどうしても以下のような特有の欠陥ができてしまうからです。しかし、これが木をラベルに使う面白さでもあります。
- ピンホール:小さな虫食いの穴
- ピンノット:成長する過程でできる節
- ミネラルストリーク:木の中に堆積した成分によってできる筋
また、ある程度の枚数を作っていると、色味が違うものもできてしまいますが、木製のラベルを使いたいなら、これらは木の個性だと思って受け入れる必要があります。
木製ラベルの印刷方法
木に印刷をするのにもっとも適しているのはUV印刷です。これは印刷後に紫外線を当てることで、急速に硬化する特殊なインクを使った方法です。 インクを乾かす時間がかからないため、納期が短くて済む、摩擦や直射日光に強いなどのメリットがある印刷方法です。また、印刷の精度が高いのも特徴のため、より精密な木製ラベルを作ることができるでしょう。 しかし、どんな木でも良いわけではなく、UV印刷に適した木材というのがあります。
UV印刷に適した木材とは
表面が塗装されている 表面に塗装がされていることで、インクののりが良くなります。これは発色の良さ、インクの定着にもつながります。逆に塗装されていない木材に印刷をすると、思った通りの色にならない、といった事態が考えられますが、木の質感を生かしたいとき(つまり印刷する色が木肌の色の影響を受けても構わないとき)は、あえて塗装をしないこともあります。
十分に乾燥されている 木材の乾燥が不十分だと、木材のひび割れや反り返りが起こる恐れがあります。UVインクの定着が悪くなりますし、印刷面が割れてしまうことも考えられますので、木材は十分に乾燥することが大切です。十分に乾燥してラベルを製作した場合でも、屋外で使用することで湿気を吸い込み、ひび割れや反り返りが起こることもあります。
薄い 当たり前のことですが、厚さ5mm以上のような、あまりに厚い木材は印刷機を通りません。また、厚すぎるラベルはボトルに貼ることもできませんし、手に取る人にも違和を感じさせるでしょう。ラベルとして使用するなら、薄いことも大切です。
紙に木目印刷をするメリット
木製ラベルには本物ならではの良さがありますが、実は紙に木目を印刷してラベルにすることにも大きなメリットがあります。それは木をラベルにするときに、注意しなくてはならないことを一切気にしなくても良いということです。 ピンホールやピンノットなどの木に特有の欠陥も、乾燥しているか、印刷機に通るかなどの問題点も紙を使えば問題になりません。それに紙に印刷するなら、自分が気に入った木目の模様を何枚でも再現することができます。
木目印刷をするには
世の中にはたくさんの木目の素材画像を選ぶことができます。ただ木目というだけでなく、スギ、マツ、ヒノキなど木の種類で選ぶことができますし、新しい木、古い木、または柾目(まさめ:年輪が並行に並んでいる)か板目(年輪が山型になって並んでいる)のような選び方もできます。 このような木の画像をダウンロード、紙に印刷することで手軽に木目印刷をすることができます。また、印刷する紙の種類によって質感が違うため、どんな紙を選ぶかで仕上がりが違ったものになります。
紙の選び方で変わる仕上がり
表面にコート剤を塗って作られているコート紙はツルツルとしてツヤがありますから、仕上がりは明るくなります。反対に上質紙は表面に何の加工もしていないため、ツヤがありません。コート紙に比べると、インクがよく染み込むため、印刷の色味が落ち着いた印象に仕上がります。同じ木目を印刷しても、印象はかなり違うものになります。
ファンシーペーパーを使ってみる
ツヤのあるなしだけでなく、紙に凹凸など立体感があると木目印刷が違った表情を見せるようになります。ファンシーペーパーという印刷用の特殊紙は独特の質感を備え、豊富な色が揃っていますが、これを使って木目印刷をすることで、ただの紙のラベルにさらに強い存在感を出すことができます。 ファンシーぺーパーにもさまざまな種類がありますが、異素材の繊維などを漉き込んだものは手触り感があるため、商品を手に取る人に強い印象を残すことができます。特殊紙の種類は多いため、自分の理想とするラベルを仕上げるためには、紙についての知識が豊富な業者との綿密な打ち合わせをすると良いでしょう。
エンボス加工でさらにリアルな仕上がり
インクを使わずに、紙に文字や図案を浮き彫りにする加工のことをエンボス加工と言います。紙の表面に陰影ができて見た目が良くなるのはもちろんですが、手触りが良くなる効果も知られています。エンボスで紙に凹凸がつくため、滑り止めになるとも考えられます。
このエンボス加工には木目調というものがあります。木目を印刷してある場合、その図案とあまりにもかけ離れるとおかしなものですが、そうでなければ視覚と触覚の両方に訴えることができますから、エンボス加工を施す価値は十分にあるのではないでしょうか。
エンボス加工だけでも、適切な色を選べば、木のような仕上がりが期待できます。
まとめ
今回は木のラベルについて解説しました。木のラベルには人の目を引きつけるだけではなく、心を安らがせる魅力があります。本物の木を使うのも良いですが、木目印刷をして作った紙のラベルにもメリットがたくさんあります。
1つずつ違うラベルができる本物の木と、自分の気に入った木目をいくらでも再現できる紙のラベル、用途と状況に合わせて選ぶと良いでしょう。ラベルの枚数は少なくても良いから、特別感を大切にしたいなら、本物の木、安定した同じ模様のラベルが枚数多く必要なら、木目印刷をした紙のラベルというように使い分けをしてください。
木のラベルは見るだけで自然を感じさせることができる貴重な存在です。上手に使って、商品アピールに役立ててください。
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能