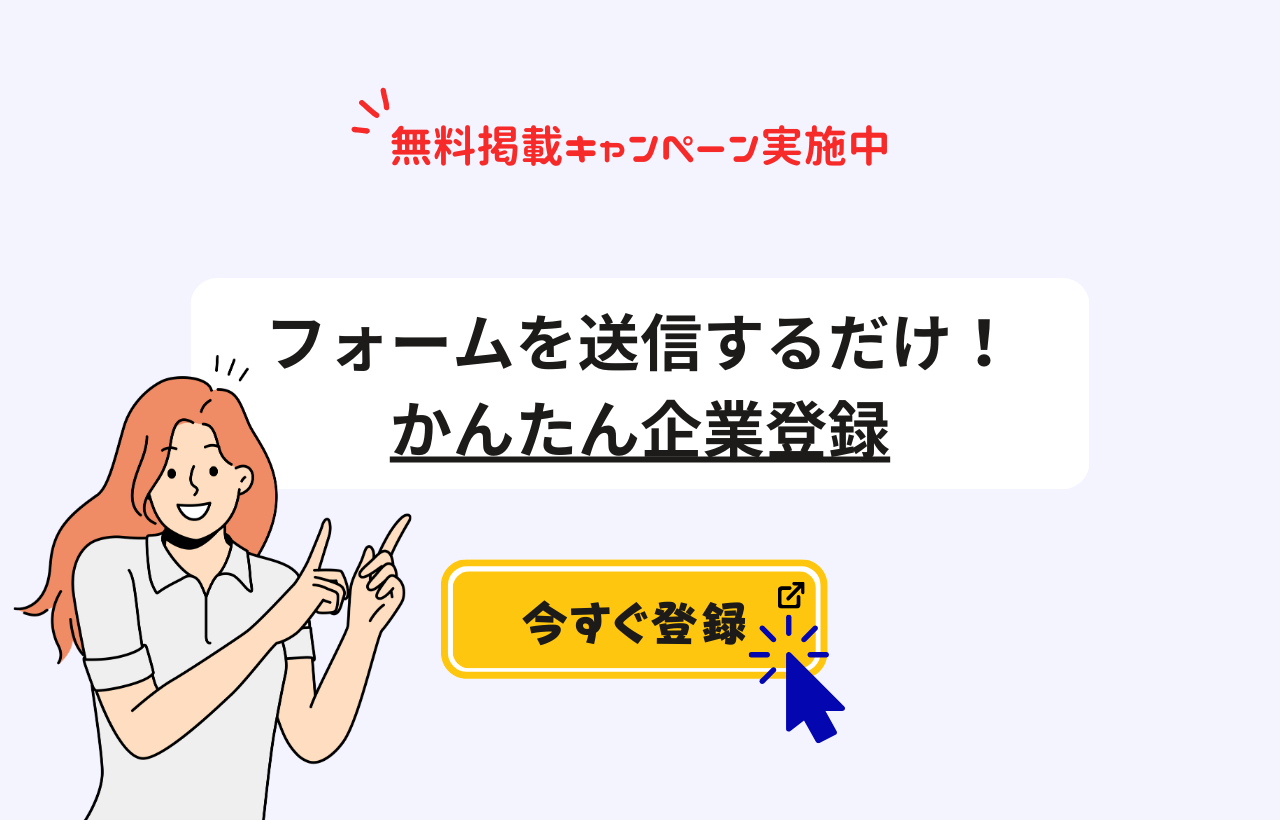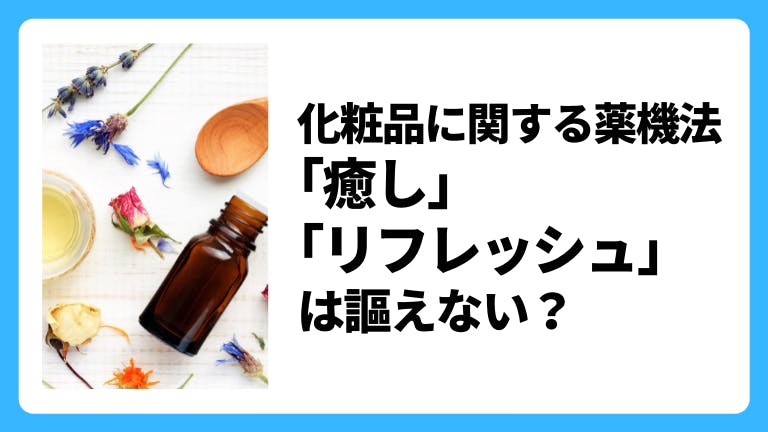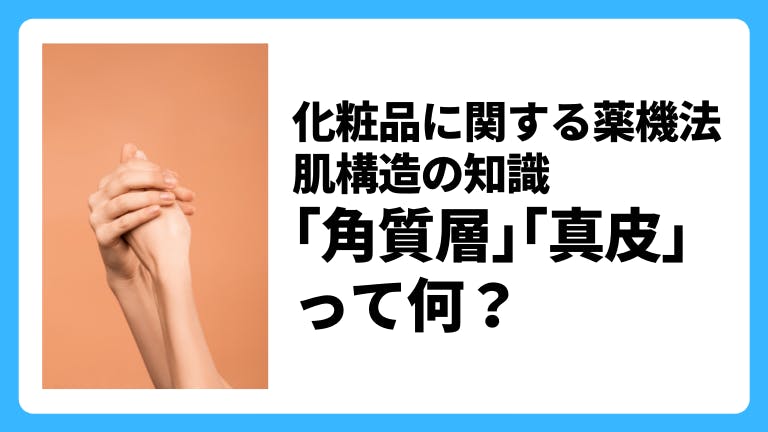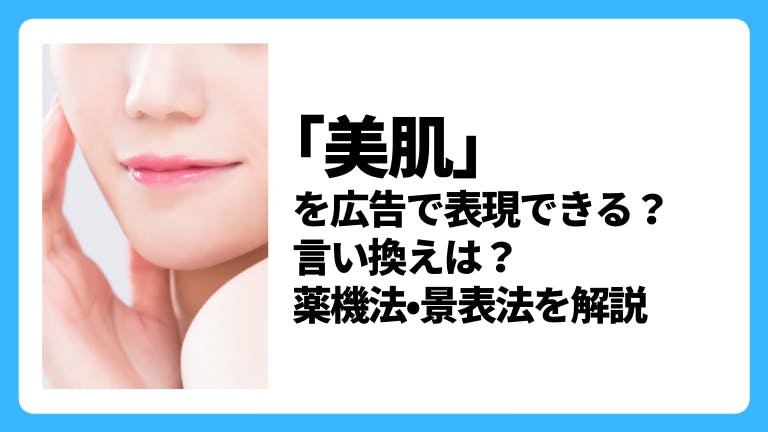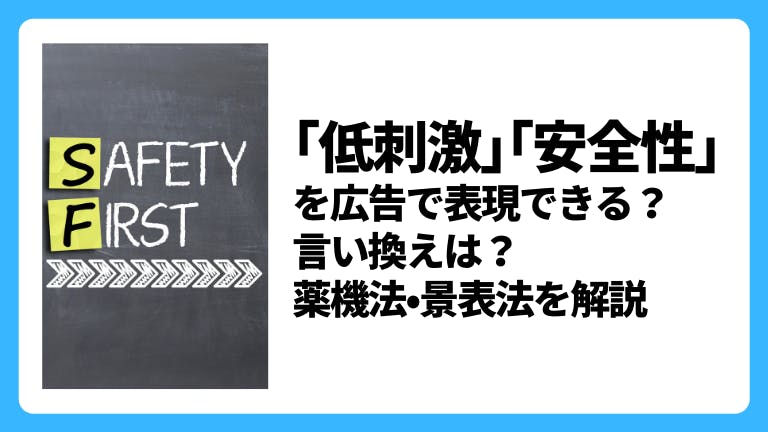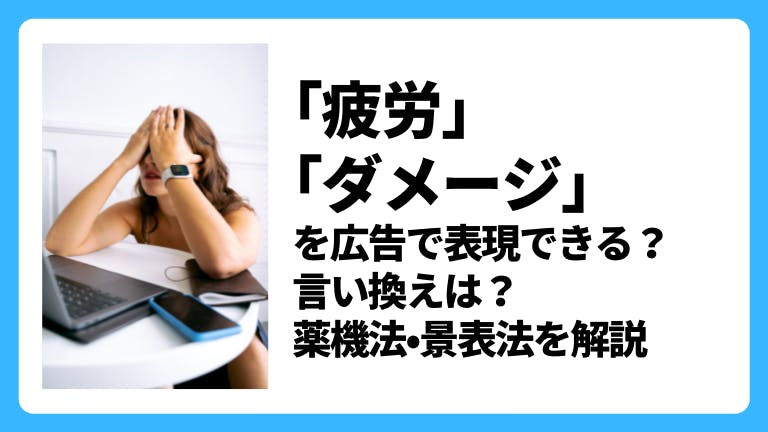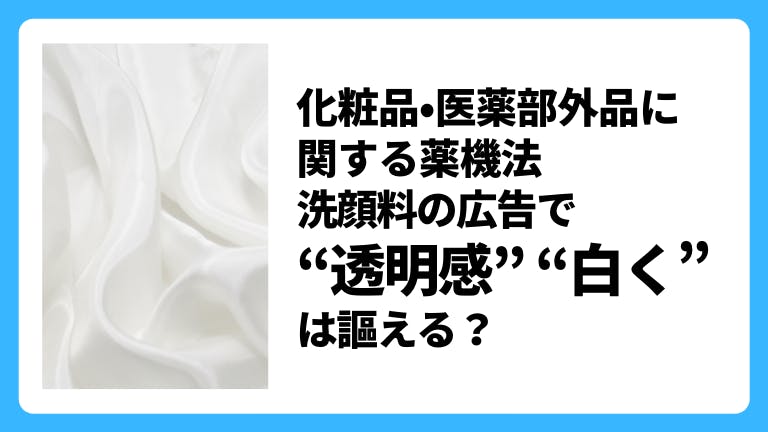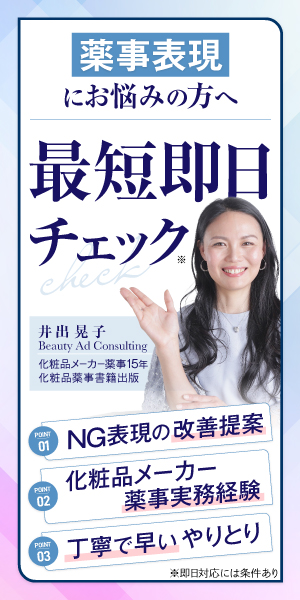最終更新:2024/08/07
ラベル・シールの気になる見積もり・相場

ラベルやシールを作りたいとき、まず予算のことが気になります。自分で用紙を購入して作るのか、業者に頼むのかでも、予算は違ってくるでしょう。なるべく低予算で高品質のラベル・シールを作るためには何に気をつけたら良いのでしょうか。
今回はラベル・シールを作るときの見積もり相場について解説します。 初めてラベル・シールを作ろうと言う人は、ぜひ今回の記事を参考にしてください。
見積もりのために、ラベル・シールの構造を知る
ラベル・シールは次のような構造になっています。
- 本体:プラスチックフィルムや紙が使われる。プラスチックフィルムの方が価格が高い
- 台紙:本体の粘着部分を貼り合わせるための紙
- 糊 :接着部分につけられている糊にも種類があるため、用途によって選ぶ必要がある
このすべてに価格が発生しますが、それだけではありません。印刷が終わった後に保護するための加工をする場合があれば、それにもコストがかかります。 ラベルやシールは印刷が終わった後は長い台紙に貼り付けられた状態で、そのままでは貼り付け作業に移ることができません。それを作業がしやすいようにロール状に巻いたり、小分けにすることが必要ですが、それにもコストが発生します。 そしてラベルやシールを作るとき、ただ安いものを使えば良いわけではありません。材質などは、使う用途によって選ばなければ、せっかく印刷したラベルやシールそのものが無駄になってしまうかもしれません。
相場がわかりやすいラベル:シールの材質
まず本体の材質を選ぶわけですが、プラスチックフィルムのPET素材の価格が一番高く、次がポリプロピレン素材が使われている合成紙・ユポです。 その次に価格が高くなるのが、紙の表面にコート剤が塗られていて、印刷がしやすいと言われているキャストコート紙、アート紙です。紙の表面になにも塗られていない(非塗工紙)の上質紙は、もっとも手頃な価格になります。
ラベル・シールの価格を抑えたいなら、上質紙を使えば良いと思われるかもしれませんが、もし水場で使うものに貼りたい場合、上質紙でラベル・シールを作ったとしても、すぐに水分で劣化してしまい、役目を果たすことができないかもしれません。それではラベル・シールを作ること自体が無駄になってしまいます。 逆に水分の心配のない屋内でしか使わないものなら、わざわざ高額なPETやユポを使う必要はないわけです。このように、ラベル・シールの材質は用途によって選ぶ必要があります。
色が増えると相場が上がる:印刷
印刷に使う色が増えれば増えるほど、コストが上昇します。通常のカラー印刷では4色のインクを使いますが、企業のロゴなど、細かな色指定がある場合は、5色、6色と色が増えるかもしれません。 企業のロゴなどは正確に印刷しないと、イメージを損ねてしまう場合があるため、コストを惜しまない方が良いでしょう。
また、蛍光色や金や銀などのメタリックカラーを使いたい場合も、色を増やす必要があります。見る人の心に訴えるラベル・シールを作るためには、あえて印刷に使う色を増やす必要もあるのです。
台紙を選ぶ
台紙はセパレーターとも呼ばれ、接着面の裏につけられるため、ラベル・シールを作るときには欠かせない存在です。台紙にも、いくつかの種類があり、手で貼るのか機械で貼るのかによって選ぶべきものが違ってきます。
- 黄色のクラフトセパレーター:厚みがあって印刷しやすいため、機械貼り以外ではほとんどこれが使われている
- 水色のクラフトセパレーター:黄色よりも薄く、機械貼りのときに枚数を数えるのに使われる
- グラシン紙のセパレーター :水色よりも更に薄く、機械貼りに使われる
また、台紙に余白がありすぎるのは、コストが増える原因になります。信頼できる業者なら、台紙に無駄ができないように印刷設計をしてくれますから、コストを抑えるためには業者選びが重要になります。
ラベル・シールの加工を選ぶ
印刷した後にラミネート加工などが必要な場合もあります。これには印刷の色落ちを防ぐ、色褪せを防ぐなどの目的の他に、ラベル・シールに光沢感やマット感を加えるという目的もあります。他にも豪華な仕上がりにしたいときの箔押し加工、エンボス加工など、さまざまな加工がありますから、ラベル・シールの仕上がりと用途に合わせて選ぶ必要があります。
これらの加工もすべてコストがかかりますが、仕上がりの見た目だけのために行う加工と違い、表面を保護するための加工は必要不可欠なことが多いです。もしどうしても加工をしなくてはならない場合は、まずラミネート加工(PP貼り)を優先的に考えてみると良いでしょう。
このようにラベル・シールの素材や加工を決定していくと、製作にかかるコストが算出されますが、コストを決めるのには、もう1つ重要な要素があります。それが注文数です。
コストを抑えるために、注文数に注意する
ラベル・シールを作るときには、ある程度の量の紙が必要になります。たとえ必要なラベル・シールが1000枚だとしても、実は用意された紙で、もっと多くの枚数が印刷できるかもしれません。その印刷できる数の上限を経済ロットと呼んでいます。
その上限数が1万枚の場合、1000枚注文するのも1万枚注文するのも、値段が同じという事態になります。もし保管する場所があり、そのラベル・シールを長い間使う予定があるなら、1万枚注文した方が1枚当りの価格は安くなるわけです。 しかし、いくら1枚当りの価格が安くなっても、使う予定のないラベル・シールを置いておくのでは、場所代が無駄になることもあります。その点をよく考えて、ラベル・シールの注文数を決めるのが、コストを安くすることにつながります。
自分でラベル・シールを作ると安く済むのか?
印刷したい数にもよりますが、自分で紙とインクを購入して、家庭用のプリンターでラベル・シールを作るのは、思いの外コストがかかります。
自分で購入するのでは、紙をそれほど安く調達できないし(業者はまとめ買いをしますから、私たちが買うのとは比べることができません)、家庭用プリンターのインクは、もともと価格が高いものです。
そして、印刷に付きっきりになる人の人件費や時間を考えると、何もかもおまかせできる業者に頼んだ方が良い場合も多いのです。凝った加工もできますから、仕上がりも満足できるはずです。そして、信頼できる業者なら、ラベル・シールの用途に応じて適正な素材と加工を選ぶ手助けをしてくれるでしょう。
信頼できる業者を探すための見積もり
もし、業者から提示された価格に納得がいかない場合は、いくつかの業者から見積をとって検討してください。しかし先程も書いた通り、ラベル・シールの価格は安ければ良いというわけではありません。用途に応じた適切な素材と加工を選べば、コストがかかる場合があります。
水場で使うラベル・シールなら、安い上質紙で作っても、ラベル・シールが劣化して作り直しにならないとも限りません。そんなことになれば、結局作り直しの金額が上乗せされて、高く付くことになるのです。それを防ぐには、なぜこの金額になるのかを丁寧に説明できる、信頼できる業者を見つけることが一番です。そんな業者を探すためにも、複数の業者から見積を取り、説明を聞いてみましょう。
まとめ
今回はラベル・シールを作るときの料金について解説しました。どんな素材や加工を使うと価格が上昇するのかを説明しましたので、ぜひ、実際にラベル・シールを作るときの参考にしてください。
用途を無視した素材選びは、どんなにそのときは節約したと思っても、結局は無駄になってしまうことがあります。金額の大小だけに囚われずに、自分がなぜラベル・シールを作るのかを考えて、必要な素材、加工を選ぶようにしてください。
そのためにも、信頼できる業者との出会いが大切です。素材や加工の必要性をきちんと説明してくれる業者と出会うためにもまずは見積もりを取ることから始めてみてください。
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能