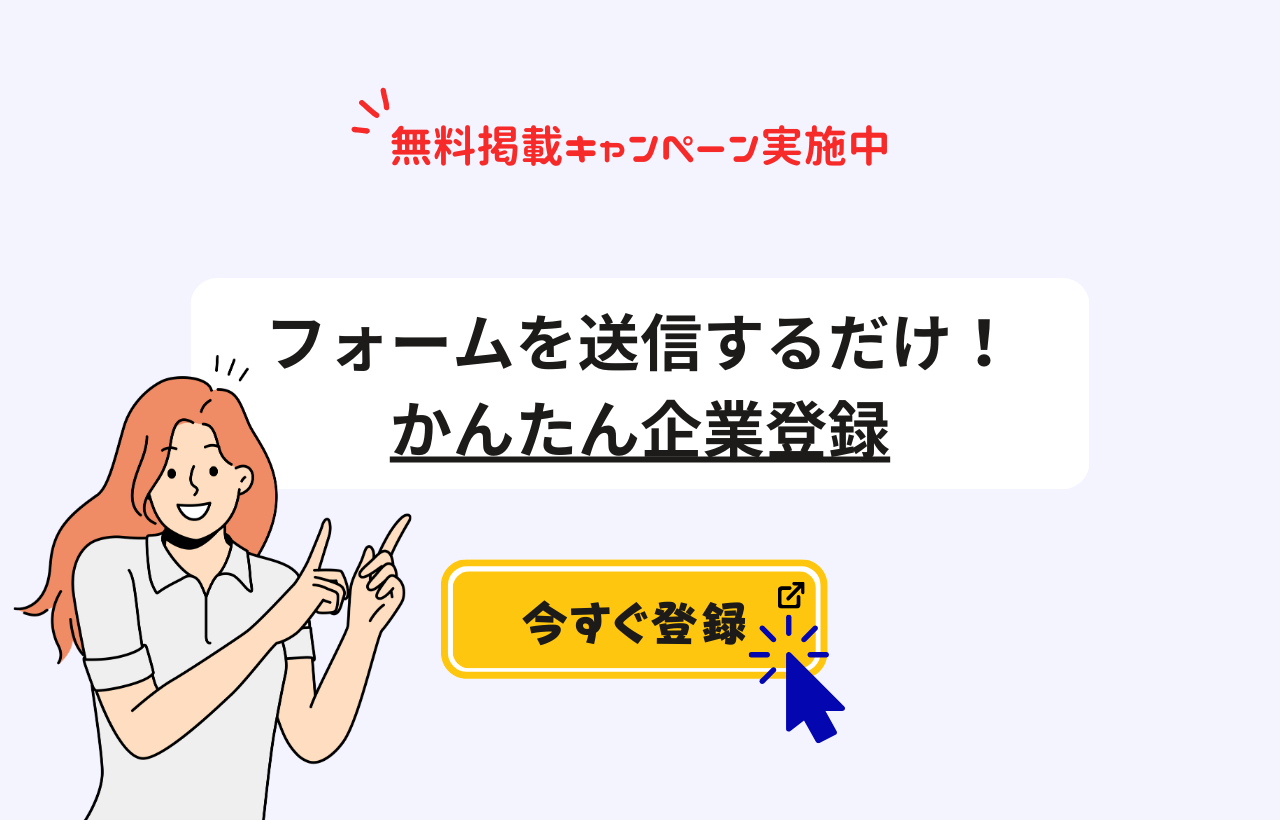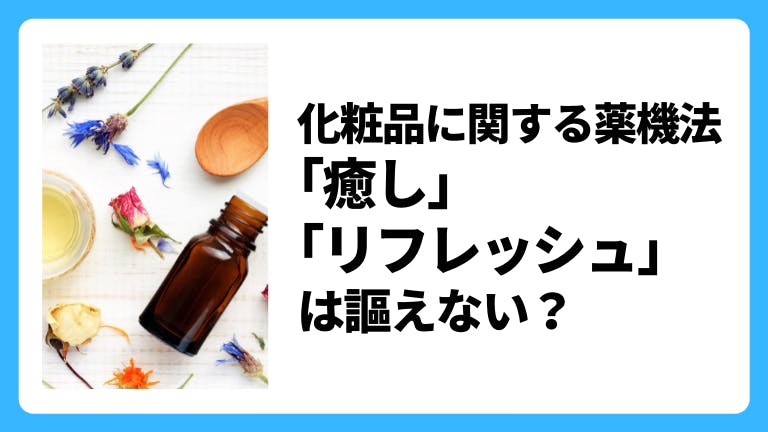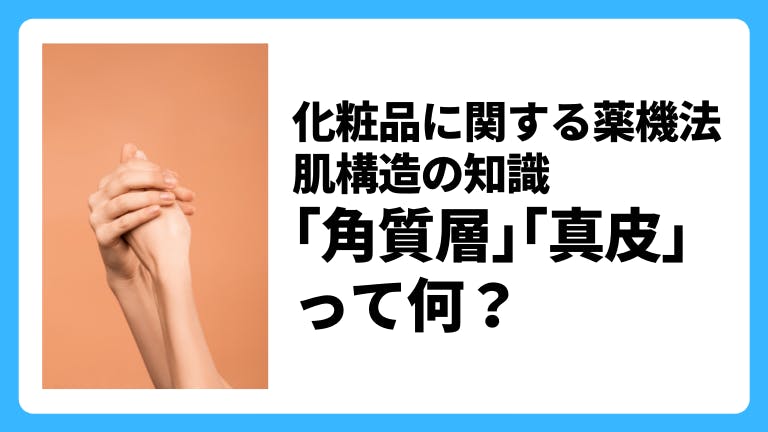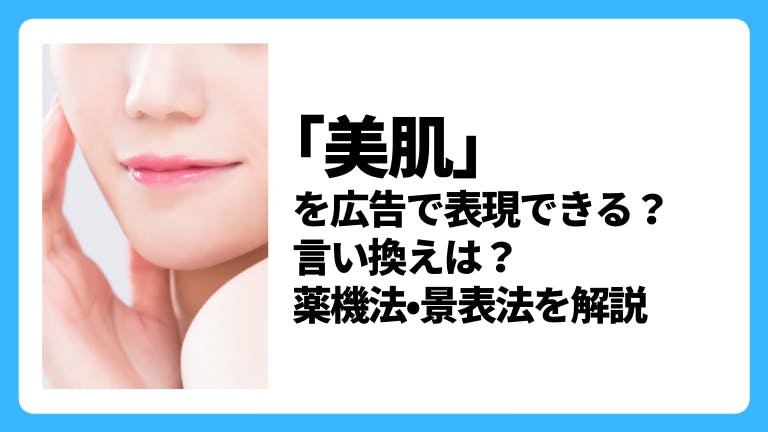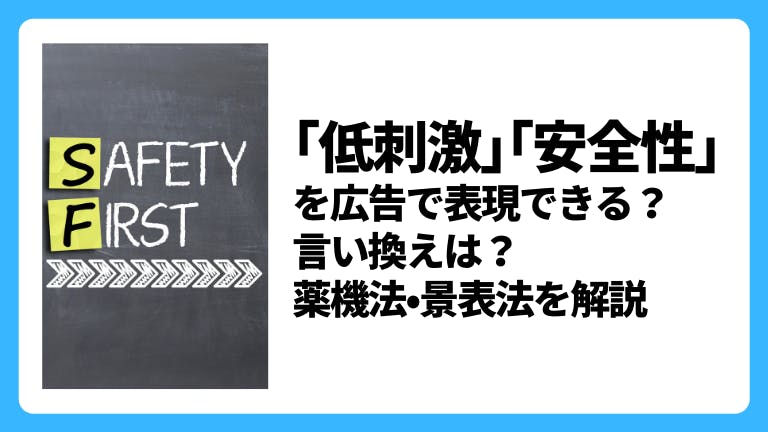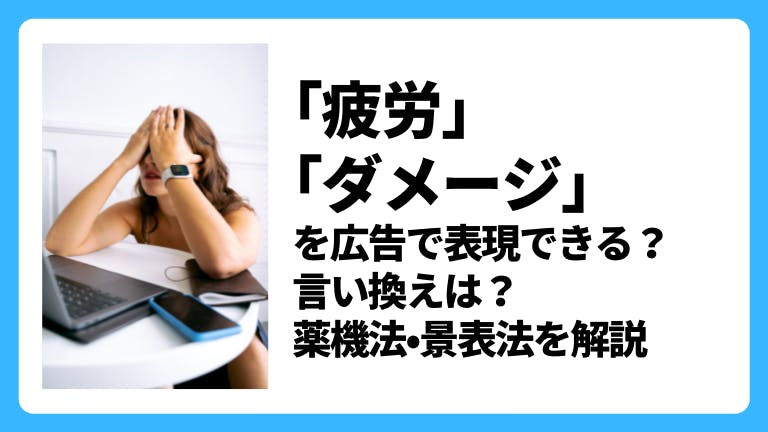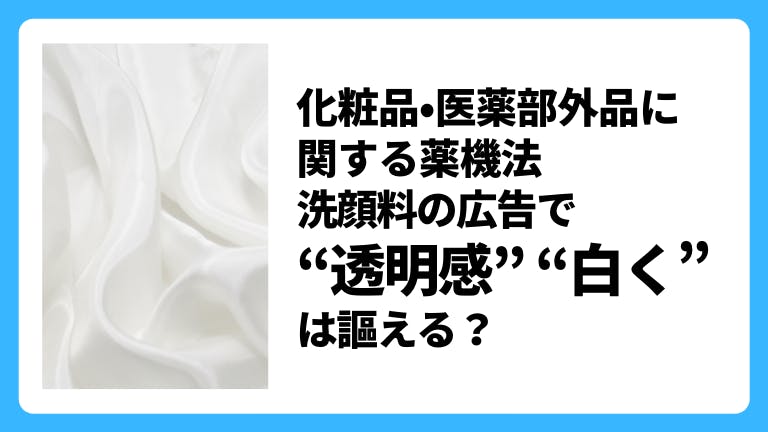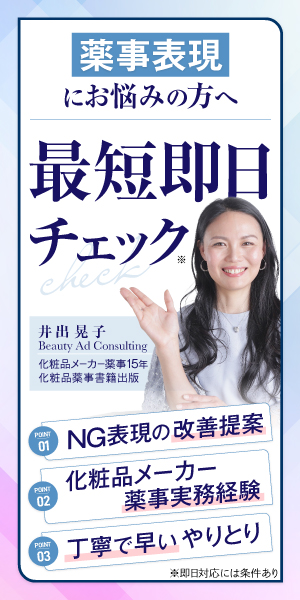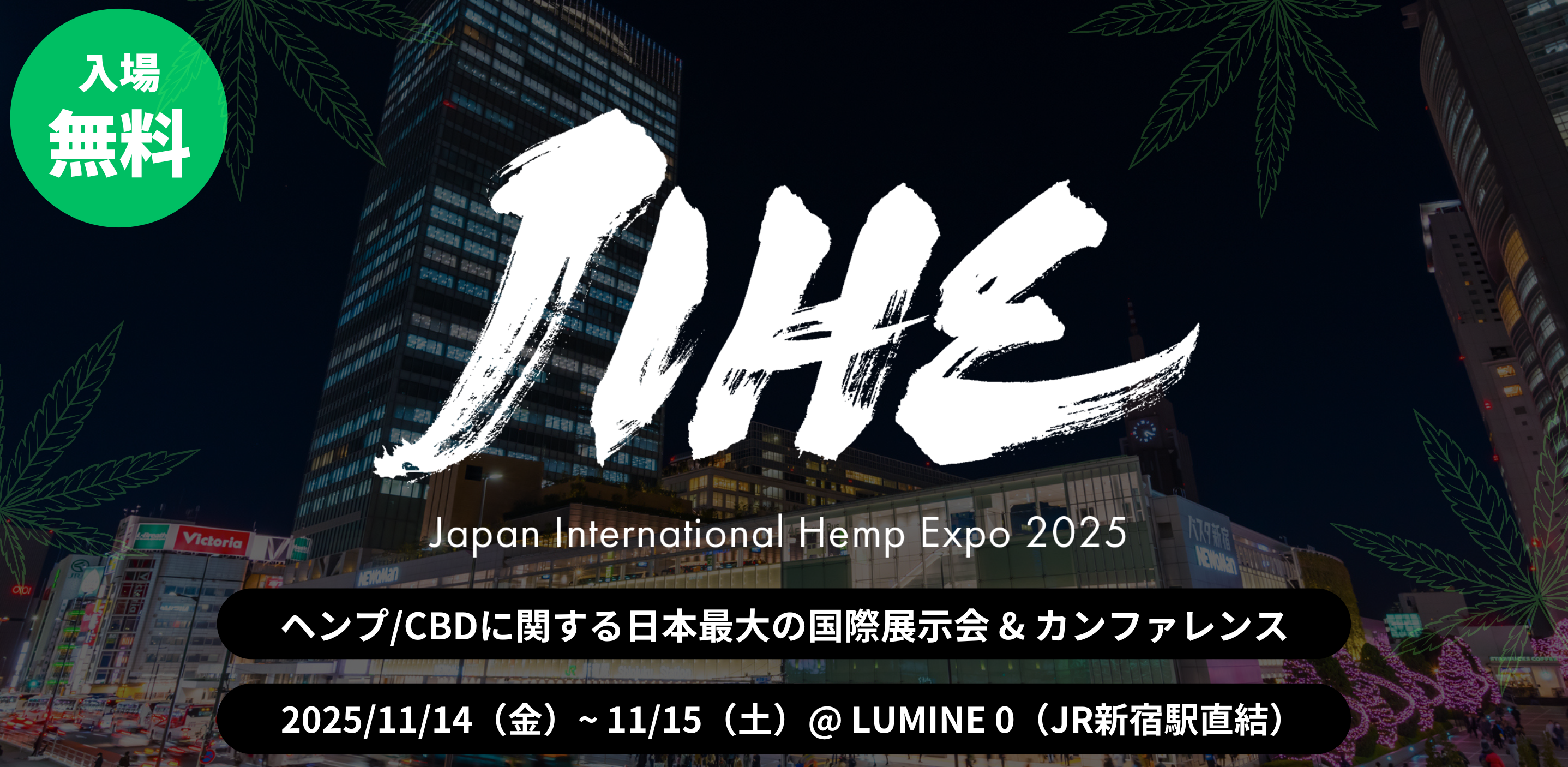
最終更新:2024/08/09
食品表示の基準を守らないとどうなる?違反事例を紹介
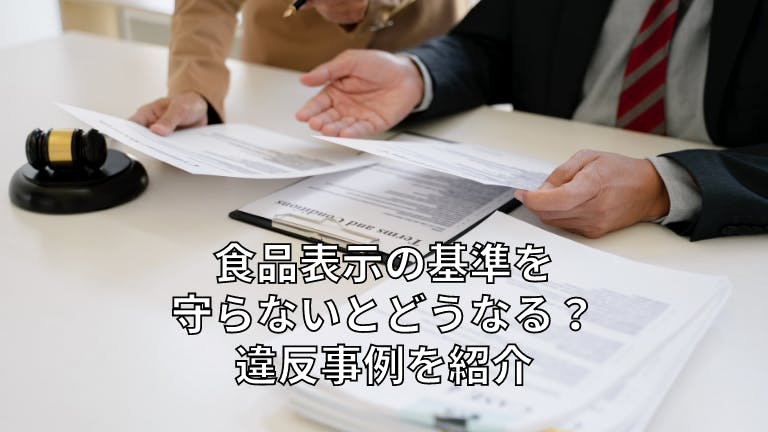
食品表示法の目的は、「食品を摂取する際の安全性」と「一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保」ですが、もし食品表示の基準を守らないとどうなるでしょうか。 今回は、食品表示を守らなかった場合の処置と、食品表示違反事例について解説します。
食品表示違反で最も多い内容は?
食品表示の違反で、多いものの順に「原産地の誤表示・欠落」、「原材料名の誤表示・欠落」、「名称の誤表示・欠落」です。 平成29年に食品表示基準が改定・施行されましたが、平成30年では表示違反での指導件数が218件であったのが、平成元年では169件に減少しています。 特に「原産地の誤表示・欠落」は、施行間もない事から製造者が食品表示法を曲解しているケースもありました。
「原産地の誤表示・欠落」の製造者の実情
ここで、「原産地の誤表示・欠落」が起こる実情について、少し書かせていただきます。 加工食材は、原料の調達から商品作りが始まっています。 特定地域の一定量の連続した収穫が見込めない場合、原産地を頻繁に表示変更せざるを得ません。 食品表示の場合、パッケージへの印刷方法が2種類あります。
- パッケージにあらかじめ印刷されている場合(例:ポテトチップスなどの菓子類)
- ラベル等で、後から印刷が可能な場合(例:弁当や総菜の表示ラベル)
1.の場合は、大量生産の場合がほとんどで、原料が一定量確保できる見込みでパッケージの数量を見極める場合が多いです。 この場合で原産地の誤表示・欠落が発生する状況は、「原料のロット(原産地)が変更になったにも関わらず、包装側に通達されず包材変更がされなかった。」と言うケースが考えられます。 発生頻度は少ないのですが、一度発生すると大量に発生してしまうのが特徴です。 また、急な原産地の変更で使用できない包材が大量に発生しやすいのも、このケースの特徴です。
2.の場合は、原産地の変更に柔軟に対応できる一方、表示間違いを起こしやすいのが特徴です。 この方法のメリットは、原産地表示が変更しやすい為、原料の確保が容易である点です。 しかし、変更頻度が多くなるため、誤表示の機会も多くなります。 誤表示の発生量が少ないのですが、発生件数が多くなりやすくなります。 包材のロス(使用できない包材の発生)は少量または全く発生しないのが特徴になります。
このように、原産地表示は製造者にとっては、大きな負担(管理面にしろ金額面にしろ)になっているのが実情です。
消費者庁、国税庁及び農林水産省による指導・指示・命令とは
食品表示法の第五条 食品表示基準の遵守では、次のように書かれています。
第五条 食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。
表示違反をした場合は次の順に執行されます。
[違反の発覚]
まず違反に対し、立ち入り検査等が入ります。 そこで、次の内容にすべて当てはまる場合は「指導」を行います。
- 食品表示基準違反が常習性がなく過失による一時的なものであること。
- 違反事業者が直ちに表示の是正(表示の修正・商品の撤去)を行っていること。
- 事実と異なる表示があった旨を、社告、ウェブサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供しているなどの改善方策を講じていること
過失であり違反をすぐに是正・告知対応を行えば、基本的に「指導」となり、罰則や行政による公表は行われません。 上記の一つでも当てはまらなければ、[指示]になります。
[指示]
「表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しなかった場合」は、食品表示法第6条第1項、第3項にて「指示」が出されます。
第六条第1項 食品表示基準に定められた第四条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。 第3項 表示事項が表示されていない酒類の販売をし、又は販売の用に供する酒類に関して表示事項を表示する際に遵守事項を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は財務大臣(内閣府令・財務省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・財務省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
つまり、食品表示法を守っていない製造者に対して「直しなさい。守りなさい。」と、言っているのです。
[命令]
「命令」については、食品表示法では次のように書かれています。
第六条第5項 内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 第8項 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をし、又は販売をしようとする場合において、消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、当該食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
これは、「指示」を受けた業者が、正当な理由も無く、言う事を効かなかったら、指示した内容を命令するよ。という事です。 また「緊急の必要性」がある場合は、「回収等命令」が執行されます。俗にいう「回収命令」です。
「命令」は強制力があり、従わない場合は罰則が課せられます。 表示事項を表示せず、又は遵守しなかった場合は、法人で1億円以下の罰金が処せられます。 食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について、食品表示基準に従った表示をしない場合で、緊急の必要性があり回収命令違反の場合は、法人で3億円以下の罰金、緊急の必要性が無い場合は1億円の罰金となります。
表示違反の実例
事例1 焼き菓子 優良誤認の例
「あきたこまち米使用純米クッキー」、「コシヒカリ純米クッキー」と記載することにより、あたかも、主原料として「あきたこまち」又は「こしひかり」と称する品種の米穀が使用されているかのように示す表示でしたが、対象商品の主原料は小麦であり、米については極めて少量でした。 この例は、原材料表示の間違いではないが、商品名とその内容が、「実際のものよりも著しく優良であると示すもの」と消費者を誤認させる例です。
事例2 はちみつ 優良誤認の例
「原材料名/蜂蜜(国産)」等と記載することにより、あたかも、対象商品の内容物は国産のはちみつであるかのように示す表示でしたが、実際には対象商品の内容物は過半が国産以外のはちみつでした。 この例は、商品ラベルの間違いで、原産地を偽って標品が優秀であると、消費者の誤認を招く「優良誤認」の例です。
まとめ
食品表示法違反の実例を調べて見ましたが、公表された実例では実際の商品よりも良く見せようと、意図的に違反表示を行っている印象を受けました。 一方、上記で述べた原料の産地が頻繁に変わる事での表示違反は少なく、実例があるのは日本産か外国産かと言った物でした。 製造メーカーとしては、食品表示法の罰則より商品回収の方が、企業イメージや損金の面で非常に大きいと言えます。回収命令が発令されなくても、納入先の要請で自主回収を迫られます。 よって、わずかなコストダウンのために虚偽の表示を行うと、非常に痛いしっぺ返しを食らう事になりかねません。
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能