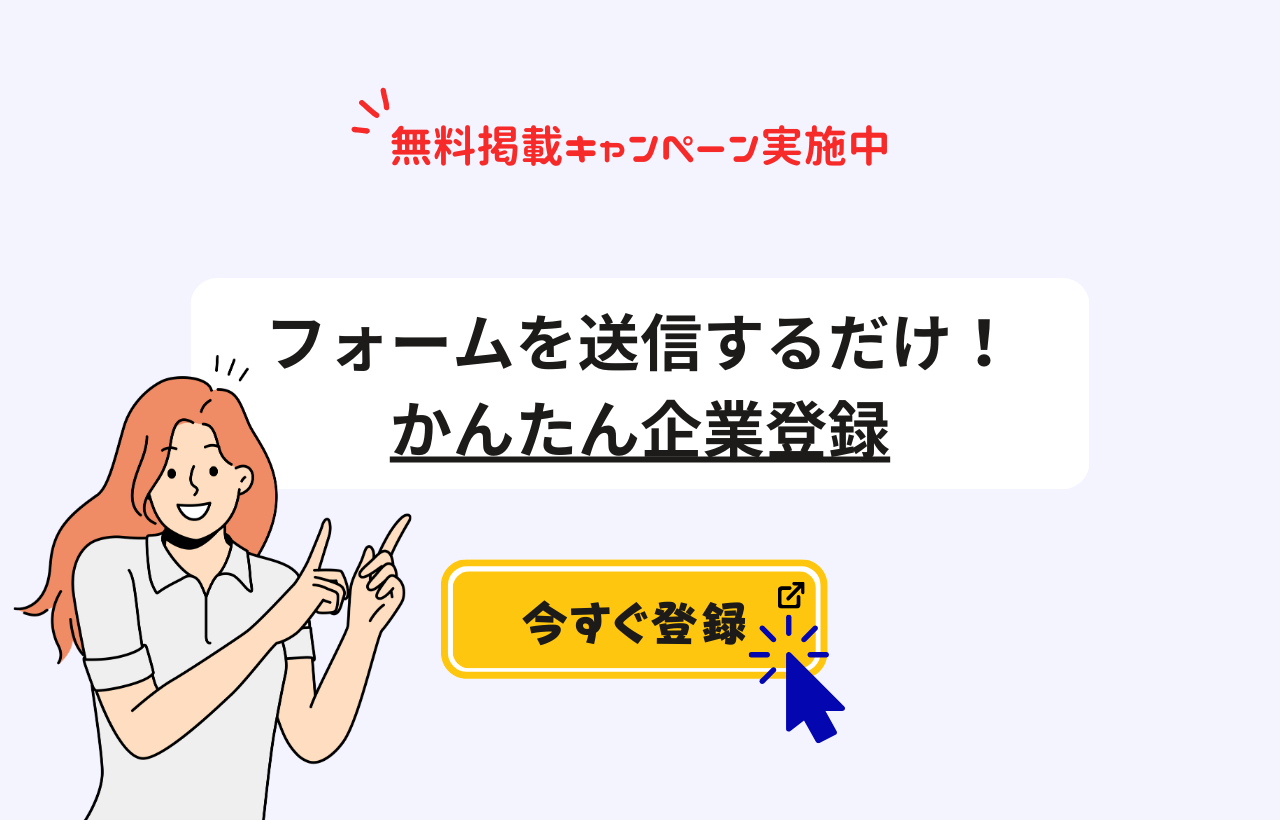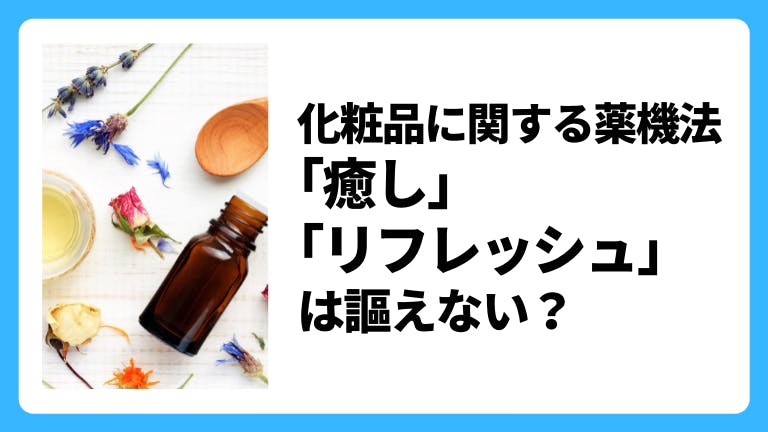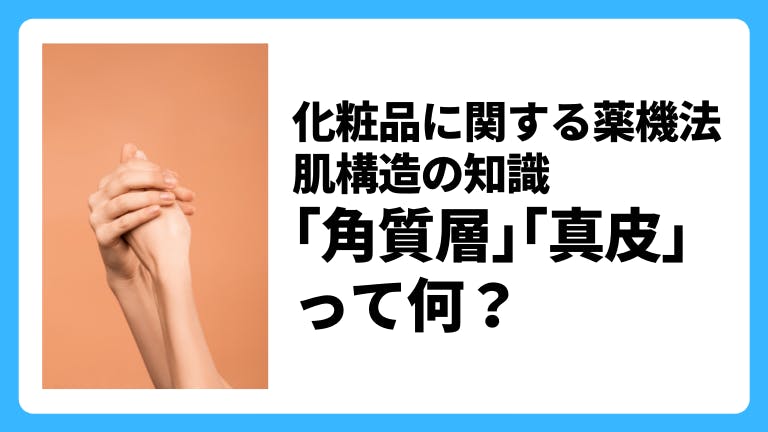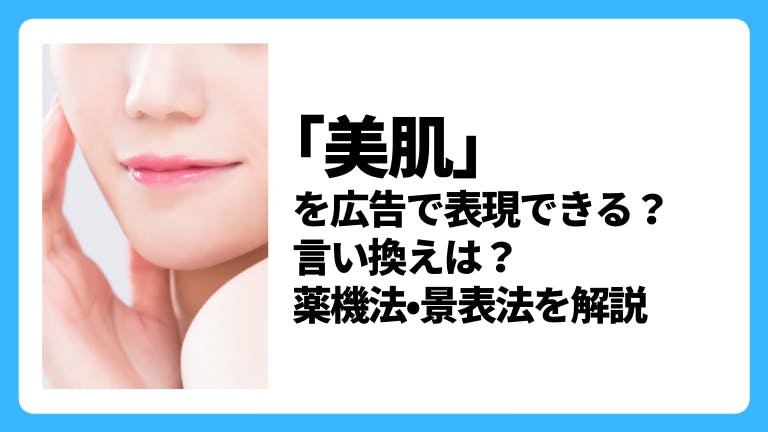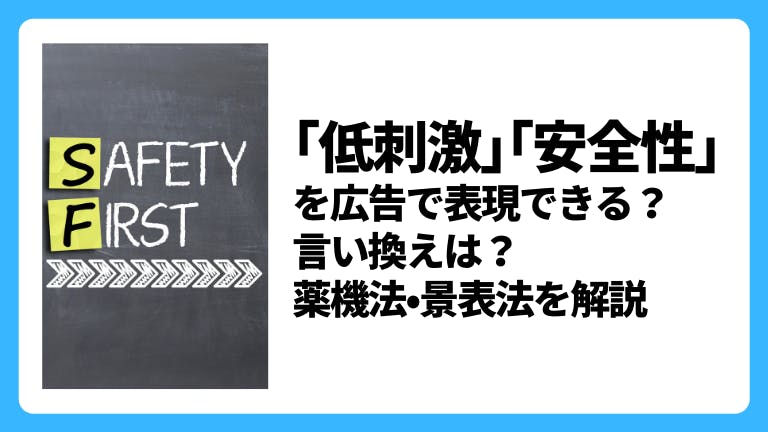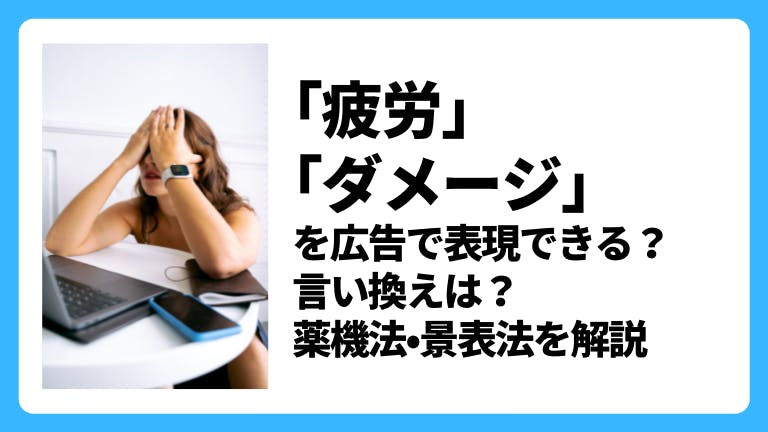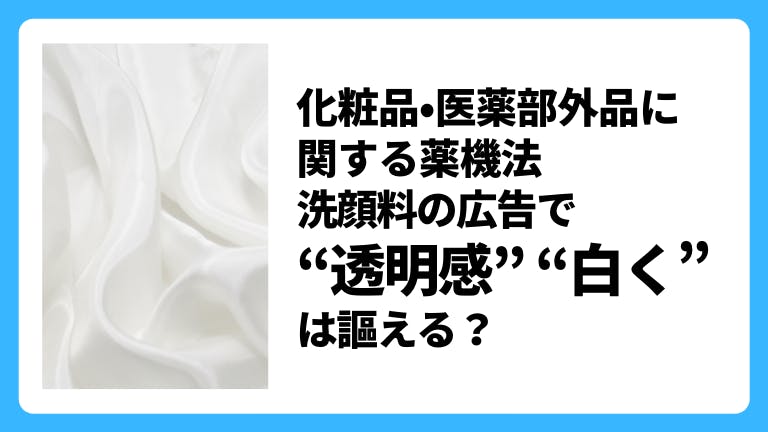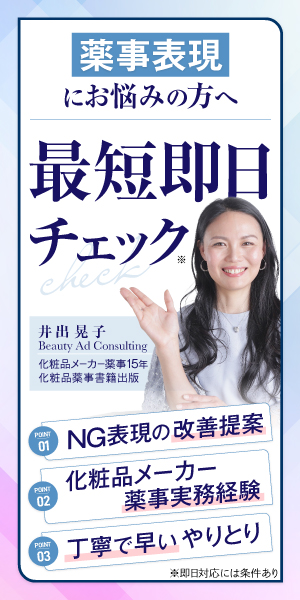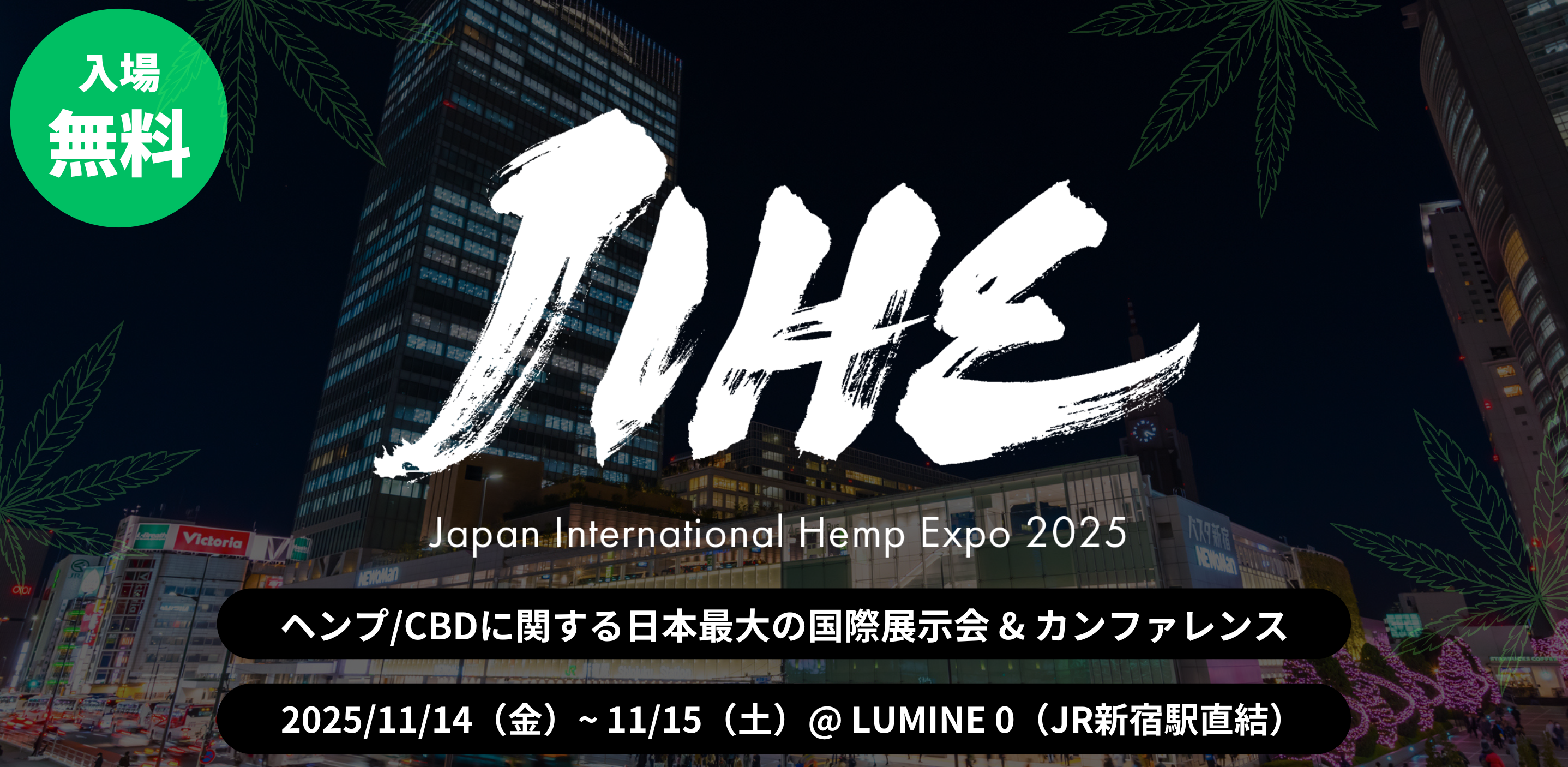
最終更新:2024/08/09
食品表示 保健機能食品のルール
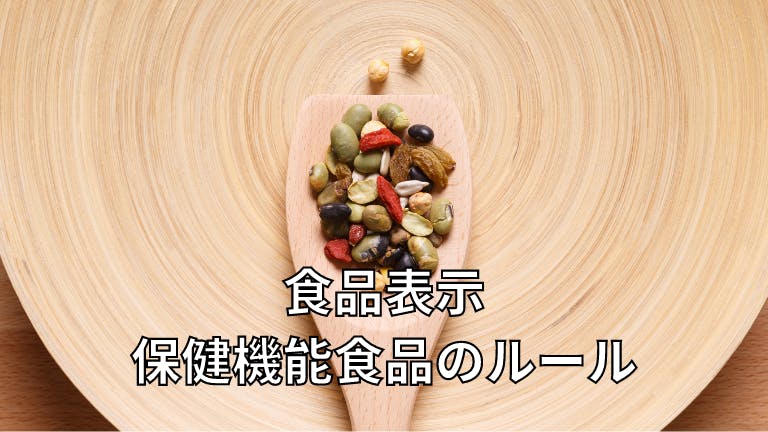
皆さんは「トクホ」と言う言葉をテレビCM等で良く耳にすると思います。 「飽食の時代」と呼ばれてすでに50年以上経過しております。今や、食は空腹を満たすだけで無く、健康維持に重視した商品が多数発売されています。表示の歴史から見て、保健機能食品が大きく発展したのはつい最近になります。 この記事では、保健機能食品について解説していきます。
保健機能食品表示の歴史
昭和59年 当時の文部省で「「食品機能の系統的解析と展開」と言う特定研究が実施されました。 これが機能性食品の始まりになります。
昭和63年には、学識経験者による「機能性食品懇談会」が発足、食品による生活習慣病一次予防の重要性、科学的根拠に基づく情報を表示した食品の提供の必要性等について検討が開始されました。
特定保健用食品の標示について施行されたのは平成3年になってからです。 そして、平成5年に特定保健用食品標示第1号が誕生します。 平成13年 「保健機能食品(栄養機能食品、特定保健用食品)」制度施行されました。 食品衛生法に規定されるようなり、これに基づく審査が開始されるようになります。
「医薬品の範囲に関する基準」の改正により、錠剤やカプセルの剤型が「食品」と標示できる事から、形状規制は外れました。これがきっかけで商品の幅が増えてきました。
平成27年 食品標示法施行に至るまで、健康食品の在り方について多くの検討会が発足しました。
保健機能食品の定義
食品標示基準には、次のように定義されています。
・特定保健用食品 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。
・機能性標示食品 疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第四十三条第一項の規定に基づく許可又は同法第六十三条第一項の規定に基づく承認を受け、特別の用途に適する旨の表示をする食品(以下「特別用途食品」という。)、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料及び国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第十一条第二項で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品を除く。)であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の六十日前までに消費者庁長官に届け出たものをいう。
・栄養機能食品 食生活において別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分(ただし、錠剤、カプセル剤等の形状の加工食品にあっては、カリウムを除く。)の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとしてこの府令に従い当該栄養成分の機能の表示をする食品(特別用途食品及び添加物を除き、容器包装に入れられたものに限る。)をいう。
出典:食品表示基準
以上の内容を補足説明しますと、
- 特定保健用食品 体の生理的機能に作用する成分を含み、それを飲食する事で特定の保健の目的が期待できる内容の標示をする食品です。食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受けて許可を得なければ表示できません。
- 機能性標示食品 国のルールに則り、事業者が食品の安全性・機能性を科学的に立証し、販売前に消費者庁長官に届け出ることで、機能性を表示することができます。特定保健用食品と異なるのは、国の審査は無い事です。
- 栄養機能食品 特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。一般用加工食品及び一般用生鮮食品に分類されます。国の審査は必要なく、自己認証制度となります。
保健機能食品の目的
保健機能食品の目的については、「保健機能食品制度の創設について」平成13年3月27日医薬発第244号に記載されています。 要約すると、消費者の食生活が多様化し、多種多様な食品の選択が可能となった今、その食品の特性を理解し消費者自身が正しい判断によって食品を選択出来るようする必要があります。 こうしたことから、一定の規格基準、表示基準等を定めるとともに、消費者に正しい情報を提供し、消費者自身の判断で食品の選択を行う事ができるように制度化しました、と書かれています。
消費者の判断により、バランスの良い食生活を送り保健に努めるのが目的です。
保健機能食品の表示ルールについて
特定保健用食品・機能性食品・栄養機能食品のそれぞれについて、補油時ルールを開設します。
特定保健用食品国の審査を受けて許可されることで、「特定保健用食品マーク」いわゆるトクホマークを標示する事が出来ます。この場合の特別な表記は、「許可表示」「1日当たりの摂取目安量」「摂取をする上での注意事項」です。「許可表示」は、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の一文を入れます。その食品を取ることで、特定の健康の目的が期待できる旨の表示を記載します。
- 1日当たりの摂取量 1日に摂取する目安量を記載します。
- 摂取方法、摂取をする上での注意事項 摂取方法や摂取した場合の注意事項を記載します。
- 栄養成分表示・関与成分 栄養成分表示は、すべての加工食品に記載されているが、特定保健用食品には「関与成分」量を表示しなければならない。関与成分とは、特定保健用食品に含まれる保健機能を有する成分の事である。
機能性食品
機能性食品特有の記載事項は、「届け出表示」「一日摂取目安量、摂取方法」「届出番号」になります。
- 届け出表示 事業者が科学的根拠を基にした機能性について、消費者庁長官に届け出た内容を記載します。
- 一日摂取目安量、摂取方法 摂取方法や摂取する目安量の注意事項を記載します。
- 届出番号 消費者庁のウェブサイトで、この番号から安全性や機能性の根拠に関する情報を確認できます。
表示には次の注意が必要です。
- 「診断」「予防」「治療」「処置」などの医学的な表現はできません。
- 治療効果、予防効果を暗示する表現は出来ません。
- 未成年、妊産婦、授乳婦に対し、機能性を訴求するような表現は出来ません。
- 肉体改造、増毛、美白などの意図的な健康増強を表す表現は出来ません。
- 科学的な根拠の説明が十分に説明できない機能性は表現出来ません。
表現できる例として、「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」があります。
栄養機能食品
栄養機能表示が許される栄養成分が上下限値の範囲にあれば、機能表示が可能です。同時に注意喚起表示も記載します。 注意喚起表示の中には、1日の摂取目安量を超える過剰摂取の注意を促す表示を含んでいます。
また、すべての商品に特定保健用食品と区別するために、「本品は特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」の表示が必要となります。
まとめ
食品標示の歴史では、新しい部類にはいる保健機能食品です。 医薬品と一般食品の間に位置するようなサプリメントなども多く販売されています。 現在、サプリメントは食品の扱いであり、医学的な効能を表示が出来ませんが、それは上記の理由によります。 保健機能食品の中の3種類の分類についても、今回解説致しました。 特定保健用食品・機能性食品・栄養機能食品の違いについて、商品を実際に手に取り見ていただけばと思います。
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能