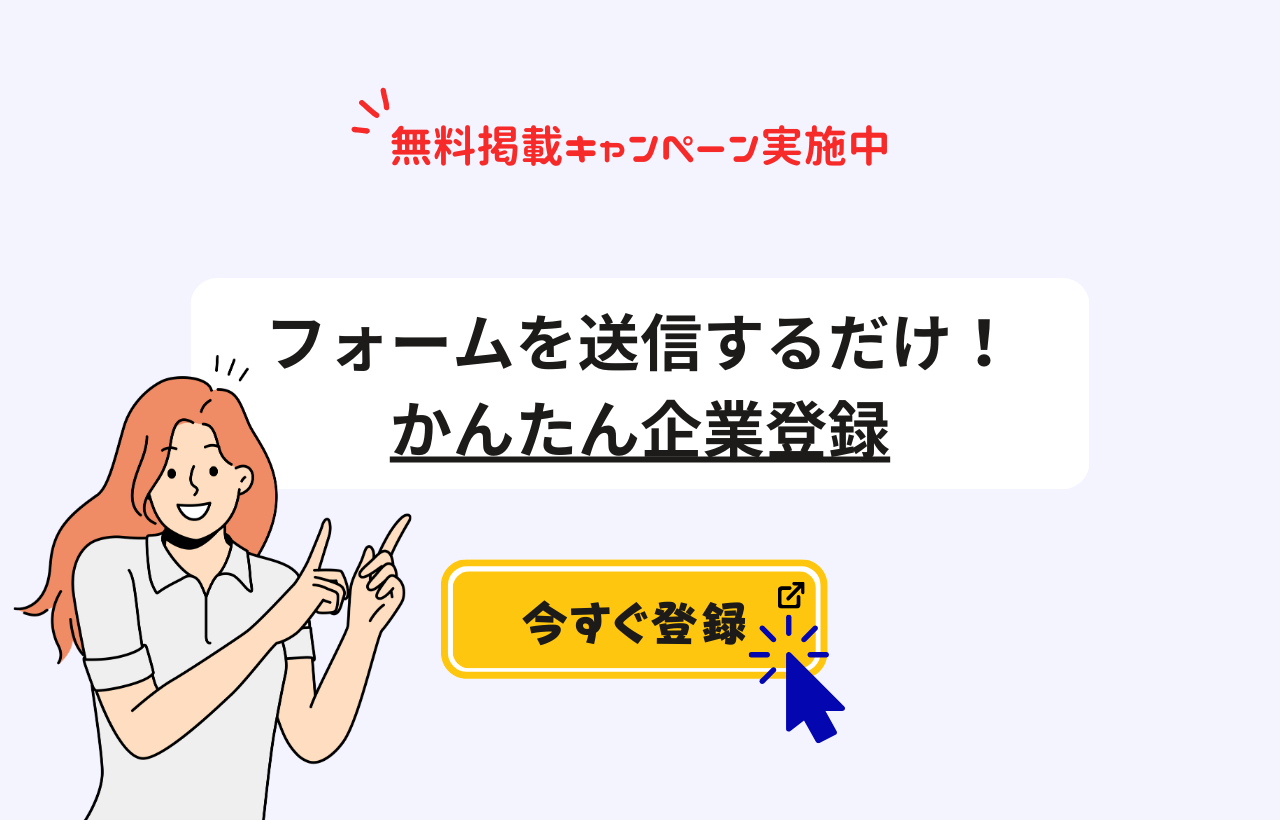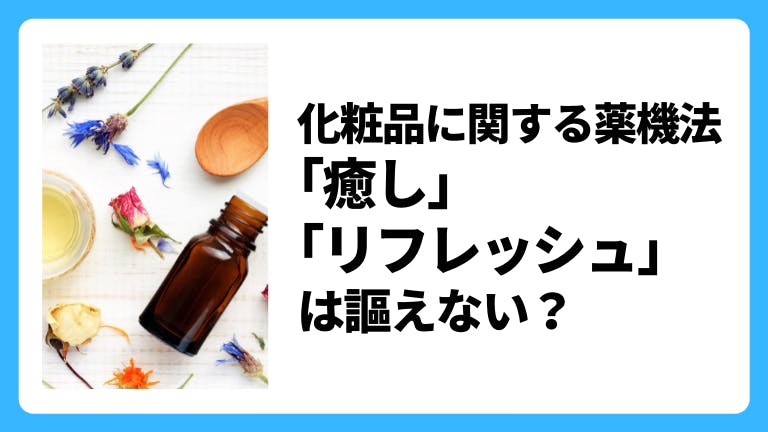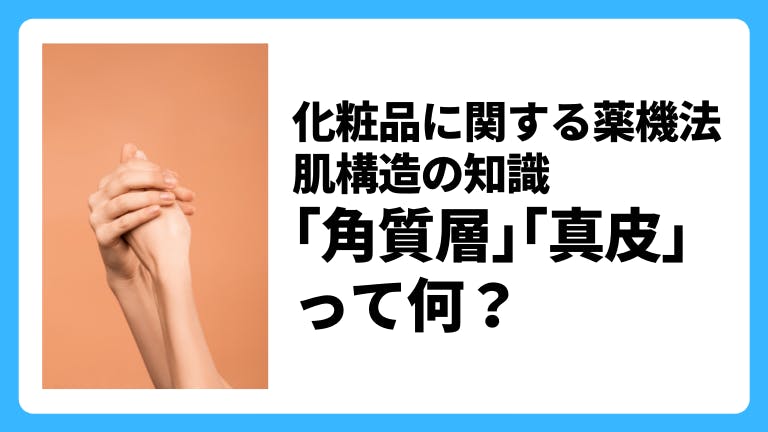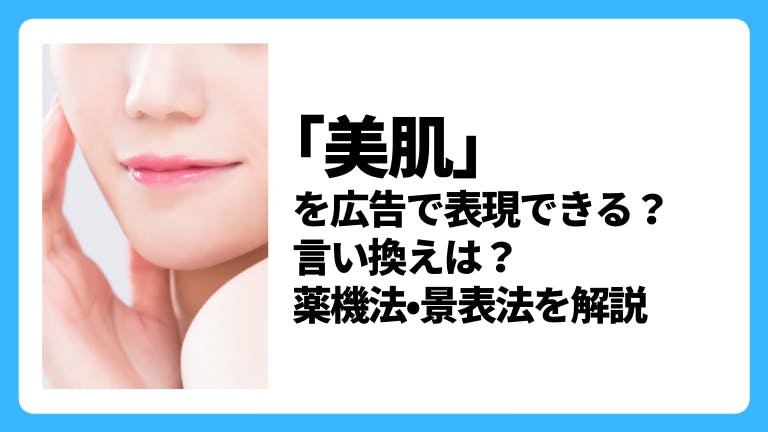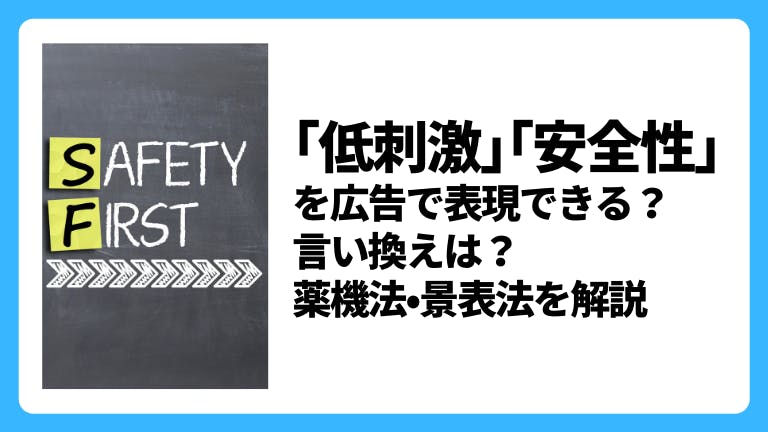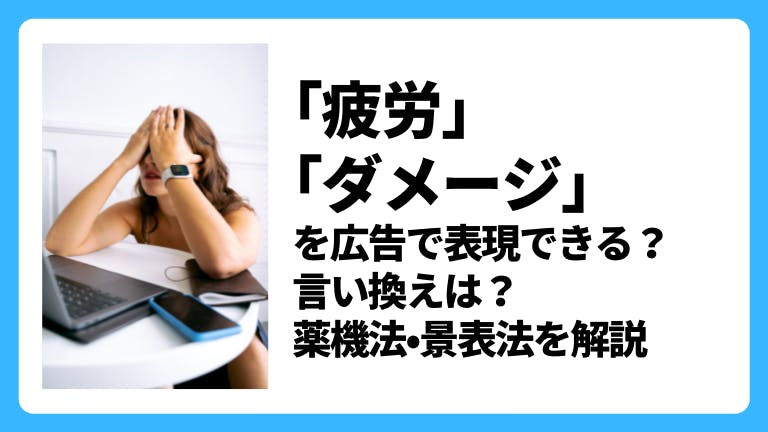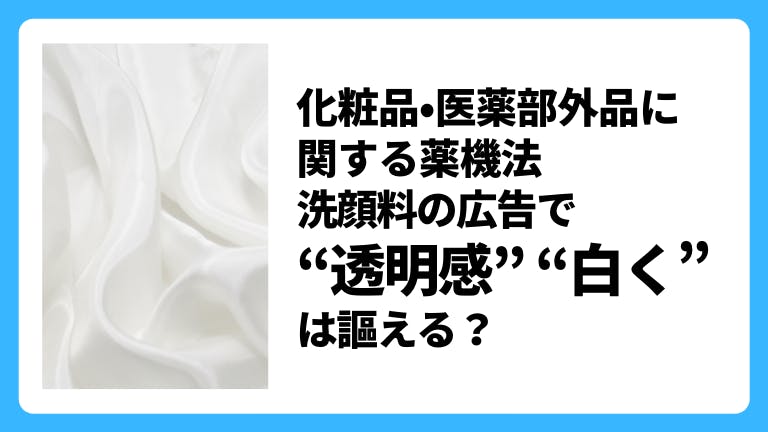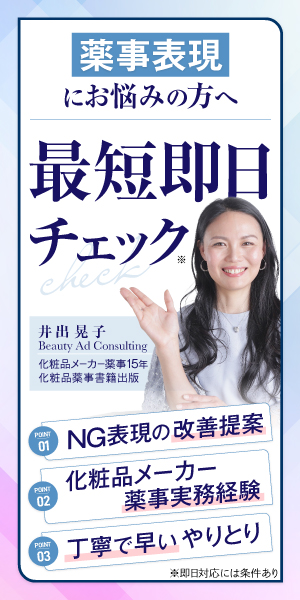最終更新:2024/08/10
食品表示 原料原産地表示のルール

私たちの食生活において加工食品が占める割合は増え、種類も多種多様化しています。また、加工食品に限らず生鮮食品も同様に、その流通も国際的になっています。
食品の安全性や栄養成分に関する情報提供は、健康を守るためには必要不可欠なものになっています。食品を販売する上で、「何をどのようにしたらよいかわからない」「加工食品についての食品表示の現制度が複雑」と悩まれている方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、食品表示に関する原産地表示のルールについて解説していきます。
食品表示に義務付けられる原産地表示のルール
2015年4月1日に新しく施行された法律「食品表示法」は、それまでにあった3つに分かれていた法律と法令を一元化したものです。
食品の原材料や添加物、栄養成分などの表示方法を統一する「食品表示法」とは、これまでの食品衛生法・日本農林規格(JAS)法・健康促進法の3法に分かれていた表示ルールを一つにまとめたものです。 栄養表示の義務化や原料原産地表示の対象品目拡大など、表示内容の基準が消費者によりわかりやすいようになりました。
また、2017年9月に食品表示基準が改正・施行され、国内で作られたすべての加工食品に対して、原料原産地表示を行うことが義務付けられました。この制度の経過措置期間は令和4年(2022年)3月までなので、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示に対応しましょう。
日本国内で製造か加工されたすべての加工食品
日本は食料の約6割(カロリーベース)を海外からの輸入に頼っているため、国内で作られた加工食品でも、その原材料は国産とは限りません。なので、外国産が使われている可能性があります。
例えば、麺などの原材料である小麦の約9割、しょうゆ・みそ・納豆などの原材料となる大豆の9割以上が外国からの輸入に依存しています。 しかし、これまでは一部の加工食品を除き、多くの加工食品には原材料の原産地の表示の義務というものが存在しませんでした。そのため、消費者が加工食品を選ぶときに、十分な原材料の現地情報を得ることが難しかった面がありました。
そこで、消費者が自主的かつ合理的に加工食品を選択することができるように、国内で製造もしくは加工されるすべての加工食品に原材料の原産地表示を義務付ける新たな表示制度「新たな加工食品の原料原産地制度」が2017年9月からスタートしています。
新しい加工食品の原料原産地制度のポイント
新しくなった加工食品の原産地表示制度のポイントは以下の2つです。
- 日本国内で製造又は加工されたすべての加工食品が対象
- 製品中、最も多く使用された原材料の原産地を表示
輸入した加工食品(原産国名の表示は義務)・外食・作ったその場で販売する食品(店内で調理された惣菜や弁当)・容器に入れずに販売する食品は、加工食品は原料原産地表示の対象とはなりません。
製造中、最も多く使用された原材料の原産地を表示
加工食品は、多くのケース何種類も原材料が使用されています。原材料一つひとつの原産地を表示しようとすると、場合によって情報が分かりにくくなり、かえって消費者が混乱してしまう可能性が危惧されてます。 そこで、原材料の原産地に関して以下のようなルールのもと表示されることになりました。場所は、加工食品パッケージになります。
原料原産地の表示の仕方
- 製品中、最も多く使用された原材料が生鮮食品の時、その原産地を表示(国産の場合は「国産」である旨を表示)。
- 2か国以上の原産地の原材料を混ぜて使っている時、多い順に原産地を表示。
- 製品中、最も多く使用された原材料が加工食品の時、その製造地を表示。 原則として、その加工食品の製造地が○○製造と表示されます。しかしながら、最も多い原材料に使用された生鮮食品の原産地が判明しているケースでは、○○製造の代わりにその原産地が表示される場合があります。
- 3か国以上の原産地の原材料を混ぜて使用された時、3か国目以降を「その他」と表示することも可能。
- 原則の「国別重量順表示」が困難な時、一定の条件のもと、「又は表示」・「大括り表示」の表示ができる。
加工食品の中には、2か国以上の原産地の原材料をまぜて作った場合に、原材料の調達先が変わったり、使用量の順番が変動したりして、国別重量順に原産地を表示することが困難なときがあります。そのような場合には、一定の条件のもとで「又は表示」や「大括り表示」による表示が認められています。
「又は表示」とは
過去の使用実績などに基づき使用が見込まれる複数国を、重量割合の高いものから順に、「又は」でつないで表示する方法です。重量割合の高いものの順番は、過去の使用実績などに基づいて表示されるため原料原産地名に近接した箇所に「又は表示」をした根拠が書かれます。
「大括り表示」とは
3か国以上の外国の原産地を「輸入」と括って表示する方法です。輸入と表示されていた場合、国産の原料は使用されていません。 また、3か国以上の外国産と国産の原材料を混合して使用する場合には、重量割合の高い順に「国産・輸入」「輸入・国産」と表示されます。
まとめ
原産地名の表示は、消費者の信用と信頼を得るためにとても大切なものです。 ぜひ参考にしてください。
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能