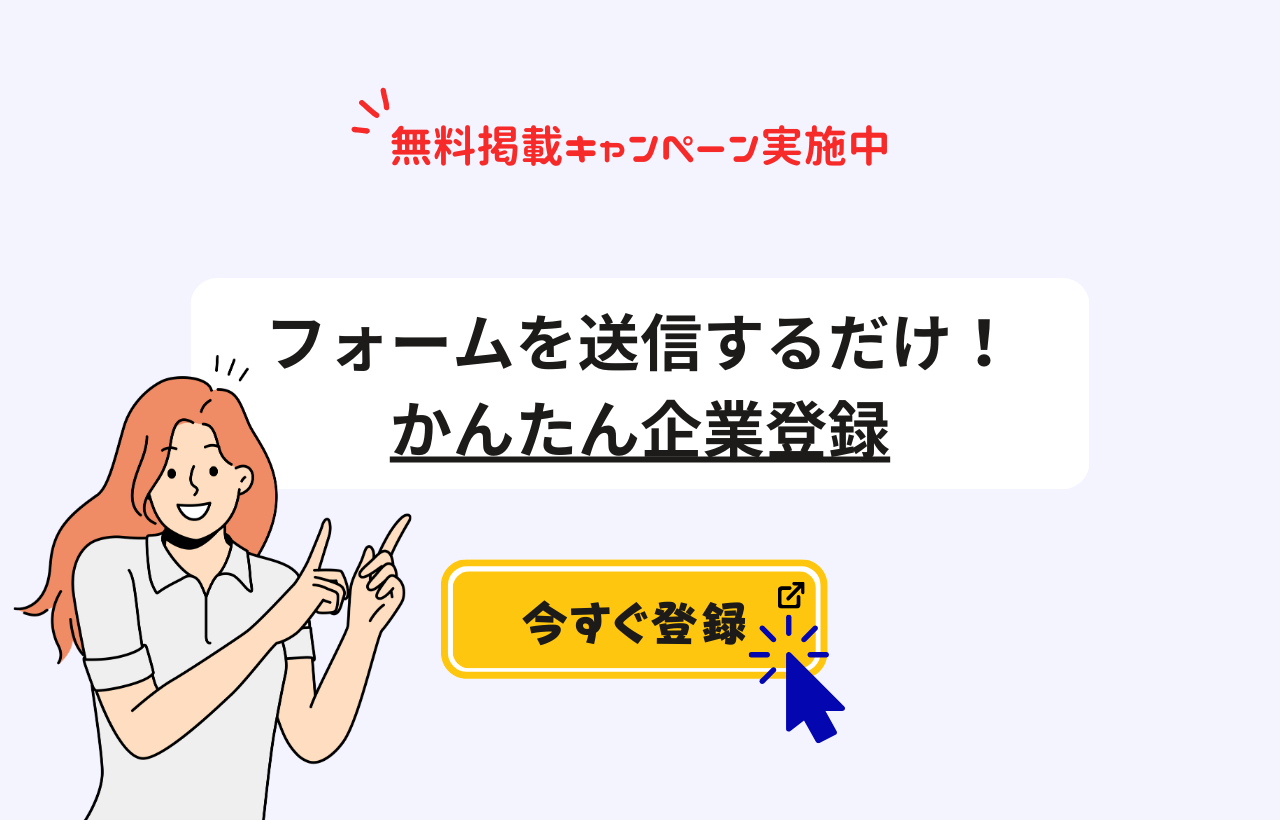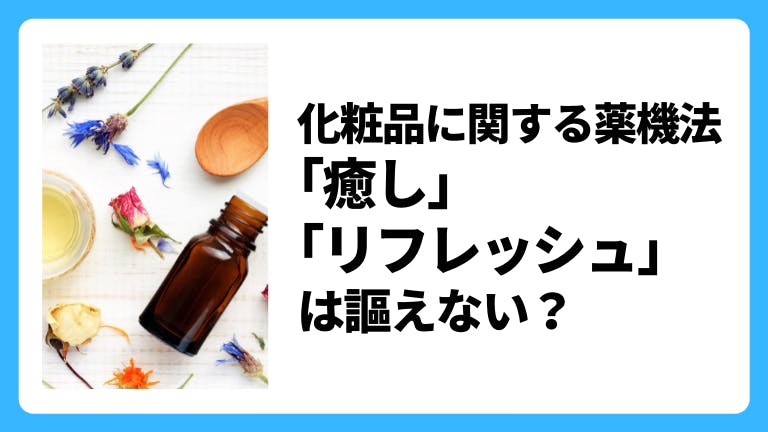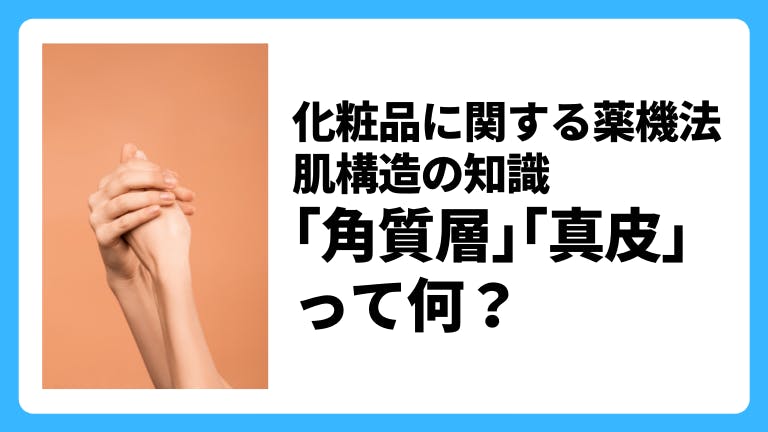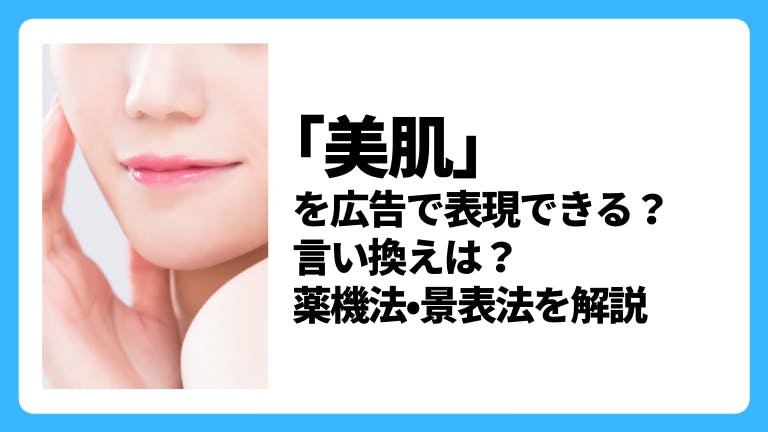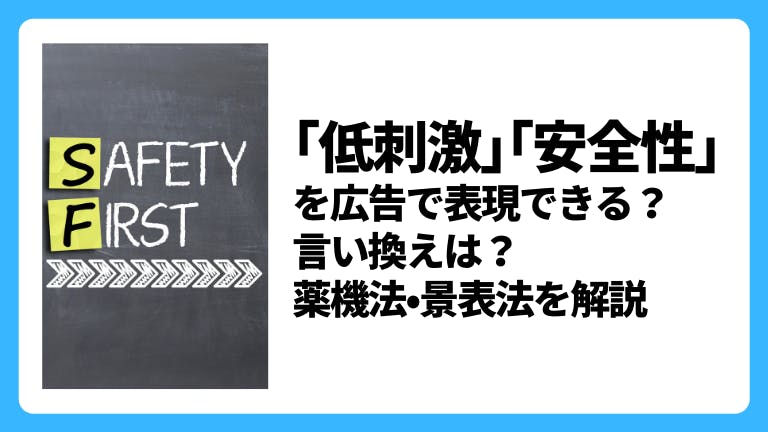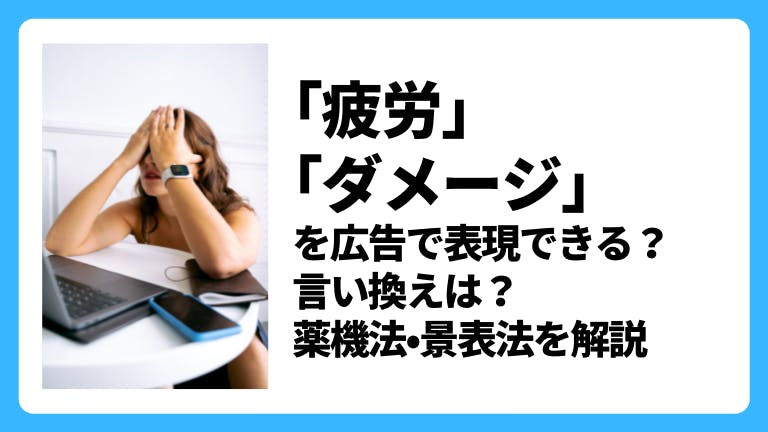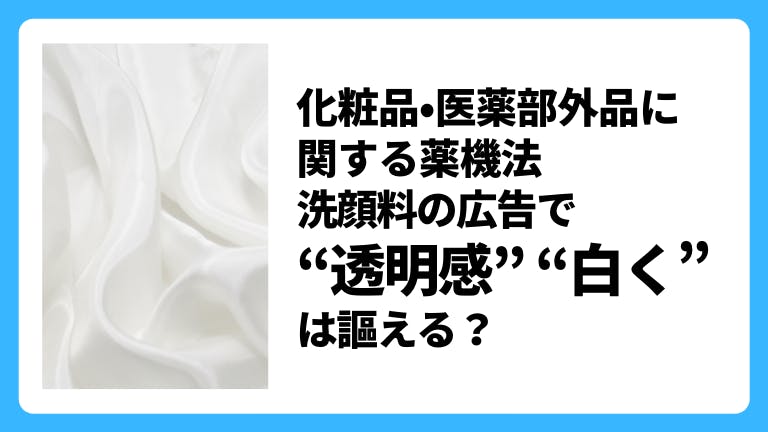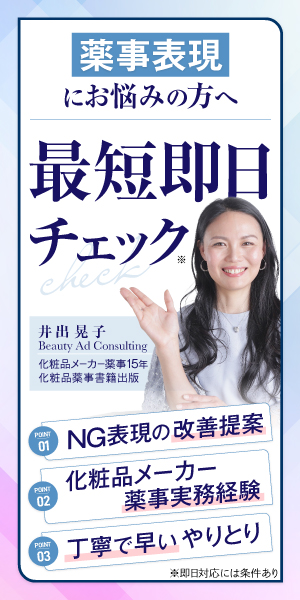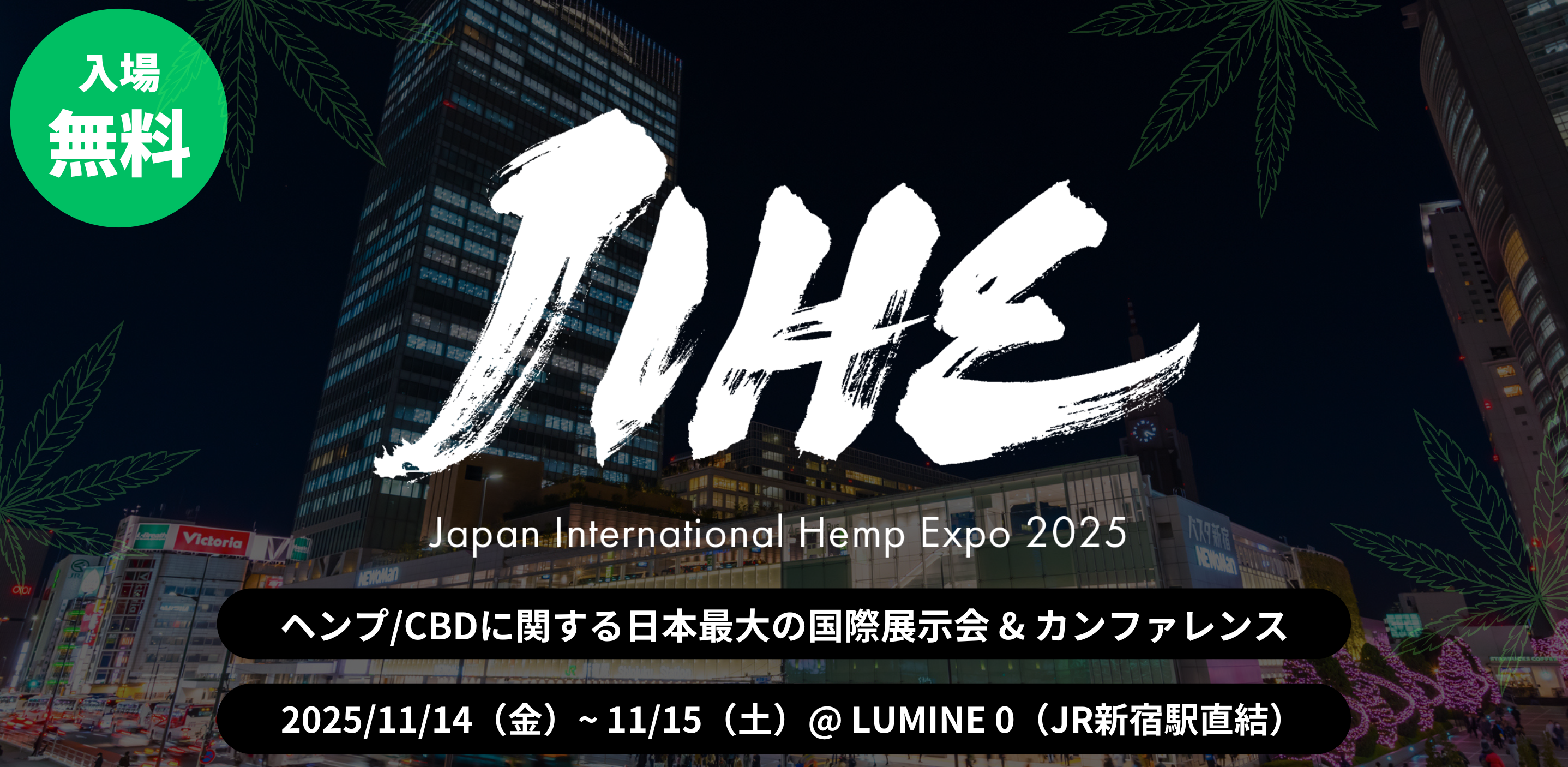
最終更新:2024/08/10
生鮮食品における食品表示の基本ルール

生鮮食品は、新鮮であることが求められかなりデリケートな食品です。具体的に青果(野菜・果実)・鮮魚・精肉を指し、青果・鮮魚・精肉のことを総じて生鮮三品と呼ばれることもあります。そしてその情報の透明性はかなり重要なものです。
しかし、生鮮食品においての食品表示の仕方や基本ルールはあまり知られていないのではないでしょうか?「食品表示のルールが複雑すぎる」「生鮮食品は食品表示の際、どう食品表示したらいいのかわからない」といった悩みがある方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、生鮮食品における食品表示の基本ルールを解説していきます。これで、生鮮食品の食品表示について理解することでより安心安全な生鮮食品を消費者に届けることができ、更に商品への信頼得ることができるでしょう。
現在の食品制度と基本ルール
まず、生鮮食品の食品表示で重要なポイントである2020年4月1日から新制度へ移行された食品表示法に触れていきます。 2020年3月までの食品表示制度は食品衛生法とJAS法と健康増進法の3つでした。 食品衛生法は衛生管理の観点や添加物やアレルギーに関する情報、JAS法では品質の観点から原材料名や原産地に関する情報、健康増進法はカロリーや栄養成分の割合の情報などを規定していました。 遺伝子組み換えについては食品衛生法とJAS法の両方で規定されてます。ですが、それぞれ目的が異なり表示のルールも別々に制定されていたので基準がとても複雑なものでした。
ということでこれまでの消費者基本法の基本理念をもとにバランスの取れた表示と事業者・消費者に分かりやすいようにまとめられたのが、2015年の食品表示法です。
生鮮食品を取り扱う際に、おさえるべき食品表示法
JAS法と食品衛生法で区分が違っていた食品は食品表示法でJAS法に区分されることが統一されました。
具体的には、生鮮食品扱いだった簡単な加工がなされた食品も加工食品として区分されることに変更されました。また、それまで名称・原材料名・添加物・消費期限だけの記載が必要だったのが、アレルギーと製造所在地も義務付けられました。
生鮮食品として扱われていたドライフルーツや干し椎茸なども加工食品となってしまい、乾燥納豆など生産者が収穫の一環として行う加工の場合、生鮮食品として扱われるように変更がありました。消費者が判断するには困難な部分もあります。
生鮮食品に必要な表示項目
生鮮食品に必要な表示項目を大まかに分けると、横断的義務表示と個別的表示の2つに区分されます。横断的義務表示とはすべてのものに対して、表示するべき事項です。
この他、必要に応じて消費期限・保存方法・使用方法・添加物などを表示します。個別的義務表示は横断的義務表示のほかに個別のルールに則った表示も必要になってきます。
横断的義務表示
横断的義務表示の主に表示する項目は以下の通りです。
- 名称
- 原産地
- 放射線照射に関する事項
- 特定保健用食品である旨
- 機能性表示食品である旨
- 遺伝子組換え農産物に関する事項
- 乳幼児規格適用商品である旨
- 内容量及び食品関連事業者の名称など(軽量法第13条1項に規定する特定商品であって密封されたもの)
個別的義務表示のあるもの
- 玄米及び精米
- シアン化合物を含む豆類
- あんず・おうとう・かんきつ類・キウイ・ざくろ・すもも・西洋なし・ネクタリン・パイナップル・バナナ・パパイヤ・ばれいしょ・びわ・マンゴー・マルメロ・もも・リンゴ
- 食肉(鳥獣の生肉に限る)
- 生乳、生山羊乳と生めん羊乳
- 鶏の殻付き卵
- 水産物
- 切り身またはむき身にした魚介類であって生食用のもの
- 冷凍食品のうち、切り身またはむき身にした魚介類を凍結させたもの
- ふぐの内臓を除去し、皮をはいだものならびに切り身にしたフグ・フグの精巣とフグの皮であって生食用のもの
- 切り身にしたフグ・フグの精巣およびフグの皮であって、生食用でないもの
- 生カキ
主な表示事項
名称
生鮮食品の名称とは農産物・畜産物・水産物の一般的な呼び名のことです。地域によって農産物や魚介類の呼び名が違う場合があります。その地域の呼び名が一般的であればそれを表示して問題ありません。
原産地
生鮮食品の原産地の表示は農産物・畜産物・水産物によって表示の仕方が違います。国産の場合、農産物は都道府県名、畜産物は国産、水産物は水域名または地域名を表示します。ただし、水産物の場合は漁獲した漁船の国籍により国産か輸入品か決定されます。
畜産物は飼育期間が一番長かった場所が原産地になります。
輸入した生鮮食品は原産国名を表示します。同じ生鮮食品でも原産地が違うものを混ぜあって販売するときは、その重量の割合から多い順に原産地を記載しなければいけません。
表示の仕方について
生鮮食品で絶対に表示しなければいけないものは、名称と原産地です。しかし、生鮮食品は陳列台や野菜や果物などを載せて販売するバラ売りと容器包装にいれて販売する2パターンがあります。
容器包装に入れて生鮮食品を販売する場合
この場合、消費者に最も見やすい箇所に表示ラベルなどを貼る必要があります。印刷文字は8ポイント以上の大きさの活字で表示します。消費期限・保存方法・使用方法・添加物を使用している場合はその内容を記載する必要があります。この他に、食肉に関して景品表示法に基づく公正競争規約のルールもあります。
計算法で定められている特定食品を容器包装で販売する場合、内容量と表記したものの本名と住所を記載する必要があります
バラ売りで生鮮食品を販売する場合
名称と原産地を表示した立て札などを食品の近くに掲示します。野菜などを段ボールに入れたまま販売するときもありますが、段ボールに名称と原産地を表示していれば表示の代わりとなります。
遺伝子組み換え農産物や放射能を照射したジャガイモはその内容を表示する必要があります。
防カビ剤や防ばい剤を使っている果実などはバラ売りであっても、陳列用容器、値札、あるいは商品名を表示した札などに表示します。
販売形態などによる表示事項の違い
一般生鮮食品を販売するとき、その販売形態等により、表示を必要としない事項があります。 容器包装の形態などで、当該包装に直接指示することが難しい場合、以下の箇所で容器包装への表示にかえることができます。
- 透明な容器包装に包装されてるなどで、必要な表示事項が外部から容易に確認できる場合、当該容器包装に内封されている表示書
- 容器包装に結び付けているなど、当該容器包装と一体となっている場合、当該容器包装に結び付けられた札、票せん、プレートなど
容器に入れられてない生鮮食品は、製品に近接した掲示やその他の見やすい場所に耐え札、ポップなどで表示します。表示する文字の色は、背景の色と対照的の色にしましょう。容器包装の表示の文字の大きさは8ポイント以上の統一の取れた文字にします。ただし、表示可能な面積がおおむね150㎠以下のものに表示する場合は、5.5ポイント以上の大きさの文字とします。
まとめ
いかがだったでしょうか。生鮮食品は、法律の変更などややこしい部分は存在します。しかし、ルールを理解ししっかり守ることで事業者は信頼を得ることができ消費者は、安心安全の生鮮食品を手に入れることができます。これらは双方にとって大切なポイントです。これであなたも安心安全の生鮮食品を消費者に届けることができますね。
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能