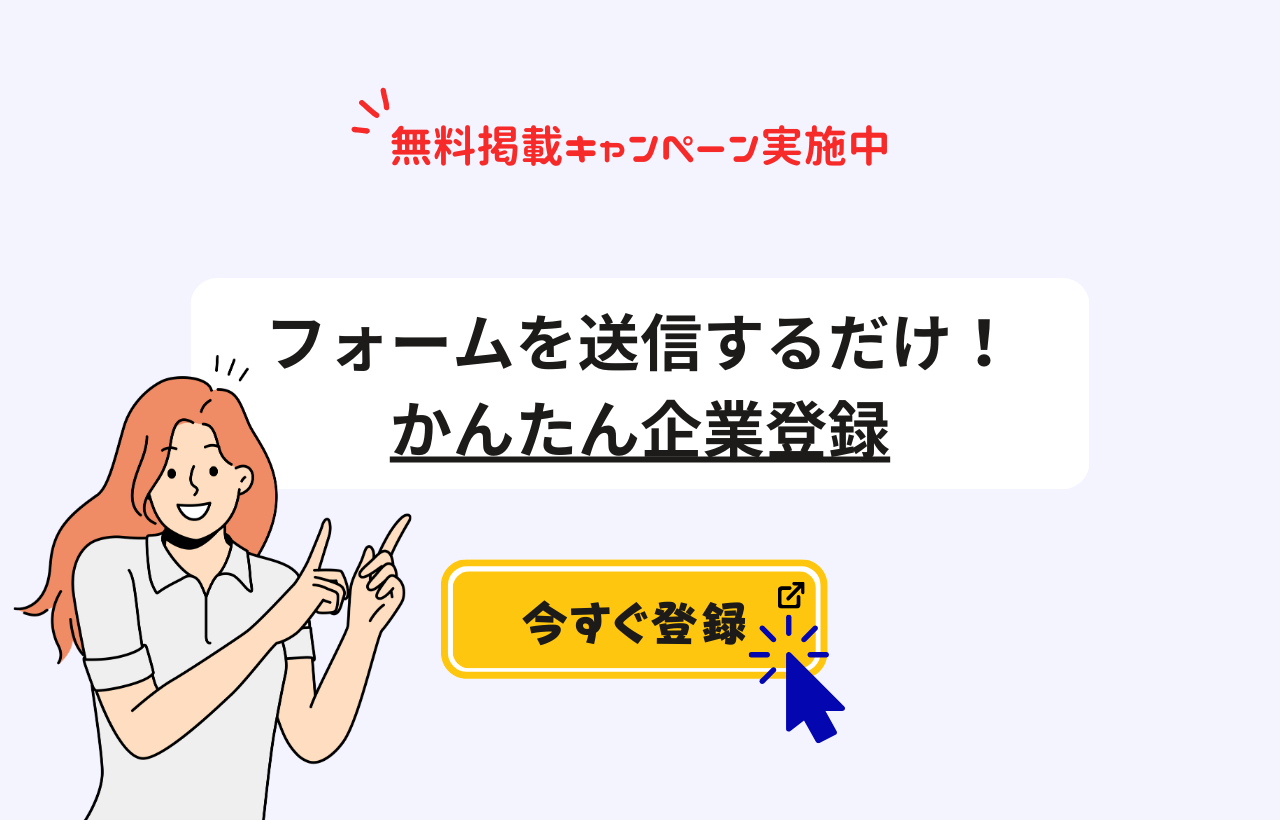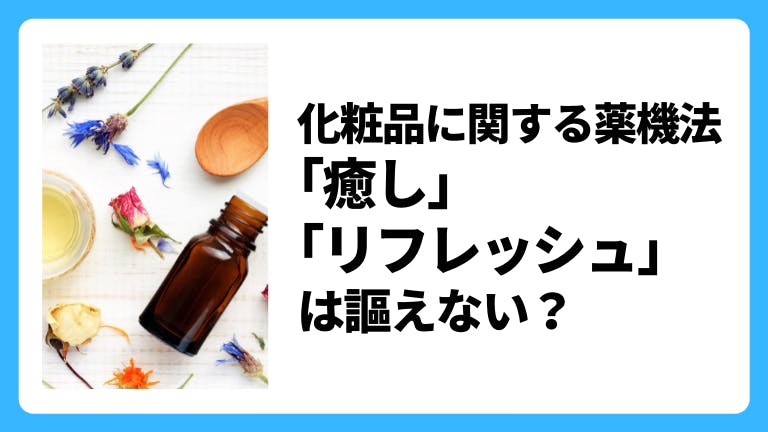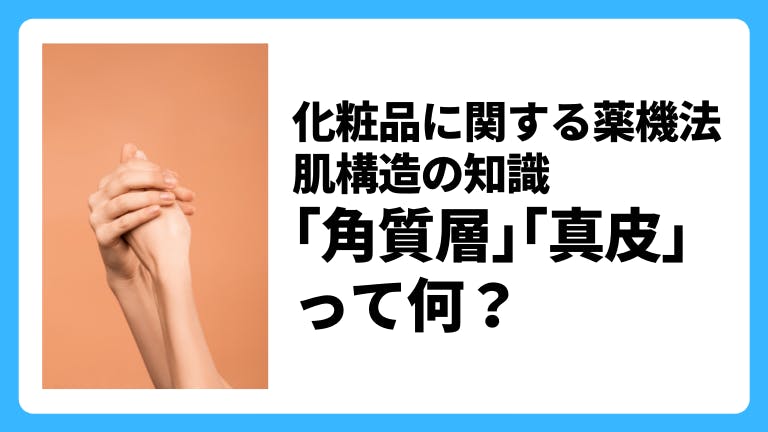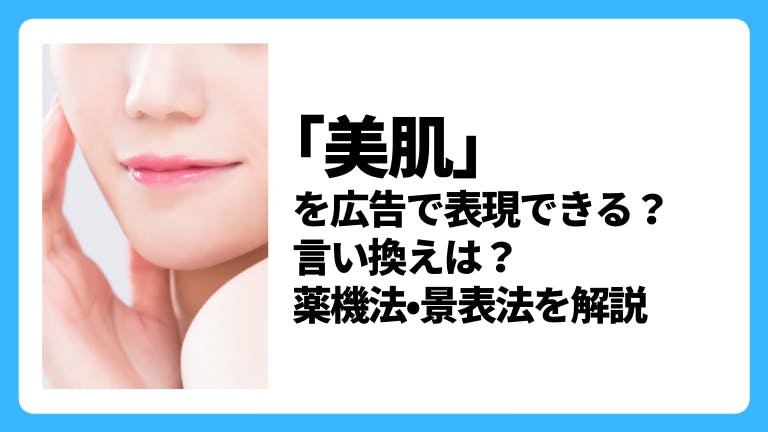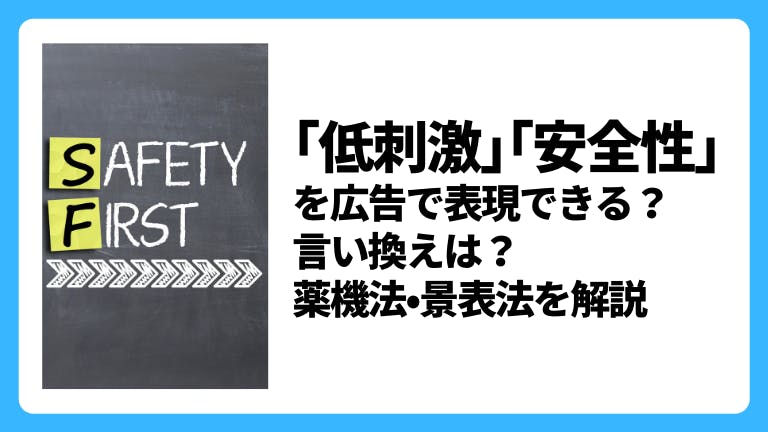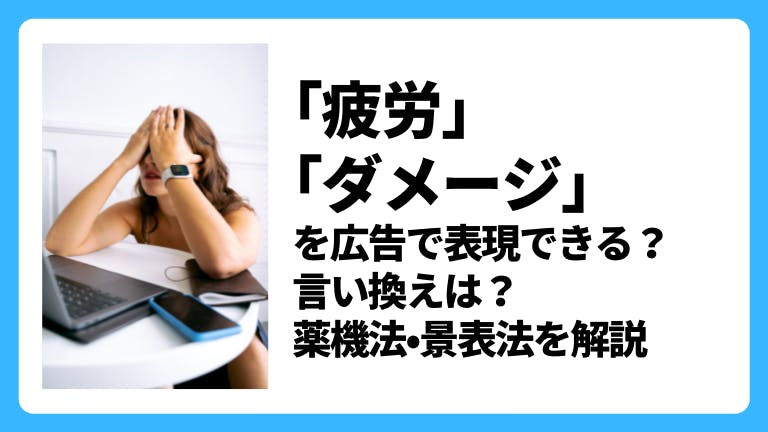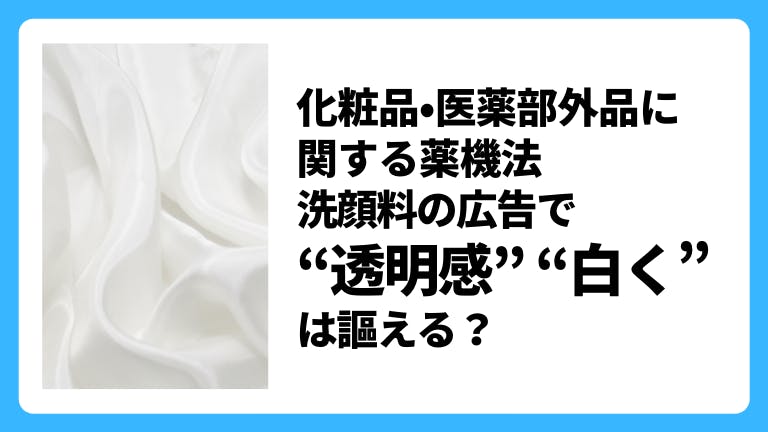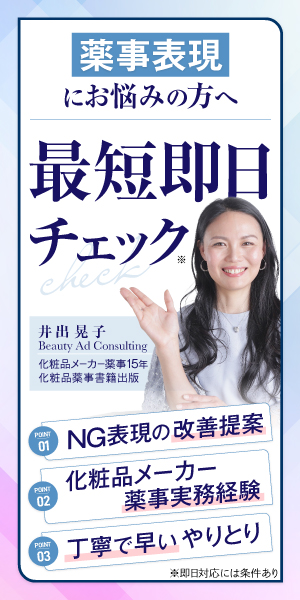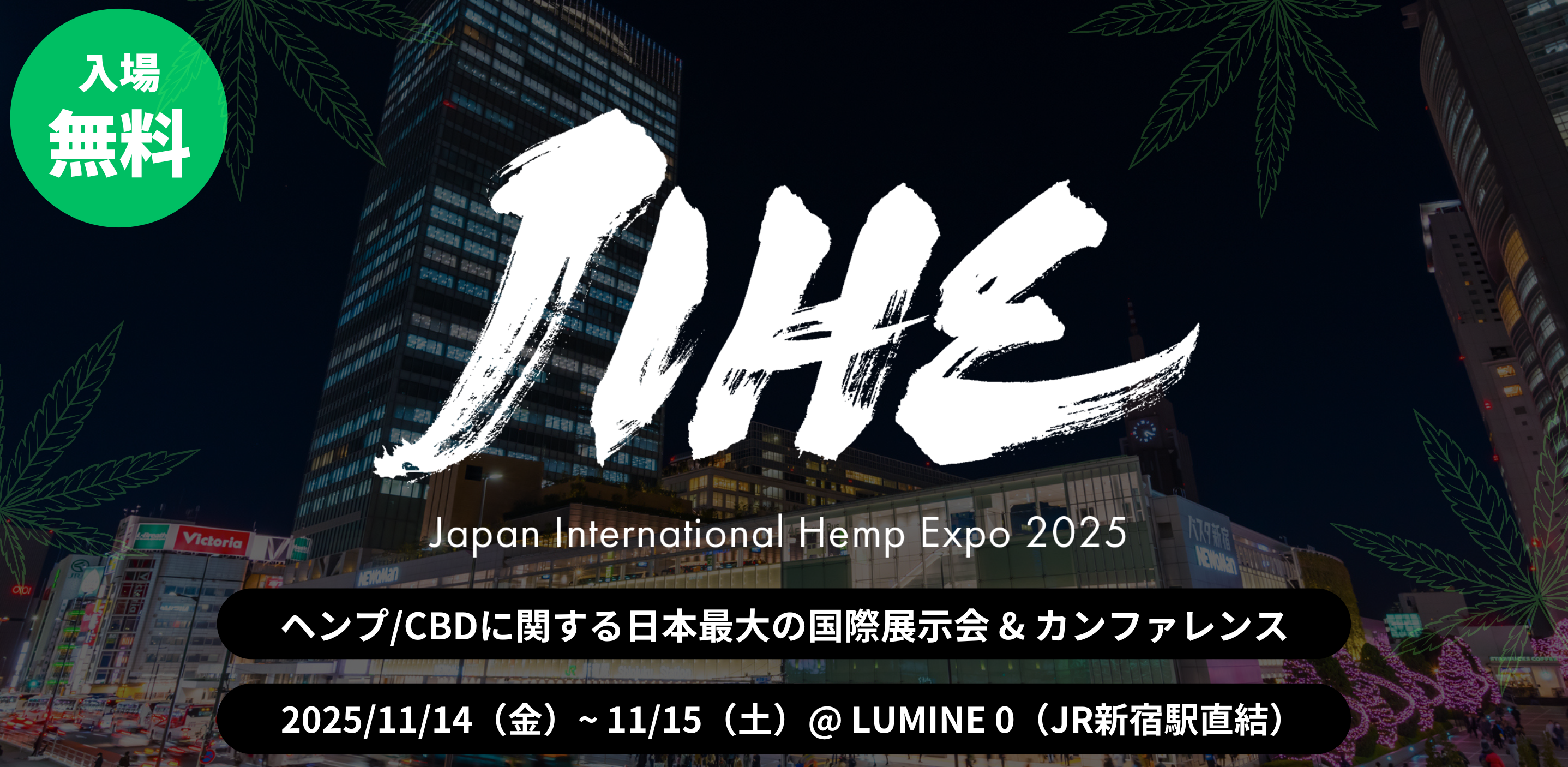
最終更新:2024/08/10
食品表示 アレルギー表示のルール

アレルギーの表示は食品を摂取する際、重要な役割を持っています。しかし、その表示が間違っていたら消費者の命を危険にさらしてしまうことがあります。「消費者に安心安全の食品を届けたい」と思われてる方は多いはずです。
そこで今回はアレルギー表示のルールを解説していきたいと思います。これで安心安全の食品を消費者に届けることができます。
アレルギーの特徴について
食物アレルギーは、ある特定の食べものを食べたり触れたりした後、アレルギー反応が見られる疾患のことを意味します。
食物アレルギーの原因となる物質であるアレルゲンは、主に食べ物に含まれるたんぱく質です。乳幼児時期には小麦や大豆、鶏卵、牛乳などで、学童期以降では甲殻類や果実、そば、魚類、ピーナッツなどのように加齢に伴って食物アレルギーの原因が変化していくという特徴があります。
乳幼児の5~10%、学童期以降では、1~3%が食物アレルギーと考えられています。子供のころの食物アレルギーは、多くが成長に伴い徐々に原因食物が食べられるようになります。これは耐性獲得と言われています。
一方、大人の食物アレルギーは、耐性獲得しにくく原因となる食品の継続的な除去が必要になることが多いと言われています。
症状について
食物アレルギーの症状は皮膚・呼吸器・消化器など様々な臓器にあらわれます。およそ90%に皮膚症状、およそ30%に呼吸器症状や粘膜症状が見られます。
主な症状
- 皮膚症状 かゆみ、じんましん、むくみ、発赤、湿疹
- 呼吸器症状 くしゃみ、鼻水、鼻づまり、咳、息苦しさ、ぜん鳴
- 粘膜症状 目の充血や腫れ、涙、かゆみなど、口の中や唇下の違和感、腫れなど
- 消化器症状 下痢、吐き気、嘔吐、血便など
- 神経症状 頭痛、元気がなくなる、意識がもうろうとする
これらの症状は、1つだけ現れる場合もあれば、急に複数の臓器に症状が現れることもあります。これをアナフィラキシーと言います。アナフィラキシー症状にさらに血圧低下や意識障害など、急激に全身の症状が進行する場合が「アナフィラキシーショック」です。生命の危険になることもあります。
特殊な食物アレルギー
食物依存性運動誘発性アナフィラキシー
ある特定の食べ物を食べた後、運動をしてアナフィラキシーの症状が出る病気です。特定の食べ物を食べただけでは症状は起きず、特定の食べ物を食べた後に運動をすると症状があらわれるという特徴があります。
ただし、特定の食べ物と運動の組み合わせが原因で生じます。また生活環境や体調、ストレスのなど、さまざまな要素が関わっていると考えられています。
食事をして30分~4時間後に運動すると、呼吸困難・めまい・吐き気・嘔吐・じんましんなどアナフィラキシーの症状が出始めます。
口腔アレルギー症候群
ある特定の果実や野菜などを食べると口の周囲に発赤や口腔内の腫れ、のどの痛みや違和感などが生じる病気です。症状が現れても、多くの場合食後しばらくすると自然軽快します。
この病気は果実や生野菜に含まれるアレルゲンが、口腔内粘膜に触れて起こる反応で、体内のIgE抗体が関係しています。症状を引き起こすアレルゲンは、植物が病原菌の感染や傷害、ストレスから身を守るための生体防御として誘導されるたんぱく質で、小腸に到達する前に壊れるので主に口腔内で反応が起きます。
容器包装された加工食品のみアレルギー物質の表示義務がある
箱・袋・缶・ビン・ペットボトルなど容器に詰められた(容器包装された)加工食品には一定量以上、常に含まれてるとき、食品表示法に則った表示をすることが定められています。
必ず表示されるアレルギー物質は7品目のみ
容器包装されている加工食品で表示が義務付けられているアレルギー物質は、卵・乳・小麦・エビ・カニ・落花生・そばの7品目だけです。(この7品目は特定原材料と言われてます)
また、イクラやオレンジなどの21品目(2019年に1品目追加されました)は、特定原材料に準ずるものとして表示されることが推奨されてます。ですが、この21品目には表示義務はありません。
特定原材料に準ずるもの21品目
アーモンド・アワビ・イカ・イクラ・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン
店頭での対面販売や外食料理にはアレルギーの表示義務がない
小売店で作った惣菜や弁当やパン、もしくは菓子などの包装されていない食品はアレルギー表示の義務がありません。
ですが最近アレルギーに関する表示をした食品を売る小売店や食物アレルギー対応食に力を注ぐファミリーレストランや遊園地の外食店などが増えてきてます。
食品表示においてアレルギー物質は統一されていない
例えば卵なら「玉子、エッグ」などというように、アレルギー物質の原材料名にいくつかの表記が許可されています。これを代替表記と言います。乳については、「バター・チーズ・アイスクリーム」など、「乳」という字ではない加工品名で記載されてる場合もあります。
原材料表示は詳しく表示
原材料表示の形には、個別表示と一括表示の二種類があります。原材料の加工食品に特定原材料など(アレルギー物質)が含まれているとき、その食品名のあとにカッコでその名称が表示されます。
表示スペースがない場合、一括表示でも大丈夫
個別の特別表示が原則とされていますが、表示スペースが狭いなどの場合、含まれる特定原材料等のアレルギー物質が表示欄の最後のカッコ内にまとめて表示されるので、最後のカッコ内をみればその食品に含まれるすべてのアレルギー物質が一目でわかります。ただし、どの食品にどのアレルギー物質が含まれているかわからないことが多いので、わかるようにするとよいでしょう。
アレルギー物質がわかりやすく表示されてる例
最近は、原材料表示とは別にその製品に含まれる特定原材料などが一目でわかる表示を併記した製品が増えています。しかしこの表示は義務付けられているものではありません。
注意喚起表示
原材料表示の欄外に、“本品製造工場では○○を含む製品を生産しています”などと書かれている場合があります。これは注意喚起と言います。特定原材料7品目には、容器包装された加工食品への表示義務があります。(加工食品中に特定原材料が数pmmを超える濃度でも含まれる場合は表示が必要になっています。)
しかし、原材料には使っていなくても、食品に製造工場で故意ではない混入(コンタミネーション)が生じる可能性を否定できないときがあります。このような場合、食品メーカーが注意喚起表示を行うケースがあります。
一般的には、注意喚起表示があったとしても、原材料表示の中に特定原材料が表示されてないことが確認でき、特定原材料の重篤な食物アレルギーでなければ、その食品は食べれます。
なお、この注意喚起表示については表示の義務がされてるわけではないので、注意喚起表示がないからと言ってその食品が特定原材料7品目と同じ製造工場内で作られていないと判断することはできません。
まとめ
いかがだったでしょう。アレルギーは時として人の命に関わることがあります。まだまだ、規制が曖昧なところもありますが、消費者の安全面を考慮したときアレルギー表示はしなくてはいけないものです。情報に透明性を持たせることが消費者にとっても事業者にとっても大切なことです。
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能