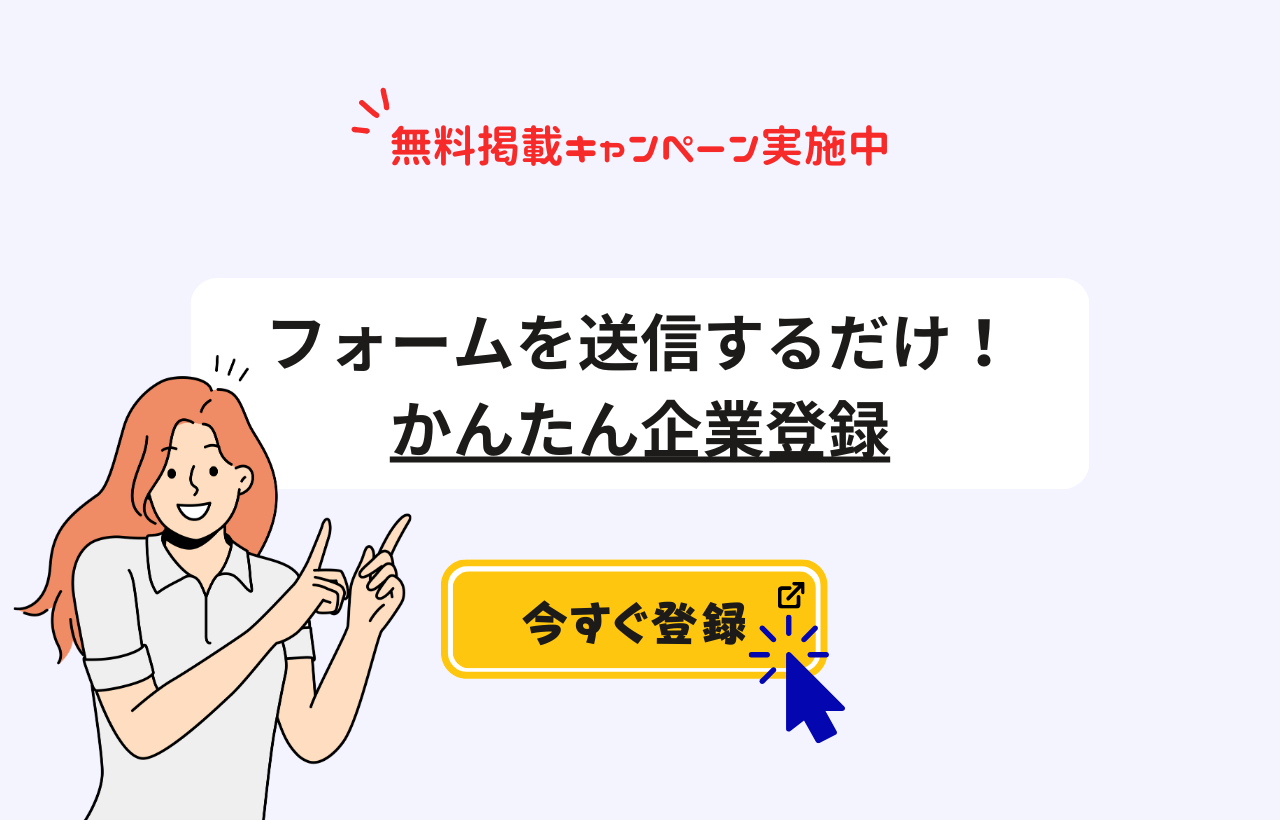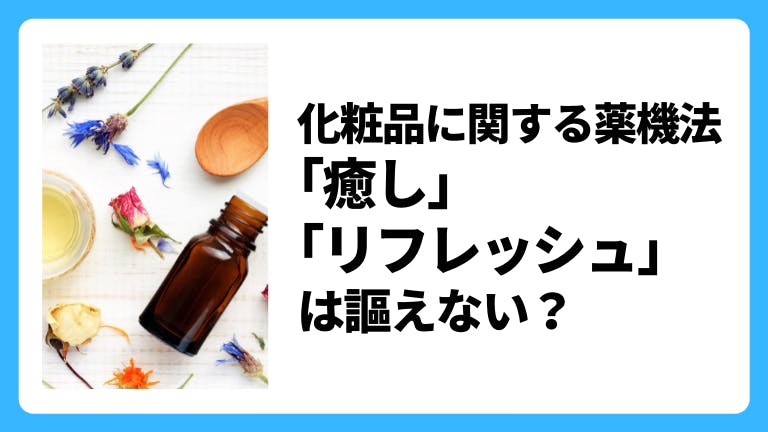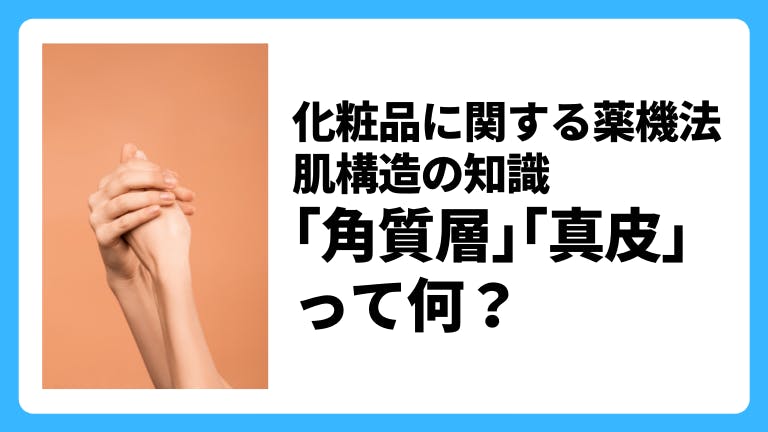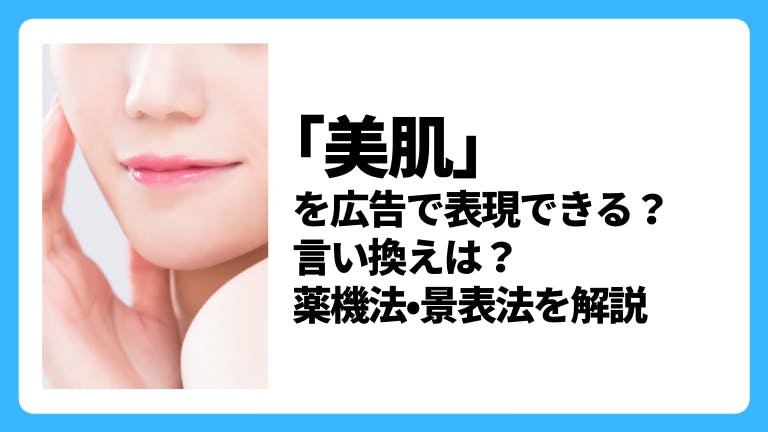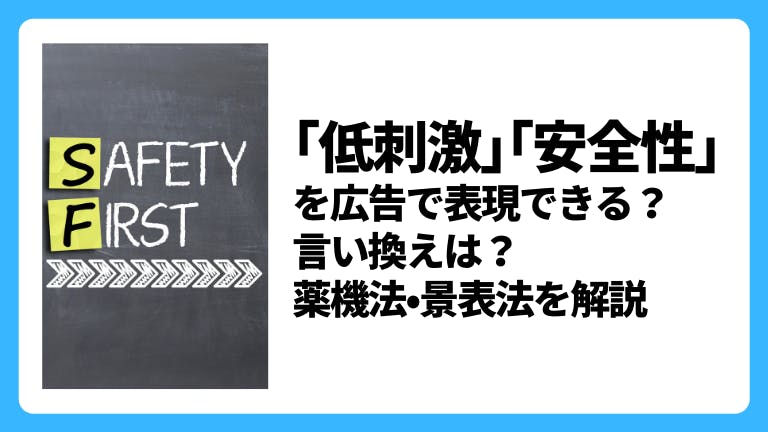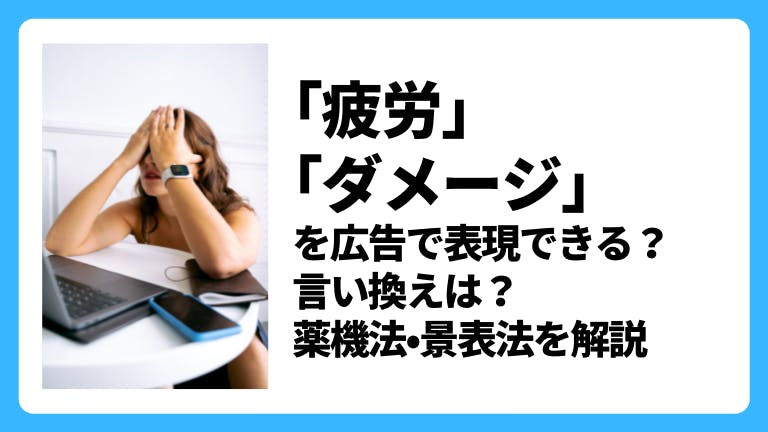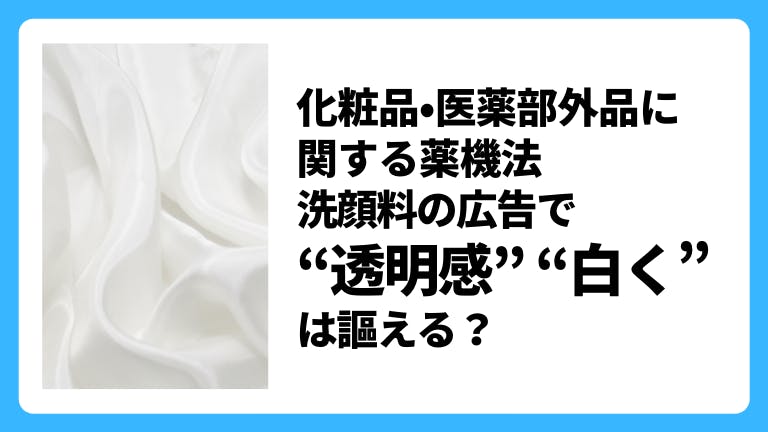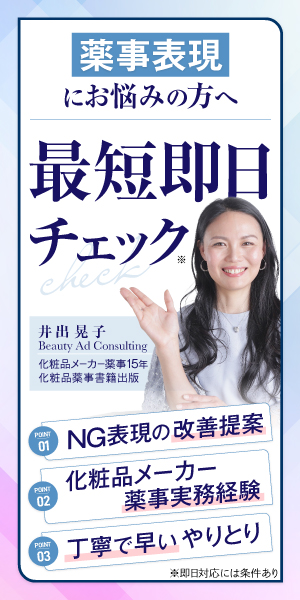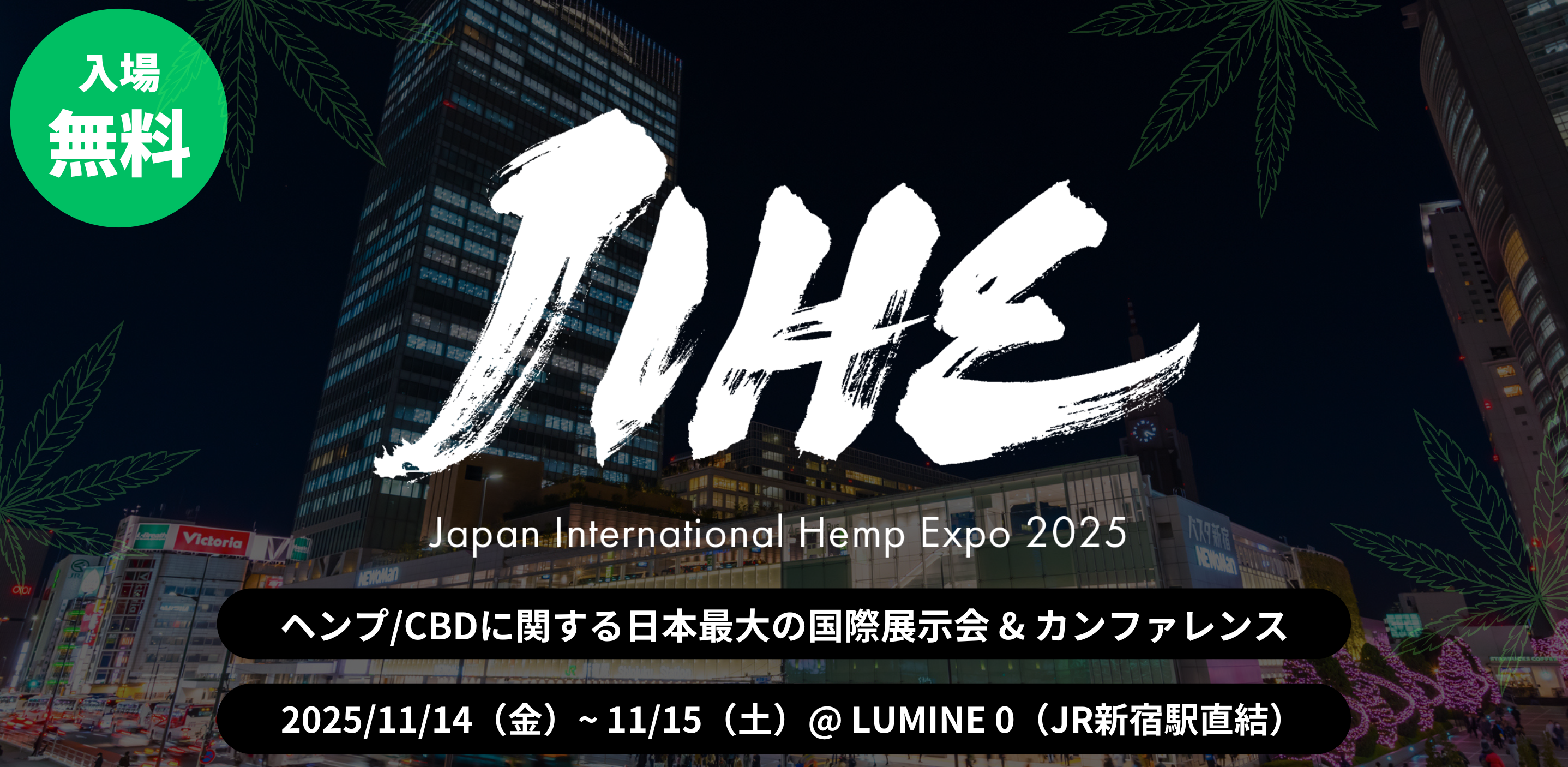
最終更新:2024/08/10
食品表示 添加物表示のルール
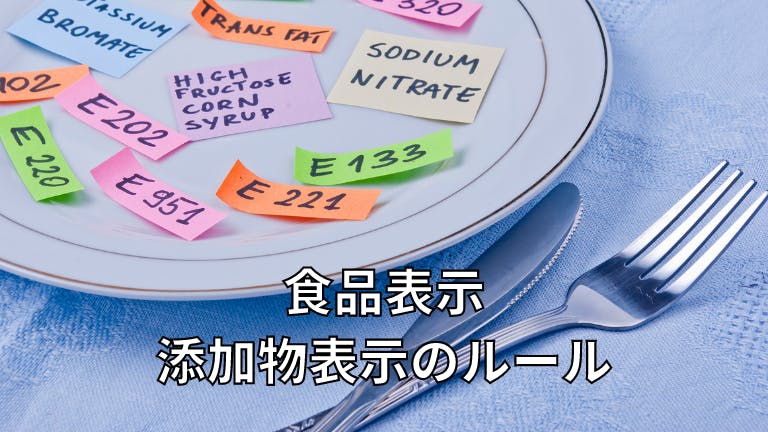
食品には欠かせない食品添加物の表示ルールについて解説します。
食品表示について
食品表示とは、
- 食品を食べる際の安全性確保
- 食品選択の大切な情報源
として、重要な役割を果たしています。 また、万が一事故が生じた場合には、その責任の追及や製品回収等の行政措置を迅速かつ的確に行うための手がかりになります。 食品表示を規定する法律には様々なものがあり、これらすべての法令に適合するように表示しなければなりません。
食品の表示ルールについて定めている、食品表示法が施行された経緯についてお話しします。 日本での食品表示は、1948年(昭和23年)から食品衛生法の施行とともにはじまりました。しかしその後、目的や経緯の異なるJAS法、健康増進法が施行されたのですが、その2法にも食品表示についての規定が加えられたこともあり、複数の法律で定められた食品表示ルールは非常に複雑でわかりにくいものとなっていました。 そのため、食品表示を事業者と消費者にとってより分かりやすいものとするため、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3法の食品表示についての規定を一元化した法律が、食品表示法となります。(具体的な表示事項や表示方法などについては食品表示基準(内閣府令)で定められています。) 食品表示法の目的は
- 食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会を確保する こと。
- 一般消費者の利益の増進を図り、国民の健康の保持・増進、食品の生産・流通の円滑化、 消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与すること。
としています。
また、食品表示法は2015年(平成27年)に施行され、2020年(令和2年)4月に完全移行しましたが、旧基準と新基準が混在する表示は、原則として認められていないため、注意が必要です。
食品添加物について
食品添加物は、食品衛生法第一章第4条2項において定義されています。
食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物
出典:食品衛生法
簡単にいうと、食品に添加することで「味をよくする」「保存期間を長くする」「色、香りを付ける」などの効果が得られる物質を指します。
ただ、なんでも添加物として使用が認められているわけではありません。 現在、日本で使用ができる添加物は、安全性と有効性を確認し厚生労働大臣からの認可を受けた「指定添加物」。または、日本で昔から広く使用されてきた「既存添加物」のほか、天然の物質で食品への香り付けを目的に使われる「天然香料」や、普通は食品として使用されている「一般飲食物添加物」のような、いわゆる天然添加物のみ使用が認められています。 また、添加物は食品衛生法上、前述した「指定添加物」「既存添加物」「天然香料」「一般飲食物添加物」の4つに分類されますが、今後新しく使われる添加物は、天然や合成を問わず、厚生労働大臣から指定を受けた「指定添加物」に分類されます。
食品添加物の表示ルール
添加物の表示ルールは食品表示法によって規定されており、その種類も様々です。 文字の大きさにも、規定があり原則8ポイント以上(表示可能面積が150㎠以下は、5.5ポイント以上)とされています。
食品添加物の表示順序ルール
基本的に、添加物は原材料のあとに記載します。 また、表示順序は、添加物の重量割合の高いものから順に表示します。 (原材料の表示も同様に、原材料の重量割合の高いものから順に表示します。) そして、食品表示法の施行に伴い、原材料と添加物は、明確に区分して表示することが義務付けられましたので注意が必要です。
主要な表示例として、3つ紹介します。
(1)「原材料名」の項目に、原材料と添加物を記号「/」で区分して表示 (2)「原材料名」の項目に、原材料と添加物を改行して表示 (3)「原材料名」の項目に、原材料と添加物を別欄に表示
食品添加物の表示名ルール
原則、添加物は物質名で記載しますが、別途以下に示すような規定が定められています。
品名、簡略名、類別名での表示が認められている
添加物は原則として、物質名で表示されます。 ただ、他によく知られた名称を持つ添加物の場合、物質名で記載されると逆に分かりづらくなるため、品名(名称、別名)、簡略名、類別名での表示が認められています。 例をあげると、「硫酸アルミニウムカリウム」なら「ビタミンC」のように表示されます。
用途名を併記する
甘味料・着色料・保存料・増粘剤・安定剤・ゲル化剤又は糊料・酸化防止剤 ・発色剤 ・漂白剤 ・防かび剤又は防ばい剤など8用途に使用されるものは名称と用途名の併記が必要です。消費者が商品を選択するうえで必要な情報だと考えられているためです。 例えば、甘味料(スクラロース)のように記載されます。
一括名で表示できる
イーストフード・ガムベース・かんすい・酵素・光沢剤・香料・酸味料・チューインガム軟化剤・調味料・豆腐用凝固剤・苦味料・乳化剤・水素イオン濃度調整剤・膨張剤の14用途に使用される添加物は一括名で表示できます。 これらは、複数を組み合わせることではじめて役割を発揮できることが多く、各々の成分を表示するメリットが低い添加物であること。また、食品にも通常使用される成分であることから一括名で表示しても表示の目的を果たせているとして一括表示が認められています。
表示が免除される場合
前述したように、添加物は食品表示法により「原則としてすべての食品添加物を物質名で食品に表示する」と定められていますが、それには例外もあります。 キャリーオーバー、加工助剤、または栄養強化の目的で使用される添加物などについては、添加物の表示が免除されます。 (ただし、アレルギー物質に関連する特定原材料から由来する添加物は、表示が免除できないため注意が必要です。)
- キャリーオーバー 原材料に含まれるものの、食品にわずかしか残らず効果を発揮できない物質です。
- 加工助剤 単にいうと、加工工程に使用されますが、除去されたりして、ほとんど残らない物質です。
- 栄養強化 栄養を強化する目的で使用されるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類の添加物です。 食品によく含まれている成分のため、添加物とみなしていない国も多いことから免除されます。
- そのほか 店頭でのばら売りされる食品も表示免除の対象となります。しかし、防かび剤又は防ばい剤として、アゾキシストロビン、イマザリルなどを使用した食品や甘味料のサッカリンなどを使用した食品は、売り場等に添加物の物質名及び用途名を使用した旨を表示する必要があります。 また、旧法では免除されていた、表示可能面積が30㎠以下の場合も、食品表示法の施行に伴い、保存方法、消費期限または賞味期限、アレルゲン、L-フェニルアラニン化合物を含む旨の記載が必要となりました。
まとめ
本記事では、添加物の表示について、法律からその表示ルールについて、ご紹介させていただきました。 食品表示は消費者との信頼を築くための大切な橋渡しとなります。 ぜひ、食品表示づくりの参考にご活用くださいね。
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能