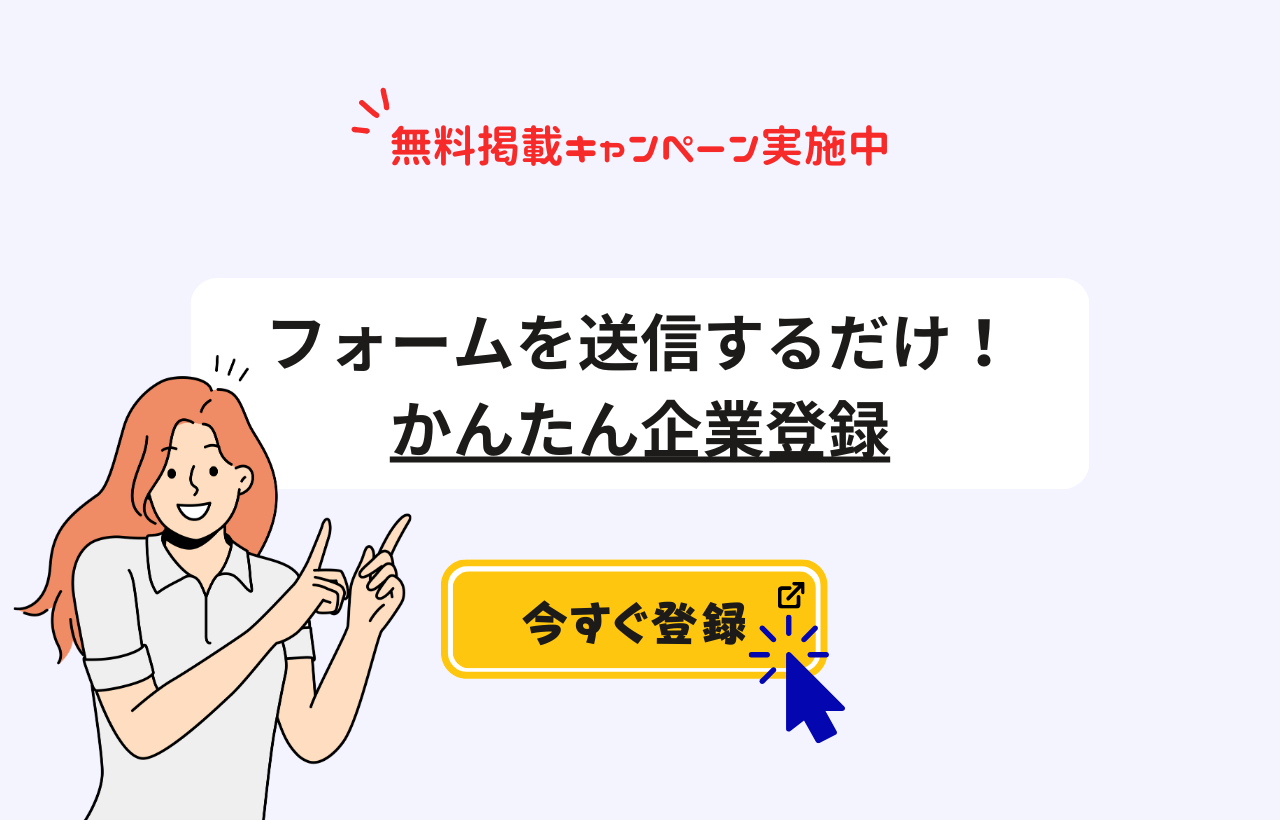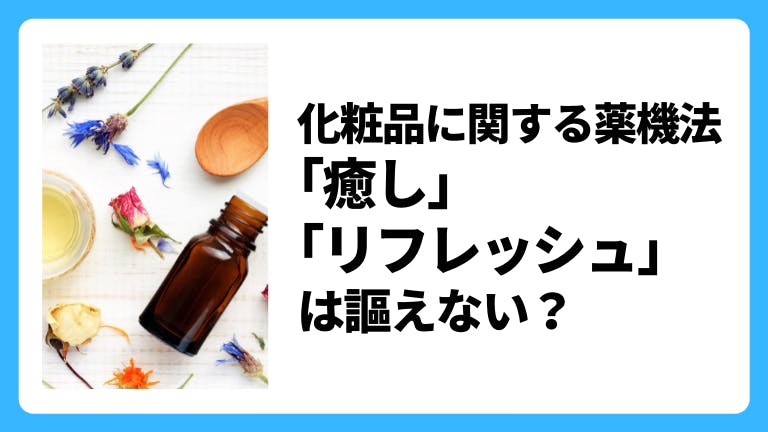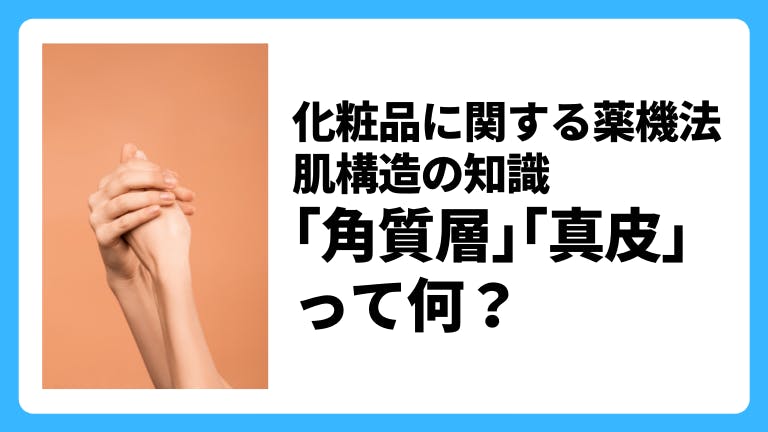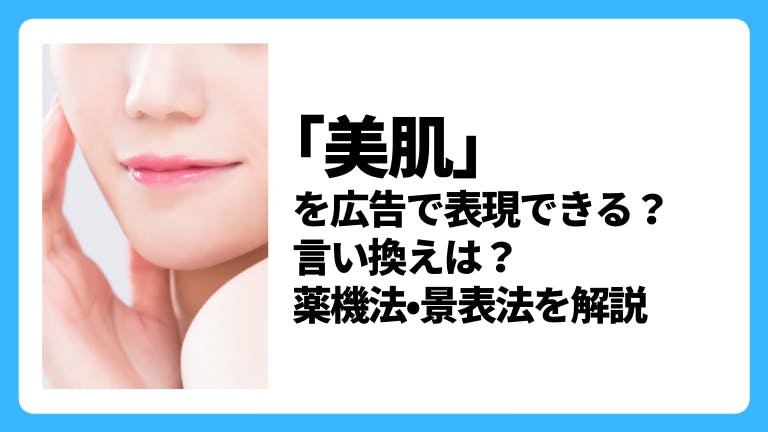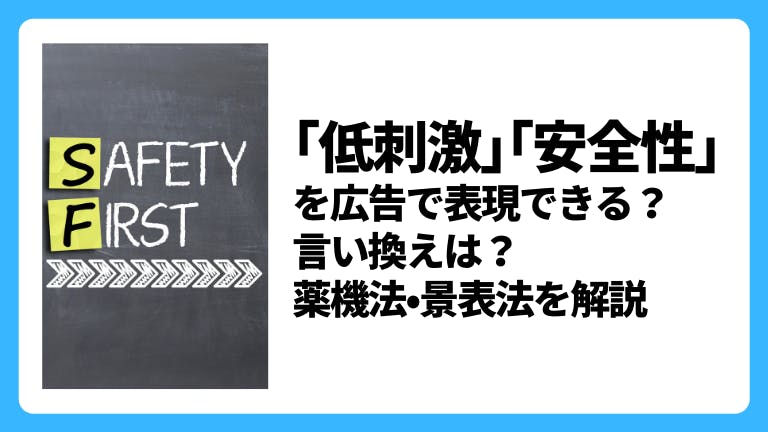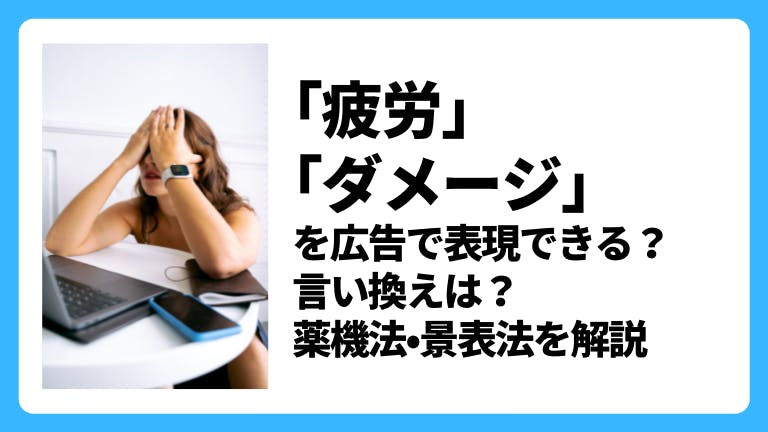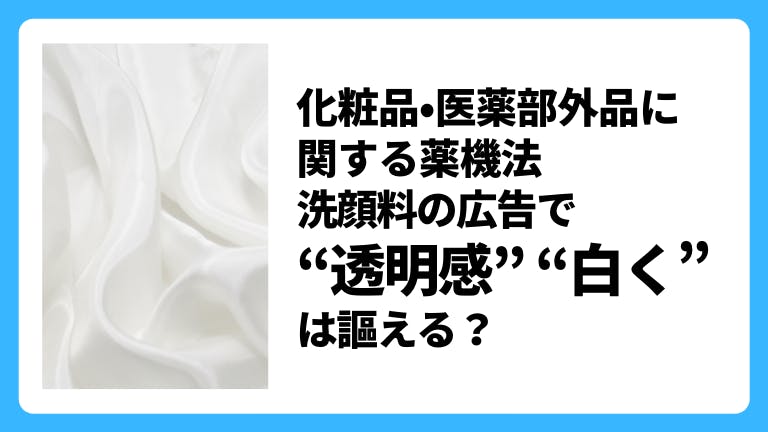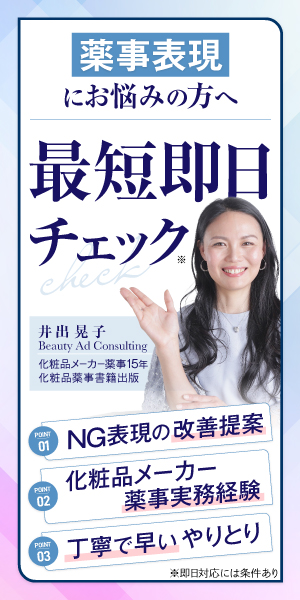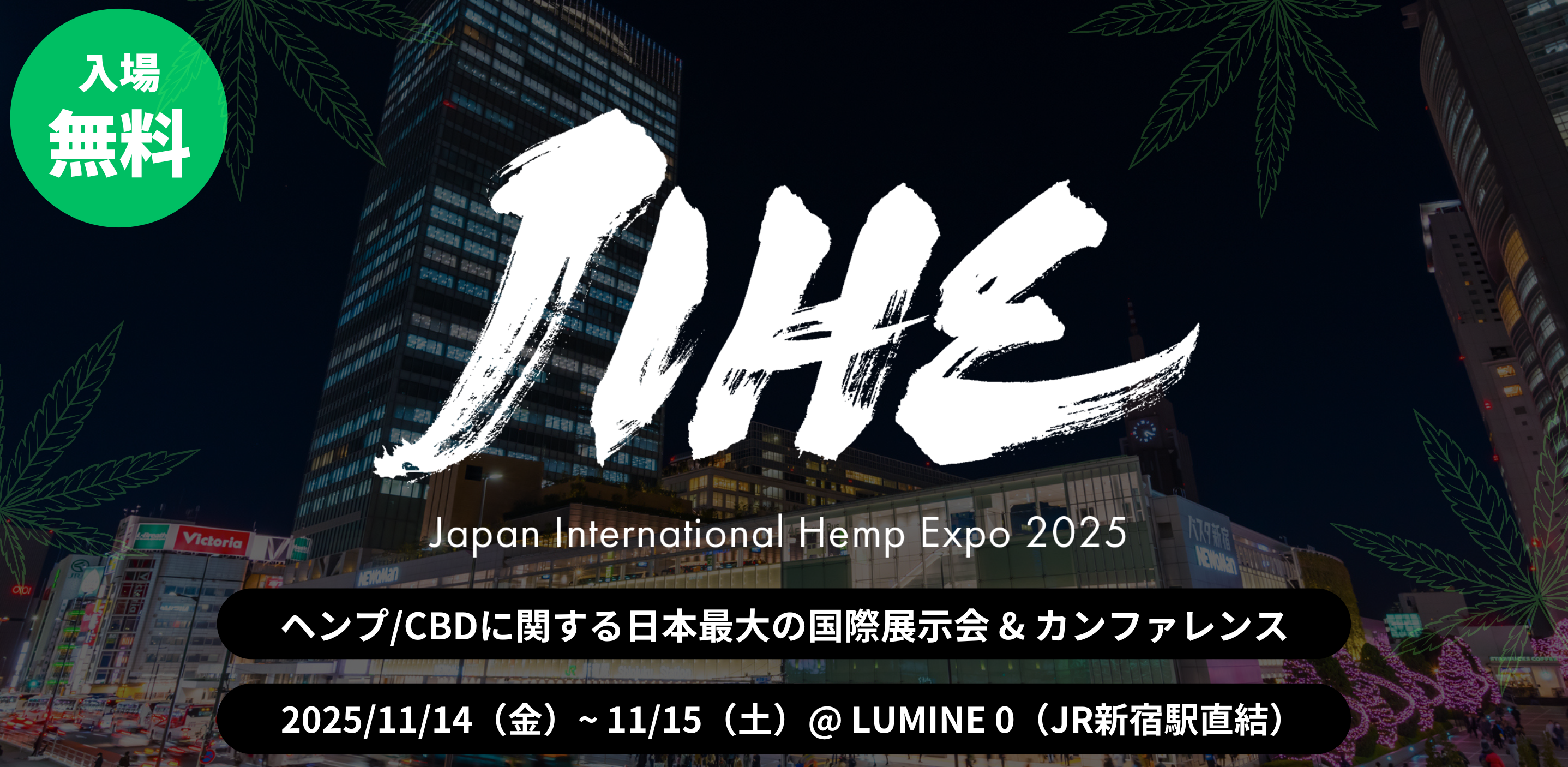
最終更新:2024/08/09
食品表示とは?概要や考え方を解説
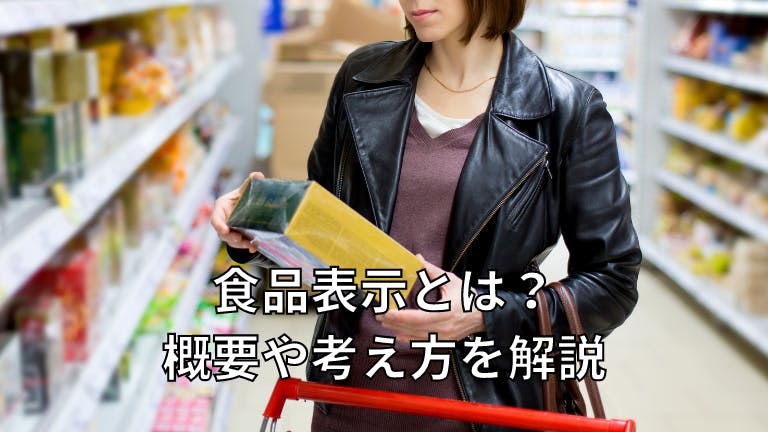
皆さんが毎日手にしてる加工食品のほとんどがパッケージングされています。 そして、どんな食品であるか、原料には何が使用されているか、製造・販売者は誰かなどが表示されています。 食品についているラベルは、食品表示法という法律で定められています。 では、その内容について今回解説していきます。
食品表示法とは
食品表示法は、元々食品衛生法、JAS法(旧:農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の3つの法律の食品の表示にかかる規定を一元化した法律です。 交付は平成25年であり、事業者のみならず消費者にも分かりやすい表示を目指して、「食品表示基準」を設けられました。 「食品表示基準」は、複雑な食品表示を具体的な表示ルールを決めて、事業者は表示の作成に戸惑わないように、消費者はその見方が理解しやすいように策定されました。施行は平成27年4月1日です。 食品表示法の構成は、品質事項・衛生事項・保健事項で構成されています。
品質事項は、JAS法で定められた食品の品質に関する表示の適正化を図るために必要な食品に関する表示事項です。 関連する項目は、原材料名、原料原産地名、内容量、原産地、原産国名、食品関連事業者名、名称、遺伝子組み換えです。
衛生事項は、食品衛生法で定められていた、国民の健康の保護を図るために必要な食品に関する表示事項を指します。 関連する項目は、添加物、賞味・消費期限、保存方法、アレルゲン、製造所です。
そして保健事項は、健康増進法で定められていた、国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示事項を指します。 関連する項目は、栄養成分表示、機能性表示食品です。
では、食品表示法がなぜ必要だったのでしょうか?
食品表示法が必要だった理由とその目的
食品表示法の目的は、「食品を摂取する際の安全性」と「一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保」が挙げられています。 例えば、以前はアレルゲン表示の表示の義務は有りませんでした。 しかし、アレルギー症状のお子さんを持つ方なら理解出来ると思いますが、アレルギー症状により時として死亡事故につながる場合があります。 この一つを見ても、「食品を摂取する際の安全性」を確保するための法律と言えます。 また原産地表示は、その商品の価値を保証する目的で表示されることがあります。 例えば「魚沼産こしひかり」「羅臼産昆布」「国産イチゴ」など高級なイメージを思わせる原材料を使用して、高級な商品を好む消費者にアピールします。 しかし、原産地に虚偽の表示があった場合は、消費者庁から措置命令が発行されますが、それ以上に事業者の信用が失われます。 食品表示には、保存方法の記載があります。 これは、食品が適切に保管される条件が記載されています。 これも、消費者が食品を摂取する際の安全性を確保する為の表示となります。 冷蔵保管の商品を、炎天下に長時間置かれた場合、賞味期限を待たずに品質劣化を起こす以上に、細菌の増殖により食中毒を引き起こす場合もあります。
上の事例はほんの一部ですが、食品表示の重要性が分かっていただけたでしょうか。
食品表示法の歴史
上記では食品表示法の目的についてお話ししましたが、その歴史について語ったほうが、よりご理解されると思います。 昭和23年 食品衛生法が制定されました。 その時の表示内容については、「名称」「添加物」「製造年月日」「保存方法」「製造者等」でした。 しばらくして、事件が起こります。 昭和35年 「にせ牛かん事件」です。 製造業者が牛肉と偽って鯨肉を使用した点と、製造業者が缶詰製造業の許可を受けずに製造していた点が問題でした。 さらに問題だったのが、当時の缶詰業界では牛肉缶詰に馬肉を使用することがなかば商習慣となっていたのです。
この事が知れ渡り社会問題となりました。 これがきっかけで、昭和36年1月、標示を規定した「畜肉味付かん詰の日本農林規格」及び「畜肉野菜煮かん詰の日本農林規格」を制定されました。 また食品添加物の安全性について問題になった事があります。 昭和32年 人工甘味料、合成着色料、合成保存料等が添加物名と用途名の表示を義務化したことがきっかけとなり、時代が進むにつれて表示する添加物が増えていきます。 流れが大きく変わったのは、アレルギー物質による健康被害が世間に知られてからです。 平成13年 構成労働省令改正により、アレルギー物質で特に重篤な症状を発する5品目を表示義務化にします。 そして以後は表示する品目が増えていきました。 期限表示については、当初製造年月日表示でした。 いつまで食べられるかという事が明確ではありませんでした。 さらにお店での販売時に、消費者がより新しいものを購入する事で、返品や廃棄が増大しました。 このため、平成6年に、製造年月日表示を廃止し、消費期限・賞味期限表示を義務付けられました。
近年、登場したのが「遺伝子組換え表示」です。 遺伝子組み換え技術が実用化されたのはつい最近なので、当然新しく追加されたものです。
平成8年 遺伝子組換え食品が輸入開始となりました。 これは、食品の高品位塚や生産性の向上を目的として遺伝子の組換え技術により、食品のDNAを組み替えたものです。 世間では、消費者の安全性への不安が高まり、知らないうちに摂取する事態を危険視していました。
そこで農林水産省と厚生労働省が部会を開き、意見を集約しました。 平成12年に農林水産省が「遺伝子組換え食品に関する品質表示基準制定」を、平成13年に厚生労働省が「厚生労働省令改正」を行いました。
そして、安全性審査を経た遺伝子組換え食品の表示を順次増やしています。
栄養表示については、時代が古く昭和27年 栄養改善法施行から始まります。 当時終戦を迎えまだ日も浅く、国民の食生活も栄養が不足していました。 そこで、特殊栄養食品制度を創設、食品にビタミン・ミネラルを強化するよう勧告、栄養改善法を制定し、特殊栄養食品制度として、勧告に基づく強化食品を規定しました。 昭和48年 「特別の用途に適する旨の表示」に病身者食品の規格基準が定められました。 背景として、疾病予防や治療に関心が高くなり始めた時代に、そのような特殊用途食品の規格作りが求められたことにあります。時代は「飽食」の時代になっていました。
その後、平成3年 特定保健用食品、いわゆる「特保」の創設となります。 機能性食品の開発により、健康づくりをうたい文句にした商品が出始めますが、これまで科学的な評価を受けることなく販売されている事から制度化しています。
それから制度を見直し統合が図られ、平成21年 特別用途食品制度が改定されました。
このように時代によって、消費者の問題意識や世間のニーズにより食品表示は目まぐるしく改定しています。
まとめ
普段から食品を購入していない方はおられないと思いますが、食品表示まではあまり見ていないのではないかと思います。 上の記事では、触れませんでしたが清涼飲料水に含まれる砂糖の量についてよく話題に上がります。 食品表示の見方が分かれば、清涼飲料水の飲みすぎがどれだけ危険かわかるはずです。 自分自身の健康を守るためにも、食品表示の見方を学ぶ事をお勧めいたします。
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能