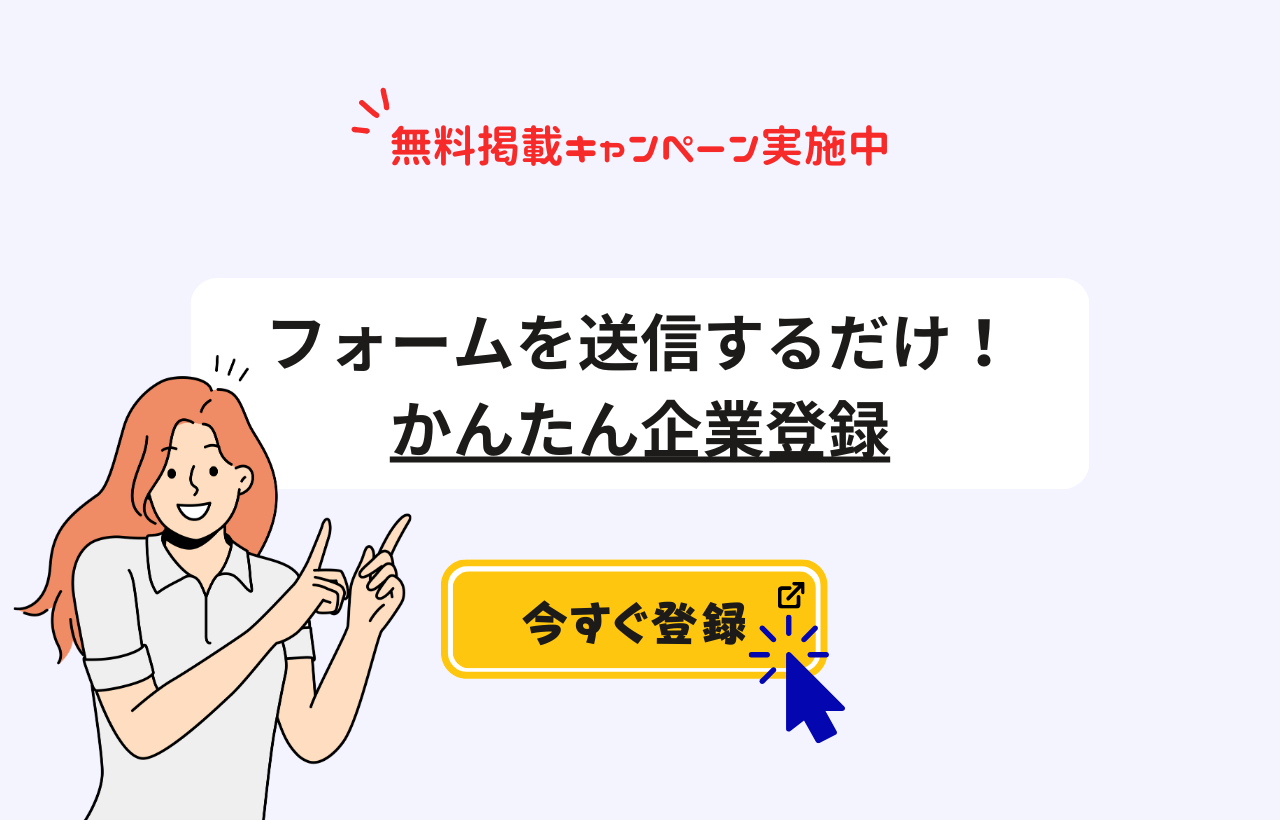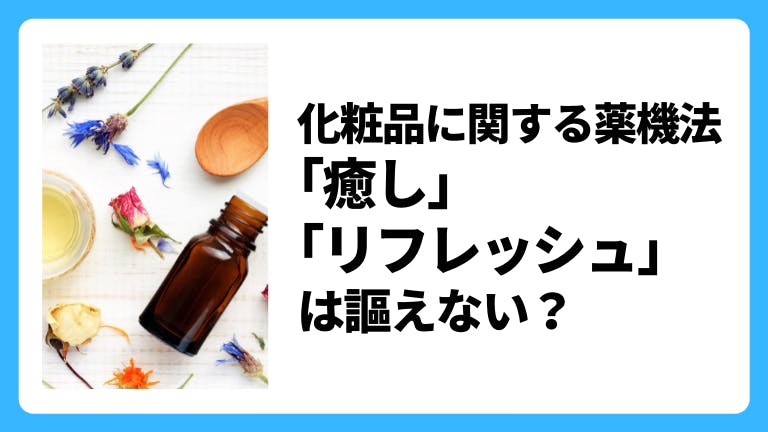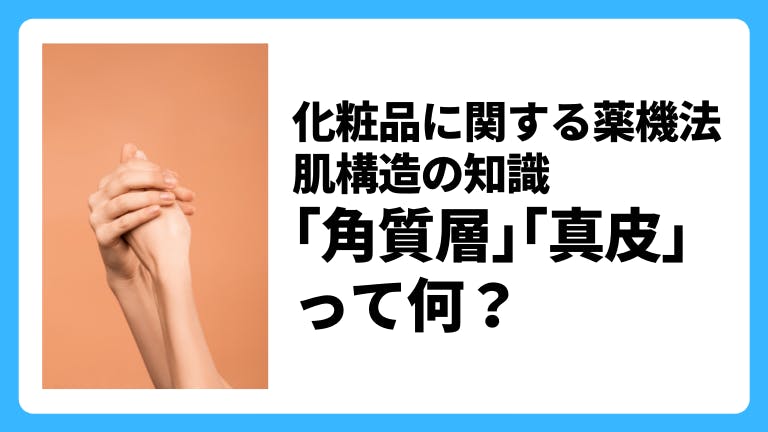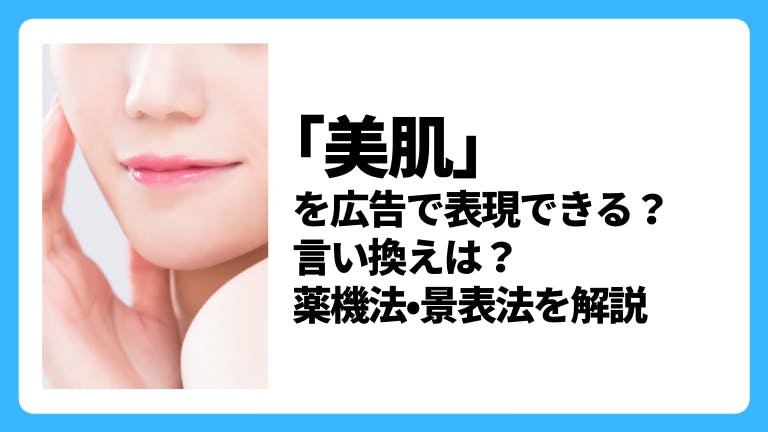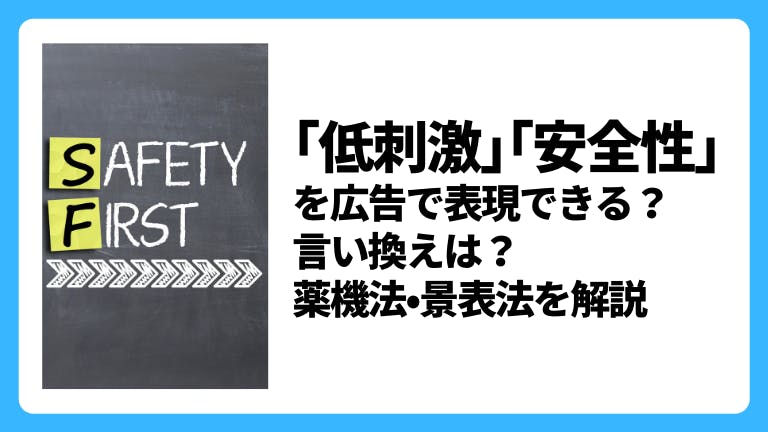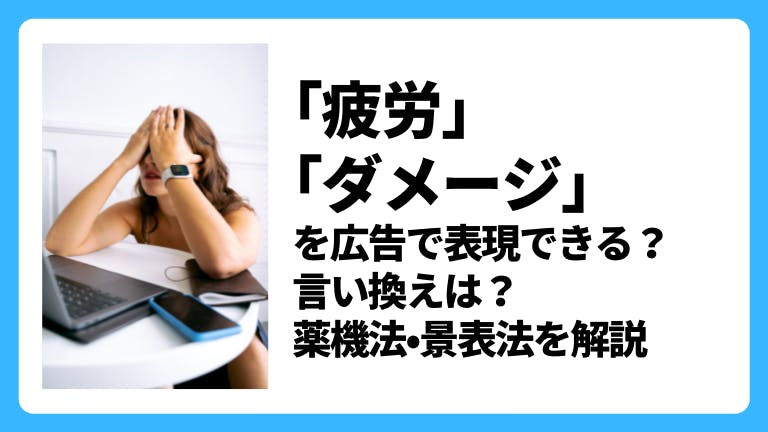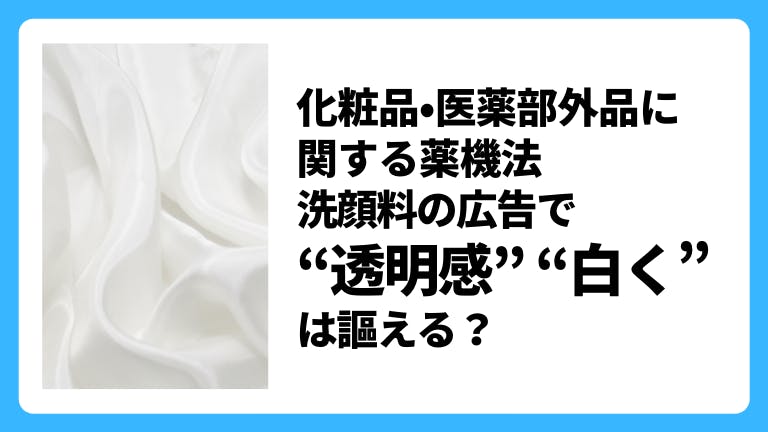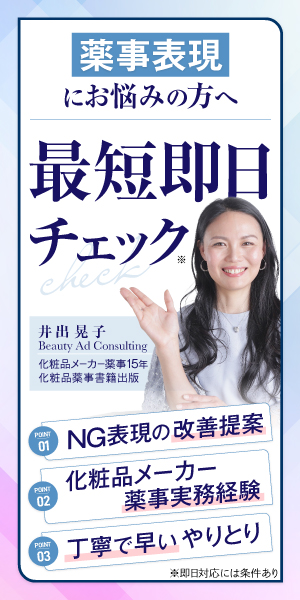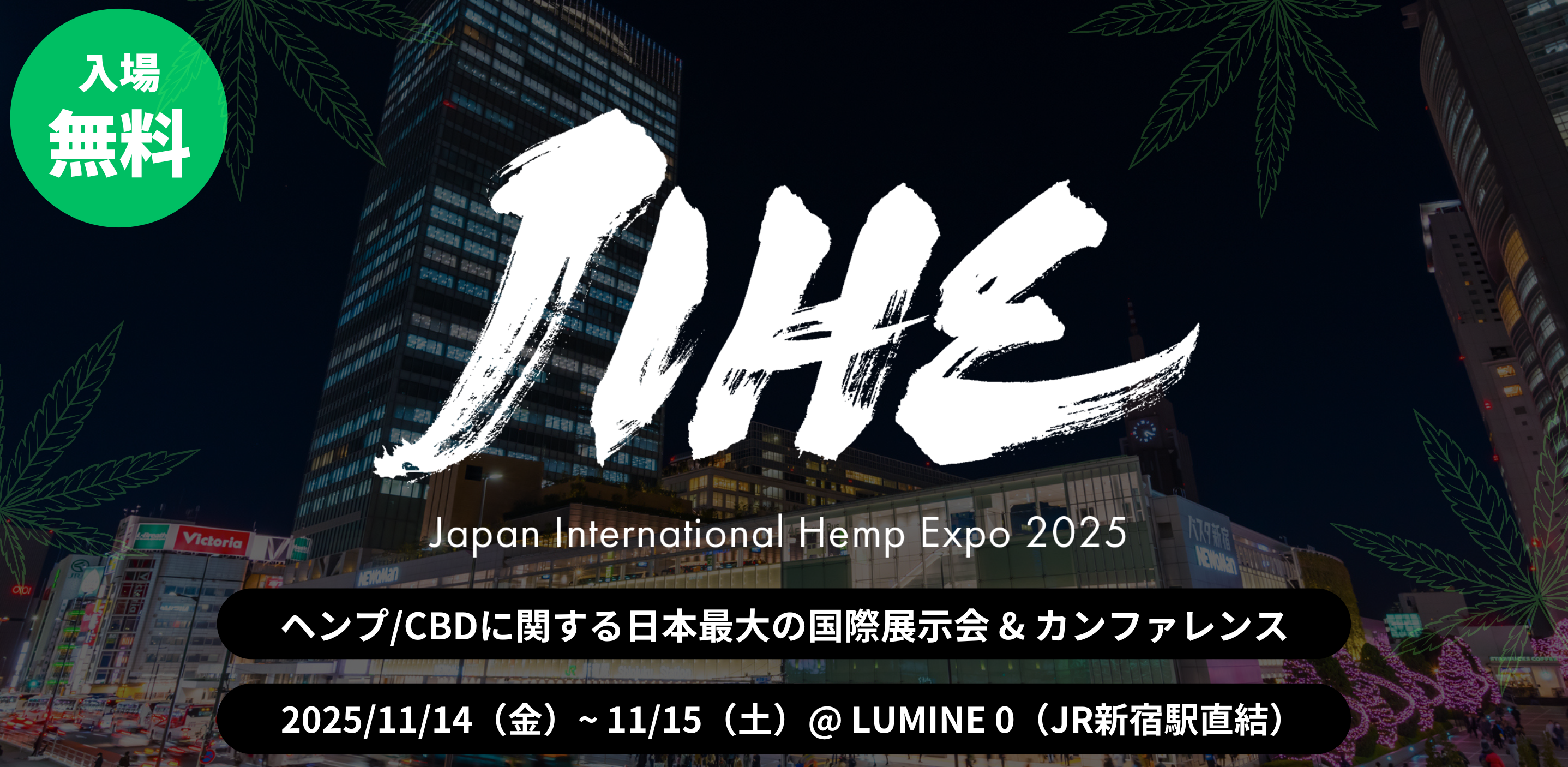
最終更新:2024/07/04
化粧品会社の社員がSNS・YouTubeで情報発信するときの注意点

SNSやYouTubeはインフルエンサーの商品レビューの場とされていましたが、最近では化粧品会社の社員が自社や他社の製品の情報を発信することも多くなっています。
ただ、会社の知らないところで社員が他社の批判や自社と他社の比較について発信してしまうといったトラブルも起きているため、SNSやYouTubeの運用には注意が必要です。
本記事では、化粧品会社の社員が、SNSやYouTubeで自社または他社製品の紹介をする際の注意点についてご紹介します。化粧品メーカーや化粧品の広告会社に勤めている方は薬機法違反にあたる表現には十分注意しましょう。
SNS・YouTubeで個人が発信しやすい現代
SNSやYouTubeで化粧品のレビューやおすすめなどの投稿を行う人は年々増加しています。近年では、化粧品会社の社員が会社や個人のアカウントで自社の情報を発信するといった宣伝戦略を行うことも増えてきました。
しかし、化粧品会社の社員がSNSやYouTubeで薬機法に抵触する表現などの不適切な内容を投稿してトラブルとなった事例も報告されています。
他社への誹謗中傷は薬機法違反
化粧品の場合、他社や他社製品への誹謗中傷は薬機法によって禁止されています。
他社の製品の誹謗広告の制限 医薬品等の品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。 (1)誹謗広告について 本項に抵触する表現例としては、次のようなものがある。 1他社の製品の品質等について実際のものより悪く表現する場合 例:「他社の口紅は流行おくれのものばかりである。」 2他社の製品の内容について事実を表現した場合 例:「どこでもまだ××式製造方法です。」
また、「他社製品にはない○○」など他社製品と比べて自社製品が優れているといった内容も他社製品の誹謗・効果や安全性の保証として薬機法に抵触するため注意が必要です。
(2)「比較広告」について1 漠然と比較する場合であっても、本基準第4の3(5)「効能効果等又 は安全性を保証する表現の禁止」に抵触するおそれがあるため注意する こと。
2 製品同士の比較広告を行う場合は、自社製品の範囲で、その対照製品 の名称を明示する場合に限定し、明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと。この場合でも説明不足にならないよう十分に注意すること。
(医薬品等適正広告基準より引用)
該当する表現例としては、次のようなものがある。
1 他社の製品の品質等について実際のものより悪く表現する場合
例 : 「他社の口紅は流行おくれのものばかりである。」
2 他社のものの内容について事実を表現した場合
例 : 「他社の製品はまだ×××を配合しています。」
例 : 「一般の洗顔料では落としきれなかったメイクまで。」
〔注意〕 他社の製品や既存カテゴリー等を比較の対象に広告を行うと、他社ひぼうにつながり易いので注意すること。
(「化粧品適正広告ガイドライン」より引用)
自社製品が他社よりも良い物であるように消費者に誤解させる内容は投稿しないよう気を付けましょう。
広告と感想の違い
化粧品会社の社員が化粧品について発信することは、一般の消費者に対する影響力が大きいと考えられることから「広告」と判断されます。逆に、影響力のない人が化粧品についてSNSで発信することは化粧品の「感想」と捉えられるでしょう。
薬機法において、化粧品の効果や安全性を保障する内容を投稿することは禁止されています。
(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止 医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。
(医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等についてより引用)
また、化粧品を使用した感想を体験談として投稿することも、消費者にその製品の効果や安全性の保証をしているとして不適切な広告と判断されます。
(5)使用体験談等について 愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び「私も使っています。」等使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し医薬品等の効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるので行わないこと。ただし、医薬品(目薬、外皮用剤等)や化粧品等の広告で使用感を説明する場合や、タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合は、本項には抵触しない。この場合には、使用感が過度にならないようにすること。
(医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等についてより引用)
ただし、化粧品の使用感を説明する場合はSNSやYouTubeへの投稿が認められています。
化粧品の使用感の具体例としては、次のようなワードが考えられます。
- 使いやすい
- のびがいい
- ベタつき感がない
- サラッとしている
- 香りがいい
化粧品会社の社員の製品について感想を投稿する場合は、一般の人より影響力が大きいと考えられます。そのため、使用感に関しても過度な内容は避けましょう。
会社名を伏せればOK?
化粧品会社の社員が、会社名を伏せて商品紹介を行う場合でも、他社製品の誹謗中傷や他社と比べた内容を投稿することは不適切とされています。
また、化粧品会社によっては従業員であることを伏せて商品の紹介をすることを禁止している場合もあるため、入社時のルールや就業規則について確認しておきましょう。
また、他社の誹謗中傷や他社製品の比較広告は、暗示的な内容でも薬機法に抵触する恐れがあります。他社名を伏せてA社、B社などの形で自社製品と比較した内容も投稿しない方が無難でしょう。
“ステマ”と見做される可能性も
社員が会社名を伏せて自社製品を宣伝するなどの行為は「ステマ」と判断されて非難やネット炎上の原因になる可能性があります。
ステマ(ステルスマーケティング)とは、SNSやYouTubeなどによって消費者に宣伝だと悟られないように宣伝するマーケティング手法です。
ステルスマーケティングは、中立的な立場での批評を装ったり、当の商品と直接の利害関係がないファンの感想を装ったりして行われる。商品の特長の紹介や、評価システム上の評価をつり上げるなどの行為により、多くのユーザーの目に触れさせ、またユーザーの商品に対する印象を上げることが主な目的とされる。 インターネット上では、ショッピングサイトのユーザー評価の投稿欄や、ブログ上の体験記、口コミ情報サイトなどがステルスマーケティングに利用されやすい。有名人などがブログでお気に入りの商品を紹介する記事の中にも、ステルスマーケティングに該当する例があるとされる。 ステルスマーケティングを行うことで、バイラルマーケティングやバズマーケティングを意図的に引き起こすことが期待できる。ステルスマーケティングはそれが宣伝であることを意図的に隠すやり方であり、一般的にはモラルに反するとされる。ステルスマーケティングを行っていることが発覚した場合、非難の対象となる場合が多い。
(Weblio辞書|ステルスマーケティングより引用)
ステマは問題のある投稿として非難やネット炎上が起こりやすいといわれています。
ネット炎上は会社の評判に直結するため、問題とされやすい行為は未然に防ぐことが大切です。また、炎上後の誠意ある対応も会社のイメージを守るために不可欠です。
まとめ
最近ではSNSやYouTubeで発信する人が多くなりました。化粧品会社の社員がSNSやYouTubeを使う場合は、会社か個人のアカウントかは関係なく、他社の批判や自社と他社の比較を行うことは不適切です。
ネット炎上は会社のイメージダウンに直結します。SNSやYouTubeを運用する際は、薬機法やガイドラインに違反する内容を投稿しないよう、十分注意しましょう。
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能