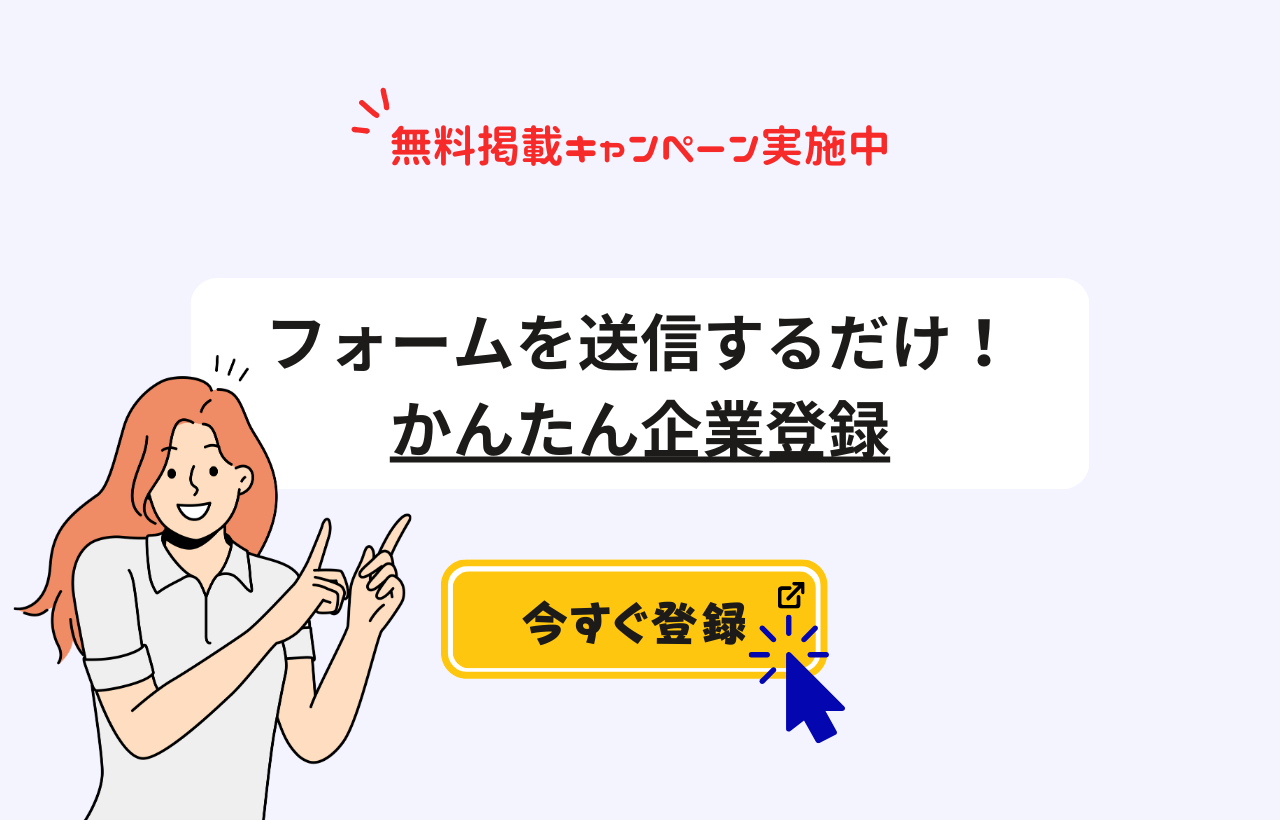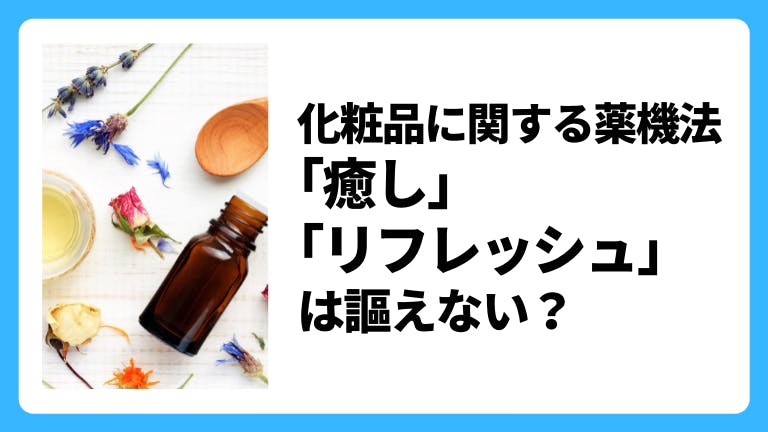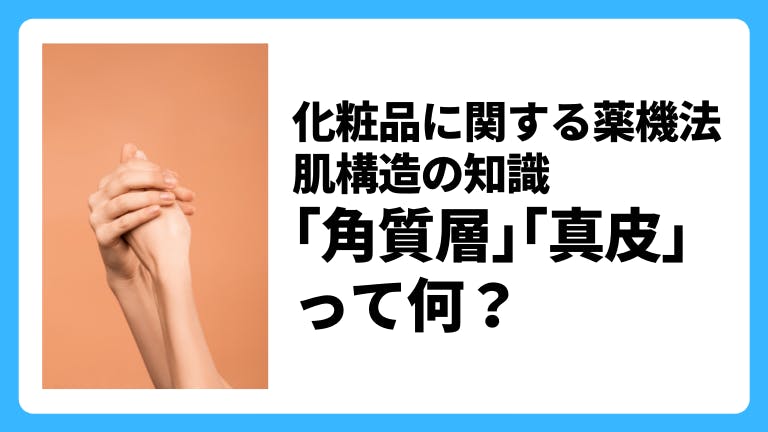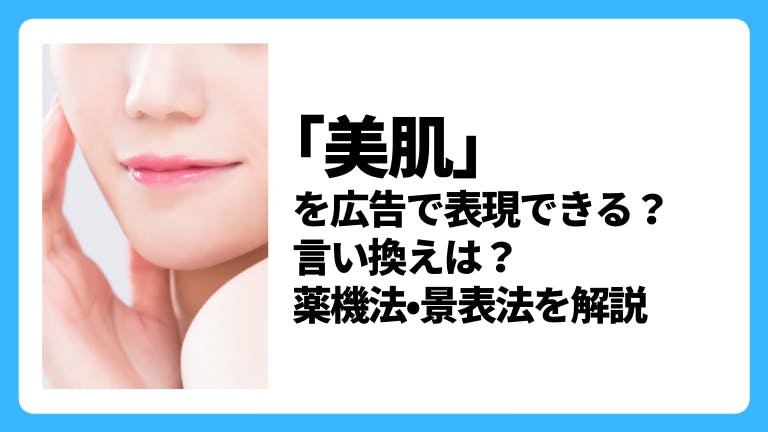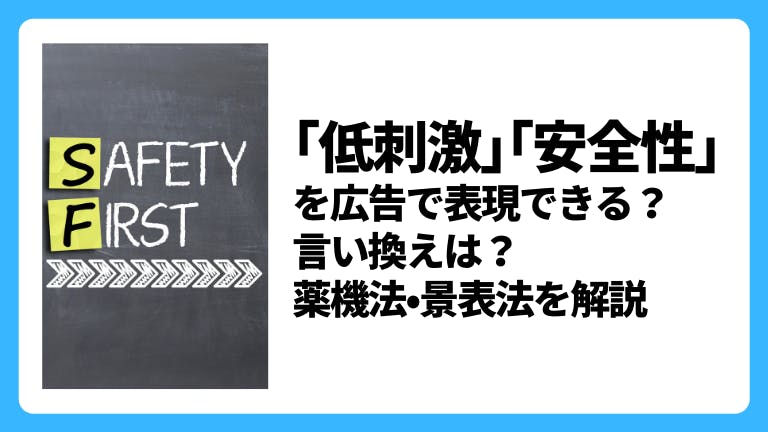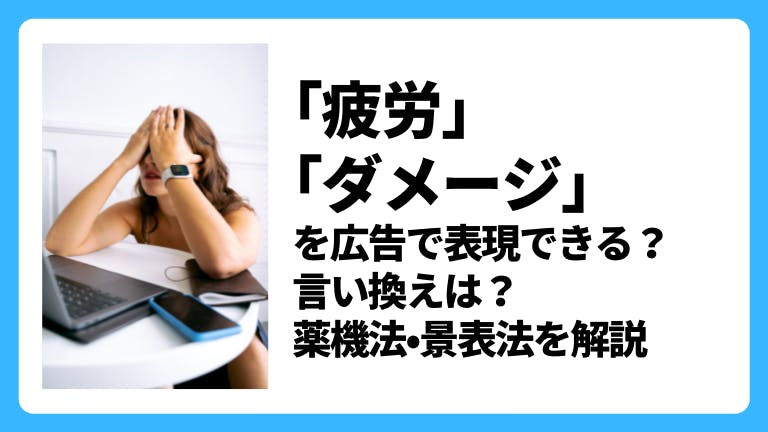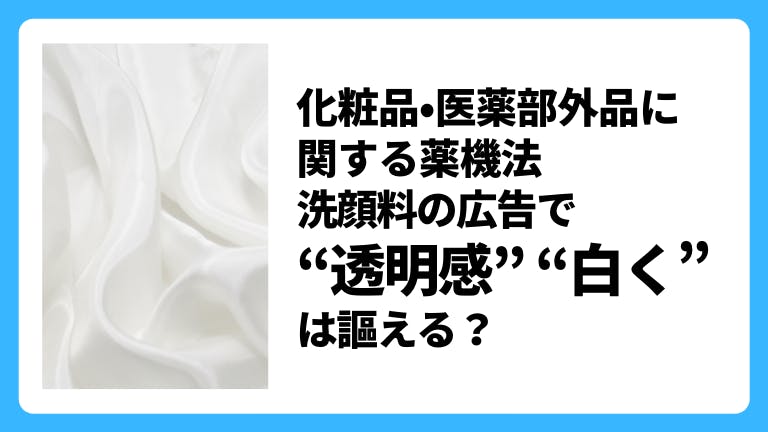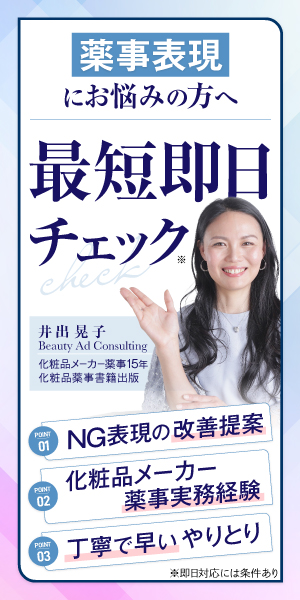最終更新:2024/07/25
カラー印刷とは?仕組みを解説

印刷物を手にする時、カラーかそうでないかで、ずいぶんと印象が違います。かつて印刷物は白と黒だけのモノクロ印刷が一般的でした。モノクロにはモノクロの良さがありますが、やはりカラー印刷は見る人にたくさんの情報を伝えてくれます。
現在のカラー印刷は、フルカラー印刷とも言われています。かなり微妙な色も再現できていますが、実はフルカラーと言われていても、実際はたった4色のインクが使われていることが多いのです。
今回はカラー印刷の仕組みについて解説します。これを理解すると、なぜ印刷機によってインクの色数が違うのか、そしてどんな仕上がりになるのかも理解できるはずです。
カラー印刷の仕組み
カラー印刷で使われる4色は、以下の通りです。
- シアン(藍)
- マゼンタ(紅)
- イエロー(黄)
- ブラック(黒)
この4色を合わせて、あらゆる色を作り出しているわけです。
色の三原色とは
ブラック以外のシアン、マゼンタ、イエローのことを、色の三原色と言い、この3色を割合を変えて混ぜることで、どんな色でも作れると言われています。
この4色は細かな点の集合体として印刷されます(この点を網点といいます)。この点の密度が高ければ濃い色になり、低ければ薄い色になります。印刷物のある部分の色の点が、シアン50%、イエロー50%で印刷されれば私たちの目には緑色に映るのです。
どんな色でもこの4色で再現するため、カラー印刷は4色印刷と呼ばれることもあります。
4色印刷にブラックが必要な理由
色の三原色があれば、どんな色でも作れるはずなのに(もちろんブラックも作れます)、インクの中にブラックが入っているのには理由があります。
三原色を混ぜて作ったブラックは、ぼやけた印象になってしまいます。文字などは輪郭がはっきりせず、読みにくいことがあります。そのため、シャープで見やすい黒にするため、わざわざブラックのインクが存在しているのです。
カラー印刷で6色印刷となる理由
4色のインクであらゆる色を再現できるカラー印刷ですが、苦手な色もあるため、色を増やして6色印刷となることがあります。苦手な色とは、基本の4色をかけ合わせてもできない色・つまり蛍光色と金や銀などのメタリックカラー、そして白です。
苦手な理由とは
蛍光色は基本の4色にはない「蛍光体」が含まれています。蛍光体のない色をいくらかけ合わせても、発光したような色を作ることはできません。
同じ理由でメタリックカラーと白も4色をかけ合わせて作ることができません。これらの色を使いたい場合には色を追加する必要があります。追加する色のことを特色と呼んでおり、蛍光色の場合は1色を追加するので5色印刷となります。
色を増やすとコストも増える?
多くのカラー印刷が4色で行われていることを考えると、6色印刷はまだまだ少数派のため、コストが高くなります。しかし、広告やパンフレットなどに蛍光色やメタリックカラーを効果的に使うことができれば、見る人に強いインパクトを与えることができ、結果的にかかったコストを上回る利益を上げることにつながります。
先程あげた美術書や、会社のロゴなどを正確に表現したいときにも、6色またはそれ以上の印刷が必要になります。会社のロゴは、企業のイメージを統一して打ち出すために、形だけでなく色も正確に再現する必要があるからです。
家庭用プリンターでの6色インクとは
家庭用のプリンターで使われているのも、基本は4色インクですが、現在は6色のインクが使われることも増えています。具体的には基本の4色にブラックとグレーが追加されて、6色となっていることがあります。
追加されているブラックはドキュメント印刷に向いている顔料系で、一層文字をはっきりと読みやすく印刷できます。そして、グレーを追加することで色の濃淡をより細かく再現できるようになっています。
インクによってはライトシアンとライトマゼンタが追加されていることもありますが、これも色の濃淡を細かく再現するためでしょう。
4色よりもコストは高くなりますが、6色印刷の方が、全体的に明るい仕上がりになり、満足感が得られるはずです。印刷物に画像が多い場合には6色を選ぶなど(反対に文字が主体の印刷物なら4色のインクで十分だと言えます)、目的によって4色か6色かを選ぶと良いでしょう。
カラー印刷を思った通りの色で仕上げるために
4色印刷を選ぶ場合ももちろんですが、高いコストを承知で6色印刷を選ぶ場合、思い通りの色で仕上げて欲しいと思うのは当然です。
ところが、往々にして出来上がってみたら、考えていたよりも暗い色合いに仕上がってしまったということがあります。しかも、それは決して珍しいことではないのです。なぜ、そんなことになるのでしょうか。
光の三原色とは
最近はパソコンでデータを作って、そのまま印刷を依頼することが多いことが原因になっているようです。同じ赤色でも、パソコンの画面で見る色と、印刷物の色は違って見えます。先程、色の三原色を紹介しましたが、パソコンやテレビのモニターで見る色は、光の三原色で表されます。 光の三原色とは、以下の3色です。
- レッド(赤)
- グリーン(緑)
- ブルー(青)
色の三原色と光の三原色では表現できる色の範囲が違います。色の三原色では、色をかけ合わせるほどに暗くなりますが、光ではかけ合わせるほどに明るくなるという性質があるのです。そのため、パソコンの画面で表現されている色を再現して印刷しても、どうしても色が暗くなってしまいます。
対策は自分の目
印刷物を思い通りの色で仕上げるには、自分の目で確かめるのが一番です。パソコンデータを自宅のプリンターで印刷して確認する方法もありますが、それでは印刷機やインクの違いで、やはり仕上がりが違ったということになりかねません。
確実な方法は業者に色校正(簡易校正、本紙色校正、本機校正など種類がありますので、業者に相談すると良いでしょう)を出してもらうことです。これなら実際に印刷をしてもらう機械で印刷したものを自分の目で確認することができます。
なお、印刷物の色はそれを見る照明にも左右されます。蛍光灯なのか、白熱灯なのかによって色味がまったく違って見えますから、注意が必要です。できれば、いろいろな照明の光で印刷物をチェックすると良いでしょう。
まとめ
カラー印刷の仕組みを説明しました。4色でも十分ですが、色を増やすことで、より自然で実物に近い色が再現できるのは事実です。
現在は技術の向上により、4色印刷も決して見劣りがするわけではありません。変わった色を使う必要がない、画像が少なくテキストが主役の印刷物なら、十分な仕上がりが望めます。
しかし、美しい画像や特別なロゴを大切にしたいなら、5色、6色、ときには8色印刷を考えてください。コストは上がっても、きっと美しい印刷物を作れます。そして、それを見る人の心をとらえることができるはずです。
また、カラー印刷を行う際に起こりがちな、仕上がりの色が暗く沈んでしまう問題を解決する方法も紹介しましたので、ぜひ、参考にしてください。
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能