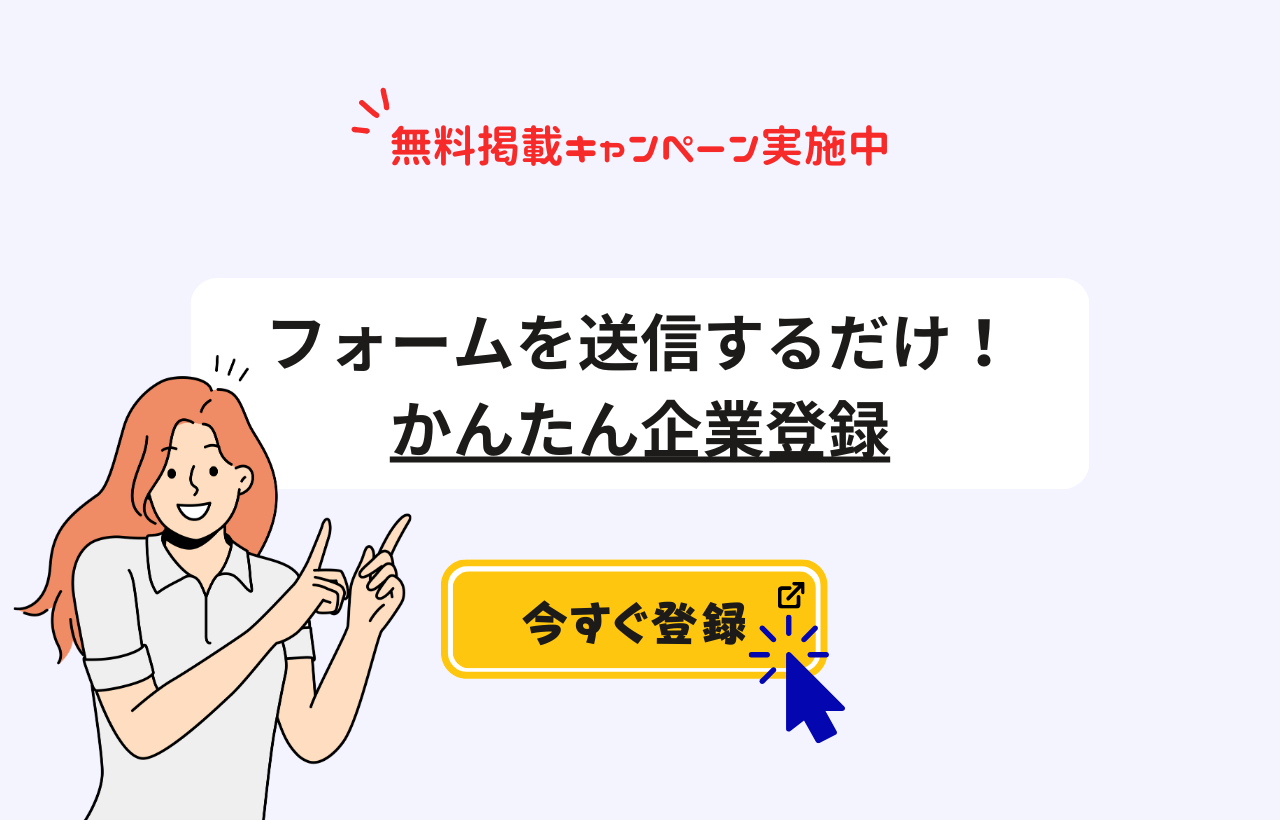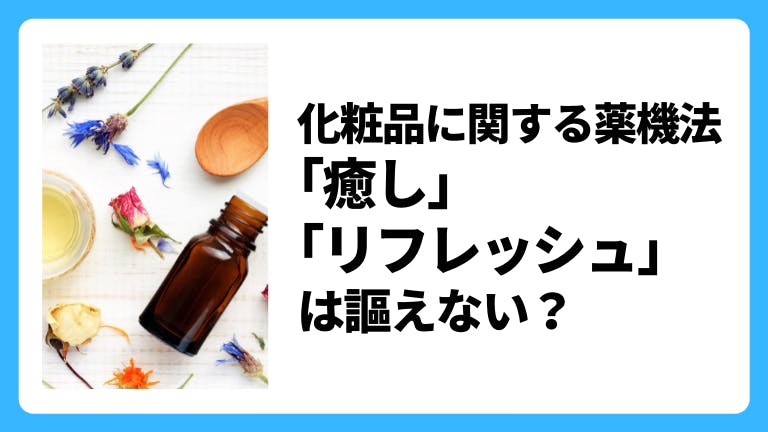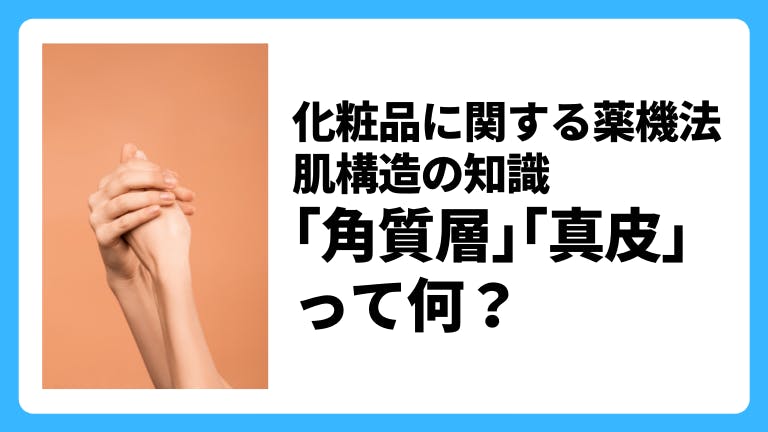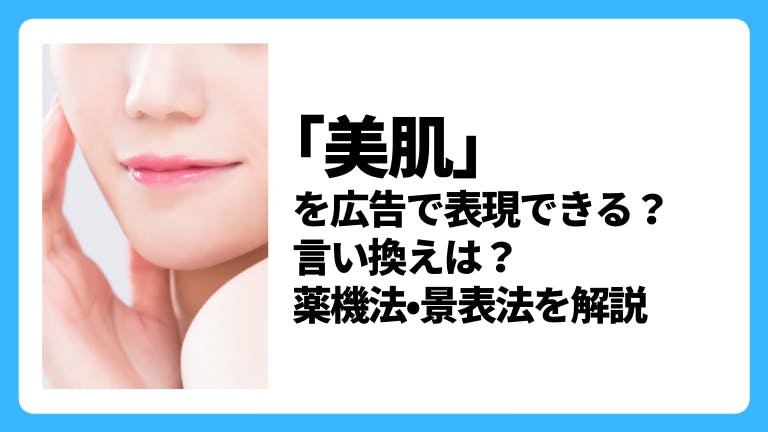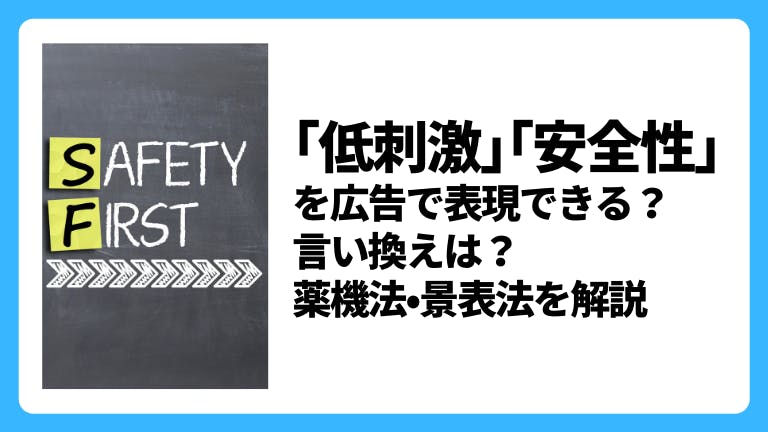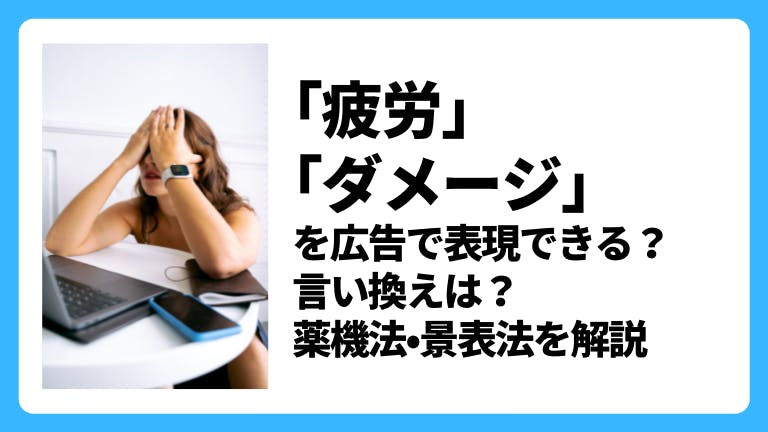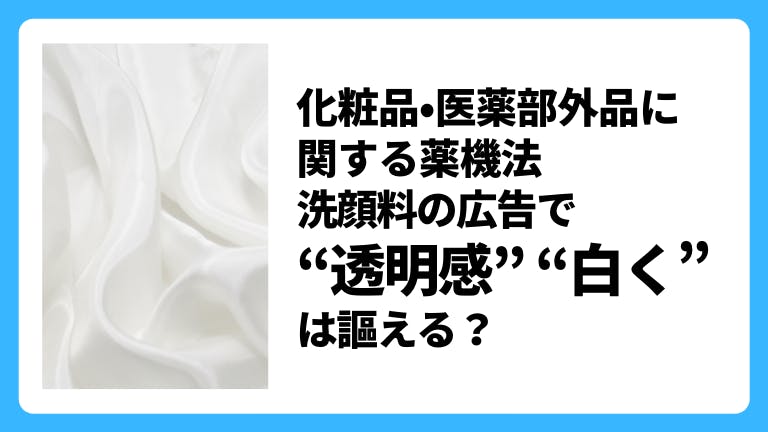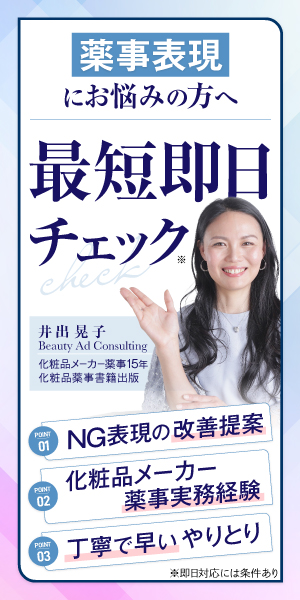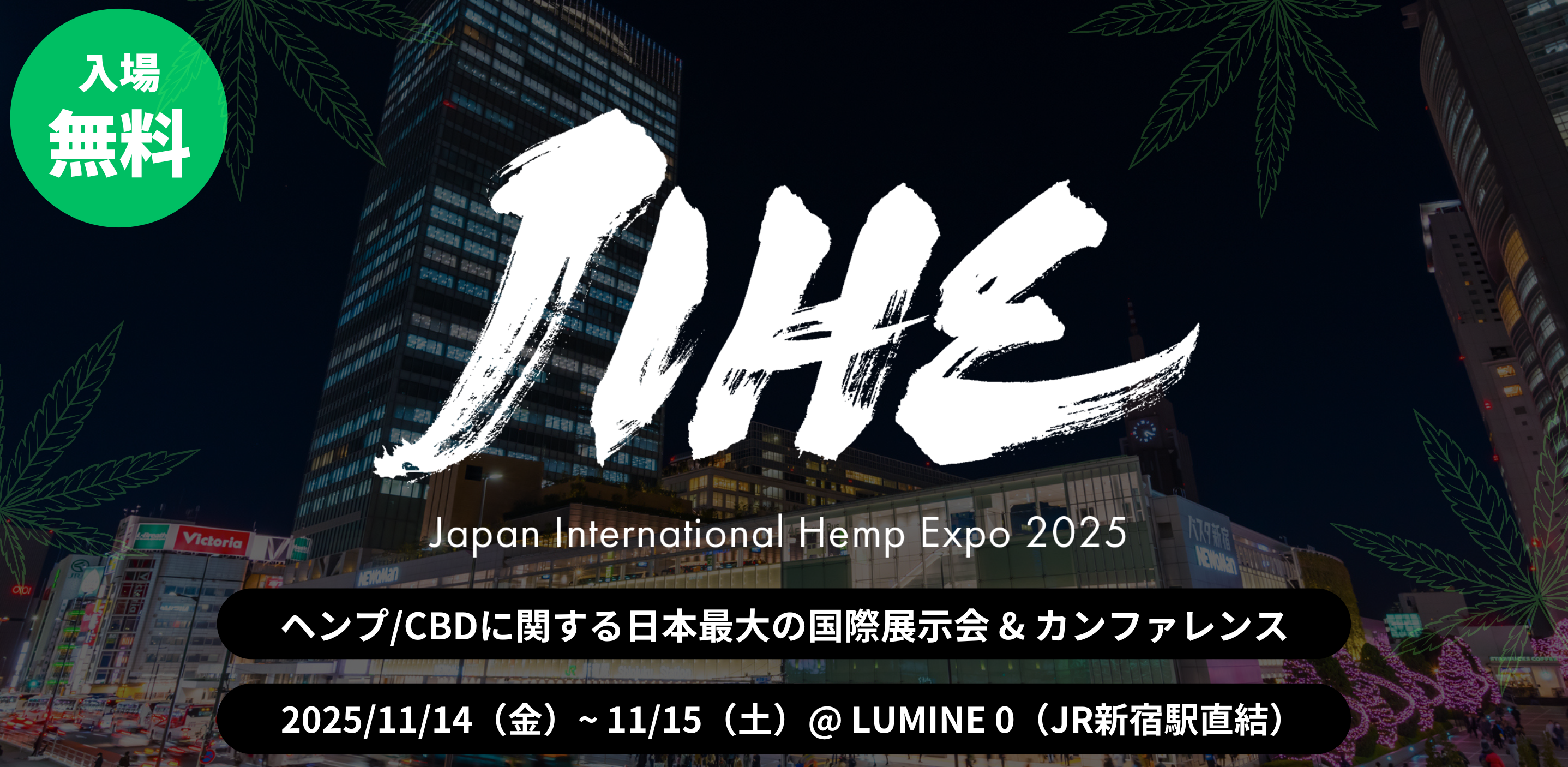
最終更新:2024/07/04
SNS投稿で訴えられる処罰とは?投稿依頼で注意することと薬機法
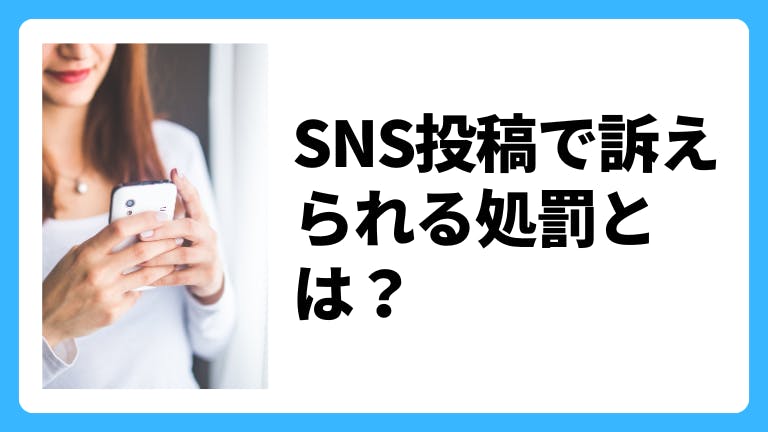
広告宣伝においてSNSの活用は必要不可欠な時代と言えます。
インフルエンサーという職業としての認知や、SNSマーケティングは各企業が参入しており、全世界を市場として行われています。インフルエンサーに関わらず、一般の生活者が日常的に使用するSNS利用者は若年化し、子供から活用する社会になりました。
警察庁はネット上の誹謗中傷、人権侵害が平成27年時点で1万件を超え、年々増加していると発表しています。
広告宣伝のマーケティングで独自にSNSを活用したり、インフルエンサー等に投稿依頼をすることもあるでしょう。
ここでSNSマーケティングにおいて注意すべき点や、訴えられる処罰について知っておきたいと思います。
SNSの投稿依頼 注意するべき処罰とは
誹謗中傷とは、事実無根の内容を悪口とし、公言することで他人を傷つけることを指します。問題となる誹謗中傷はの多くはネット上、つまりSNSや掲示板の投稿です。
まず刑事責任についてまとめてみましょう。
- 脅迫罪
- 強要罪
- 名誉毀損罪
- 侮辱罪
- 信用毀損及び業務妨害罪
次に誹謗中傷という不法行為に対して民事責任があります。
- 損害賠償(慰謝料)
- 名誉回復措置
刑事責任
脅迫罪
刑法第222条によると
- 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した者
- 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した者
これらを2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するというものです。 匿名であっても「死ね」「殺す」など生命、身体はじめ自由、名誉、財産に害を加える告知を投稿し、かつ具体的な期日をほのめかすような内容は脅迫罪に値します。
強要罪
刑法第223条によると
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
先ほどの脅迫罪よりエスカレートした内容です。脅迫に加え、人に義務のないことを行わせとありますが、このような事例があります。
ある店にクレームを入れた夫婦が、店員に土下座をさせ、その様子をSNSで拡散しました。店舗名や、氏名など個人情報を公開した上に、自宅を訪問し謝罪するという命令を出し、個人の権利義務を妨害したとされます。
名誉毀損罪
刑法第230条によると、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、事実の有無に関わらず3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処するというものです。
侮辱罪
刑法第231条によると、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は1年以下の懲役か禁固、若しくは30万円以下の罰金、又は拘留か科料に処するというものです。
侮辱罪については、脅迫罪のように具体的な期日をほのめかす内容がなくても該当する可能性があります。例えば、「死ね」「死ね」と何度も同じように投稿することはこれにあたります。
信用棄損及び業務妨害罪
刑法第233条によると、虚偽の風説を流布し、また偽計を用いて人の信用を毀損し、業務を妨害した者は3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処するというものです。
これらの刑事罰に伴い、民事責任があります。慰謝料という損害賠償請求が生じ、損害賠償とともに名誉を回復するのに適当な処分を命じられることがあります。このことを名誉回復措置といい、謝罪広告などが一般的とされています。
発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは、インターネットで他者から誹謗中傷があった場合、発信者の情報(住所、氏名、メールアドレスなど)を特定するための手続きのことを言います。発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づいて行うことができます。
インターネットでの発信は匿名性が高く、誹謗中傷などがあった場合、その発信者を個人では容易に特定できません。誹謗中傷を受けた被害者が損害賠償責任請求を行い、必要な賠償を受けるためには、発信者(加害者)の特定が必要となります。また被害届を提出する際にも、発信者(加害者)が特定されていないと、適切な処分が下されません。
発信者情報開示請求は以下の流れで行われます。 ①コンテンツプロバイダ(サイトの運営者)に対し通信ログと言われるIPアドレスなどの開示を求める ②裁判所がIPアドレスの開示を決定 ③コンテンツプロバイダがIPアドレスを開示 ④アクセスプロバイダ(インターネット業者)に対して、発信者の情報開示を求める ⑤裁判所が発信者の情報開示を決定 ⑥アクセスプロバイダが発信者の情報開示を行う
プロバイダ責任制限法は2022年10月1日に改正され、手続きが簡易化・迅速化されました。 今までは発信者の情報開示までに2回の裁判手続が必要でしたが、1回での裁判で速やかに行えるようになりました。そのため誹謗中傷の発信日時から時間が経ちすぎたことにより、通信ログが削除されて発信者の情報が無くなってしまうといった問題点が改善されました。
SNSの投稿依頼と薬機法
SNSの投稿依頼をする場合、依頼する企業は投稿内容が薬機法に違反しないよう注意する必要があります。 薬機法の第10章では、
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
と定められています。 出典:**医薬品等の広告 e-Gov法令検索**
薬機法には、商品の広告をする際に使用してはならない細かな表現が定められています。例えば、化粧品において効果・効能に関する表現は禁止されているため、「肌が白くなった」などの表現は使えません。商品の使い方や、使用感(テクスチャー等の表現)については表現が可能とされています。
しかし、SNS投稿を依頼されたインフルエンサーは、薬機法に関する十分な知識を持ち合わせていないことがあります。インフルエンサーが商品を使用した感想を思いのままに発信してしまうと、表現が薬機法に抵触する可能性があります。 そのため企業側はSNSの投稿依頼をする場合に、しても良い表現や、ダメな表現を確認し、インフルエンサーと十分にコミュニケーションを取っておくことが必要です。
もし薬機法に違反する表現があった場合、投稿を依頼した企業側に責任が問われることになります。またインフルエンサー側にも責任が問われ迷惑をかけることになるので、投稿内容には十分注意しましょう。
まとめ
SNSによる広告宣伝やSNSマーケティングは近年莫大に増加しています。特別な資格がなくてもできるので、気軽に始める人も多いのではないでしょうか。
しかしSNSを投稿依頼する場合には、法律に抵触する表現や、処罰の対象となる行為を知っておく必要があります。知らず知らずのうちに使った表現が、法律に抵触している可能性もあるからです。
自分自身の身を守るためにも、確かな知識を身につけて安全に利用することが重要です。
資料請求・お問い合わせを増やす方法
資料請求・問い合わせを増やすためには、企業がどんな事業をしているのかを知ってもらうことが重要です。Beaker mediaの企業情報掲載サービスでは会社の事業内容や特徴、取得免許や対応ロット数などを掲載し、化粧品・健康食品に専門性の高い多くのユーザーへ会社情報を発信することができます。
Beaker mediaで会社情報を掲載しませんか?
Beaker mediaで会社情報を掲載するメリットは以下の通りです。
- 業界特化型メディアでの露出増加
- 化粧品、健康食品原料の専門分野でのターゲットリーチ拡大
- 企業情報や製品の逐次更新が可能