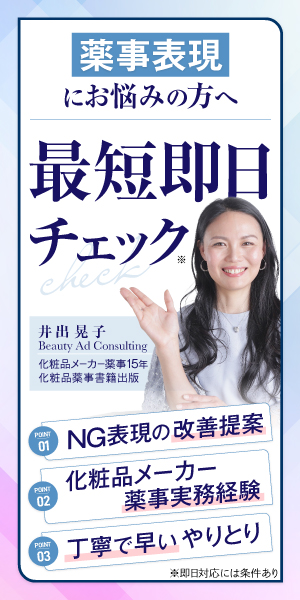表示名称成分詳細
温泉水
成分番号(JP number): 555559
- INCI
- (NOTHING)
- 定義(Description)
- 本品は、温泉から湧出した湯又は水である。
- 日本の規制情報(Japanese regulation information)
- 中文inci(CN/中国名称)
- -
- 中国の規制情報(Chinese regulation information)
- -
- 韓国inci(KR/ハングル/성분명)
- CAS No.
- -
- EC No.
- -
- EUの規制情報(Restriction/Annex/Ref#)
-
原料情報
温泉水 / (NOTHING)
温泉水とは
温泉水とは、温泉法が定める基準を満たした湧き水です。
温泉法での定義を記載します。
「この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。 引用先:昭和二十三年法律第百二十五号 温泉法 第一章 第2」
別表に記載のある、温度また成分を記載します。
「別表
温 度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
摂氏25度以上
含有物質名:含有量(1kg中)
ガス性のものを除く溶存物質:総量1,000mg以上
遊離炭酸:250mg以上
リチウムイオン:1mg以上
ストロンチウムイオン:10mg以上
バリウムイオン:5mg以上
第一鉄または第二鉄イオン:10mg以上
マンガンイオン:10mg以上
水素イオン:1mg以上
臭素イオン:5mg以上
ヨウ素イオン:1mg以上
フッ素イオン:2mg以上
ヒドロヒ酸イオン:1.3mg以上
メタ亜ヒ酸イオン:1mg以上
総イオウ:1mg以上
メタホウ酸:5mg以上
メタケイ酸:50mg以上
重炭酸ナトリウム:340mg以上
ラドン:20(100億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩:1億分の1mg以上
(昭和二十三年法律第百二十五号 温泉法 附則 別表)」
採取する温泉源により成分構成は変わってきます。
成分構成の違いで配合する目的が変わっていきますので、各温泉源の特徴を理解するこも重要です。
例として、温泉水の特徴的な成分である、二酸化炭素、硫酸ナトリウム等を紹介します。
二酸化炭素を多く含む温泉水は「炭酸泉」と呼ばれ、含有二酸化炭素の抹梢血管拡張作用による循環改善が認められています。
循環改善作用により、身体を温める効果があるとされています(8)。
硫酸ナトリウムを含む温泉水に関しては、ナトリウム-硫酸泉「芒硝(ぼしょう)」と呼ばれています。
硫酸の刺激により、ヒスタミンの遊離促進による、血管拡張作用により保温効果を発揮します(7)。
炭酸泉、ナトリウム-硫酸泉以外にも群馬県の草津温泉、北海道の豊富温泉、フランスのアベンヌ温泉などアトピー性皮膚炎などの皮膚疾患に有効ということが分かっています。
これは温泉成分の作用により、皮表黄色ブドウ球菌が減少し、アトピー性皮膚炎の症状が改善したと報告もあります(4)(5)(6)。
化粧成分の中で温泉水は、ベース成分、保湿成分、バリア改善成分に分類されています。
具体的な製品としては、スキンケア化粧品、シート&マスク製品、ボディ&ハンドケア製品、洗顔料、洗顔石鹸、クレンジング製品、シャンプー製品、ヘアケア製品です。
保湿成分、バリア機能改善
温泉水のバリア機能改善作用は、角質層の保湿作用、及び角化促進作用が関係しています。
保湿が不十分の角質層は、水分量の低下、角質層のひび割れと状態が悪化してきます。角質層の悪化は、皮膚表面の状態悪化に直結します。皮膚表面の亀裂、落屑、鱗屑が起こり、肌荒、皮膚のバリア機能の低下に繋がります(3)。
また、皮膚の乾燥が続くことによってターンオーバーが低下、角化不全が起こり、角質層が普段よりも厚くなり剥がれ落ちます。
メタケイ酸およびCaイオンを含む温泉水が角質層の保湿、また角化を促進し、皮膚を正常な状態に戻す作用があるのです(2)。
保温、血流改善
温泉水の中でも炭酸泉、ナトリウム-硫酸泉は、血管拡張作用から血流改善、保温効果を持つことが分かっています(7)(8)。
ベース成分
化粧品のベース成分としては水性成分、油性成分、界面活性剤、顔料・粉体成分のうち、水性成分として分類されます。保湿効果から、肌に潤いを与える目的で配合されます。
安全性
安全性に関しては、30年以上の使用実績があり、一般的な仕様に関しては問題ないと言われています。
温泉水のアレルギー治療への使用実績はあるものの、現状において、安全性を証明する実験等の報告はありません(1)。
参考文献
(1)大島 良雄(1971)「温泉とアレルギー」日本温泉気候物理医学会雑誌(35)(3-4),3-10.
(2)井上 紳太郎(2003)「皮膚に有用な温泉水成分を探る」日本温泉気候物理医学会雑誌(67)(1),12-13.
(3)高橋 康之「保湿化粧品とその作用」日本香粧品学会誌, 2018, 42 巻, 4 号, p. 280-287
(4)K Kubota, et al(1997)「Treatment of refractory cases of atopic dermatitis with acidic hot-spring bathing」Acta Dermatol Venereologica(77)(6),452-454.
(5)久保田 一雄(2016)「皮膚疾患に対する草津温泉療法」日本温泉気候物理医学会雑誌(79)(1),17.
(6)村上 慎之介(2019)「豊富温泉入浴によるアトピー性皮膚炎抑制メカニズムの解明」日本健康開発雑誌(40),105-110.
(7)古元 嘉昭, 曽田 益弘, 平井 俊一, 森末 真八, 鈴鹿 伊智雄, 藤原 敏雄, 川崎 義巳「硫酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム浴の効果 (第3報)」日本温泉気候物理医学会雑誌, 1989-1990, 53 巻, 3 号, p. 133-136
(8)萬 秀憲, 久保 裕一郎, 江口 泰輝, 河本 知二, 砂川 満, 古元 嘉昭「人工炭酸浴に関する研究」日本温泉気候物理医学会雑誌, 1983-1984, 47 巻, 3-4 号, p. 123-129,
温泉水の配合目的
- 温泉水の角質層の保湿作用
- 皮膚のターンオーバー機能(基底細胞の角化)を促進し、角質層を正常に維持する作用
- 乾燥により角質の肥厚化、角化不全の影響でバリア機能の低下した皮膚への、保湿作用と角化促進作用によるバリア機能改善作用
- 温泉水の抹消血管拡張作用による循環改善作用、保温作用
温泉水の安全性情報
一般的に皮膚刺激および皮膚感作性(アレルギー性)はほとんどないと考えられますが、詳細な安全性試験データがみあたらず、データ不足のため詳細は不明です(1)。
一般的に眼刺激性はほとんどないと考えられますが、詳細な安全性試験データがみあたらず、データ不足のため詳細は不明です(1)。
参考文献
大島 良雄(1971)「温泉とアレルギー」日本温泉気候物理医学会雑誌(35)(3-4),3-10.
日本語論文
セレクチオーズ,アベンヌ温泉水による肌の保湿と製品開発 (特集 肌の保湿と製品開発)
鈴木 能里 , ランベール ナターシャ , 伊達 朗 Fragrance journal 41(12), 67-75, 2013-12
英語論文
The effect of vehicle on skin absorption of Mg(2+) and Ca(2+) from thermal spring water.
Tarnowska M, et al. Int J Cosmet Sci. 2020. PMID: 32027379
Electromagnetic wave emitting products and "Kikoh" potentiate human leukocyte functions.
Niwa Y, et al. Int J Biometeorol. 1993. PMID: 8406976
Curri SB, et al. Clin Ter. 1997. PMID: 9528201 Italian.
Wang C, et al. J Med Entomol. 2009. PMID: 19496428